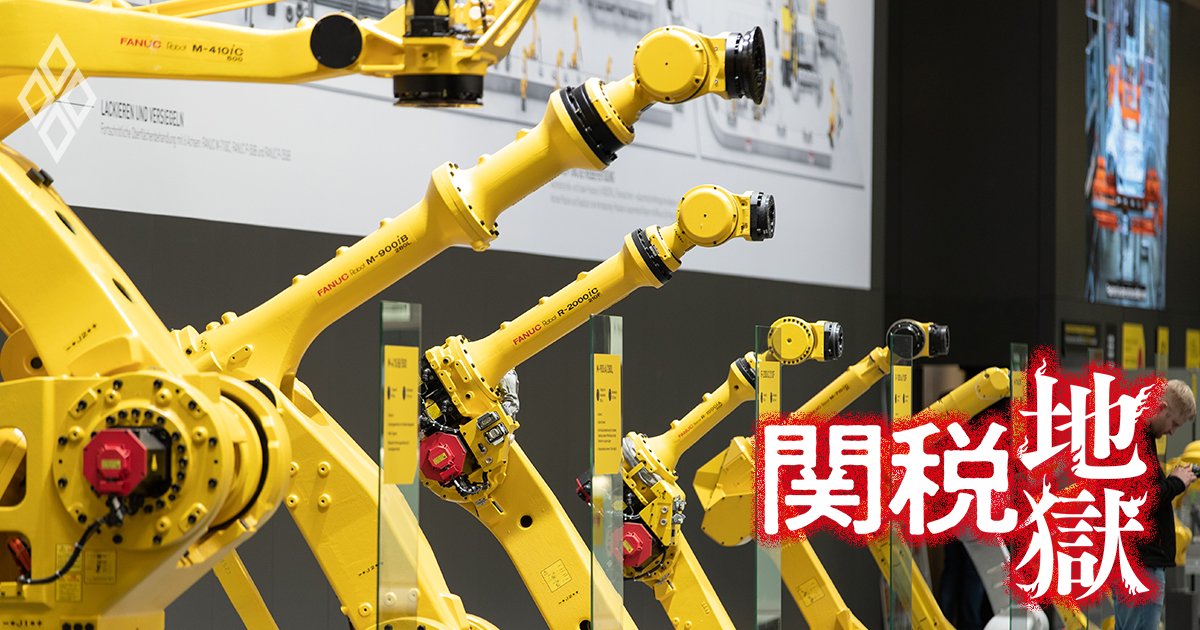Photo:HONDA
Photo:HONDA
ホンダが4月1日付で社長を交代した。新社長に就いた三部敏宏氏は、就任会見で「電動化100%」「死亡事故ゼロ」などの壮大な目標を発表。夢のあるビジョンをぶち上げる姿は、米テスラのイーロン・マスクCEOを彷彿(ほうふつ)とさせた。だが現在のホンダには、官僚的な縦割り体制や、リコール問題などの課題が山積だ。三部新社長はこれらを解消し、かつて“ホンダ神話”と称された頃のチャレンジ精神を社内に取り戻せるのか。(ジャーナリスト 井元康一郎)
「あの頃のホンダ」が戻ってきた
新社長のスピーチに覚えた懐かしさ
「“あの頃のホンダ”を思わせる強気発言だ」――。ある完成車メーカーの元幹部は、ホンダの三部敏宏新社長が4月下旬に開いた就任会見のスピーチを聞いてこう感じたという。
何しろ三部社長は、売上高、営業利益、販売台数といった経営指標の目標値や、現在の経営課題とその解決策といった“お決まり”の内容にほとんど触れなかったのだ。その代わりに示したのは、2040~50年という遠い未来に実現したいホンダの姿だった。
経営トップが目先の数字にとらわれずに大きな夢を語ることは、“ホンダ神話”と呼ばれるほどの急成長を遂げた20世紀にしばしばあったが、2000年以降は「めっきり減っていた」と元幹部は振り返る。
会見の動画が一般公開されているので細かい内容は割愛するが、主なポイントは(1)40年までに、世界で販売する新車を全てEV(電気自動車)とFCV(燃料電池車)に切り替える、(2)50年にホンダ車が関与する交通死亡事故をゼロにする、(3)航空、宇宙、ロボット、陸上、海洋に関連するモビリティの研究を進める――といったところだ。
これらの目標はスケールがあまりにも大きく、「本当に実現できるのか?」と勘繰りたくなるものばかりだが、冒頭の元幹部は三部社長の強気な姿勢が懐かしかったという。
「21世紀以降、ホンダは正論ばかり言うメーカーに成り下がったが、昔はもっと暴れん坊だった。失敗も多くあったが、途方もない目標を公言して業界を驚かせ、実現させてきた。その最たる例がF1参入であり北米進出だ。強気な姿勢はいつしか失われたが、三部社長は突然、当時に戻ったかのような目標を掲げた。トヨタ経営陣は『先に言われた』と悔しがっているのではないか」(元幹部)
また、三部社長は会見で、目指したいビジョンをまとめたショートムービーを披露したが、これもかなり壮大なものだった。
何しろ映像では、自動運転車が道路を走り、船が海を進み、大型ドローンやジェット機が空を飛び、ロケットが宇宙へ向かう世界が描かれていたのだ。クライマックスとなるシーンでは、月に見立てた白い円の中に「HONDA」の文字が浮かび上がった。
「これがホンダの世界観です」。少し照れ笑いを見せながら、三部社長はこう述べた。
だが現状、映像の中で実在する製品は「ホンダジェット」のみ。人の手が不要な自動運転車はまだ開発段階であり、船やロケット、ドローンなどは手掛けていない。今の段階ではほぼ全てが空想の産物であり、形にするには膨大な資金と時間がかかる。
実現できるかはともかく、野心的な目標を掲げて注目を集める――。そんな狙いが透けて見えた三部新社長のプレゼンテーションは、米テスラのCEO(最高経営責任者)であるイーロン・マスク氏の手法に似ている。