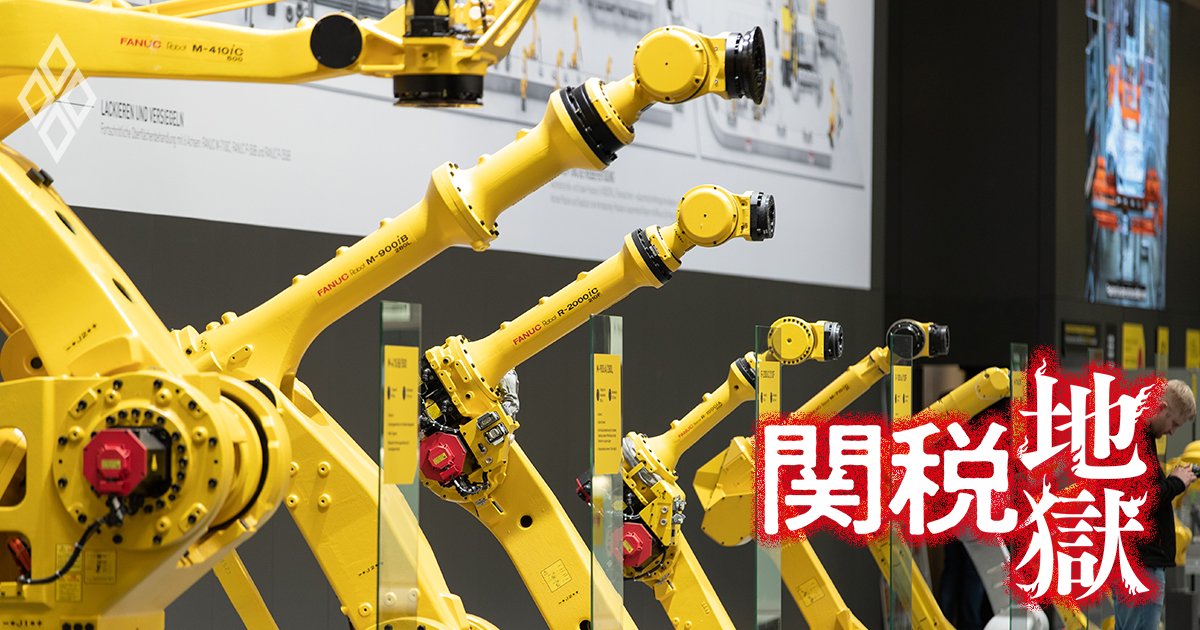Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
北京オリンピックが開催されていた時期の中国で五輪を凌駕(りょうが)するほど話題になったことがある。それは、中国農村部で女性が人権をないがしろにされながら暮らしている様子を映した「ある動画」についてだ。ショッキングな映像に国民からは批判の声が上がり、真相の追及に乗り出す人も現れた。そして過熱した世論はついに国をも動かしたのである。(日中福祉プランニング代表 王 青)
鎖につながれ、小屋に閉じ込められた女性…
衝撃的な映像が中国で瞬く間に「拡散」
1月28日。中国では最も重要な伝統の祝日「春節」を控えている中、中国版TikTok「抖音(ドウイン)」のあるアカウントに投稿された一本の動画が国中に拡散され、中国社会に大きな衝撃を与えた。
撮影された場所は中国東部の江蘇省徐州市豊県。その動画に映し出されていたのは、ゴミが散らばったうす暗い小屋に、薄汚れたセーターを着た一人の中年女性が寒そうに震え、脅えている様子であった。足元に凍っているかのようなお粥が置かれている。そして、彼女の首にはなんと、鉄の鎖がつながれているというショッキングな映像だった。
これは一体、どういう状況なのか? 動画を見た人は全員、自分の目を疑ったに違いない。動画は瞬く間にSNSで拡散された。「女性は地元の出身ではなく人身売買されてこの地に来た」「50代の村民との間に8人の子どもがいる」「歯がほとんど抜け落ちていて、舌の先が欠けている」「精神疾患の疑いがある」など、さまざまなうわさが瞬く間に流れた。