スシローの大株主は、日本の投資ファンド、ユニゾン・キャピタルから英大手ファンドのペルミラに変わった。ペルミラは、グローバル化とさらなる国内市場の開拓、デジタル化による生産性の向上にスシローの成長の可能性を感じていた。そこでスシローの可能性を最大限に引き出すトップとして起用したのが、水留浩一だった。ペルミラは、なぜ水留を社長にしたのか。そして、どうやって、さらなる企業価値の向上を実現したのか。その舞台裏を探ってみた。(名古屋外国語大学教授 小野展克)
ペルミラが感じたスシローの伸びしろ
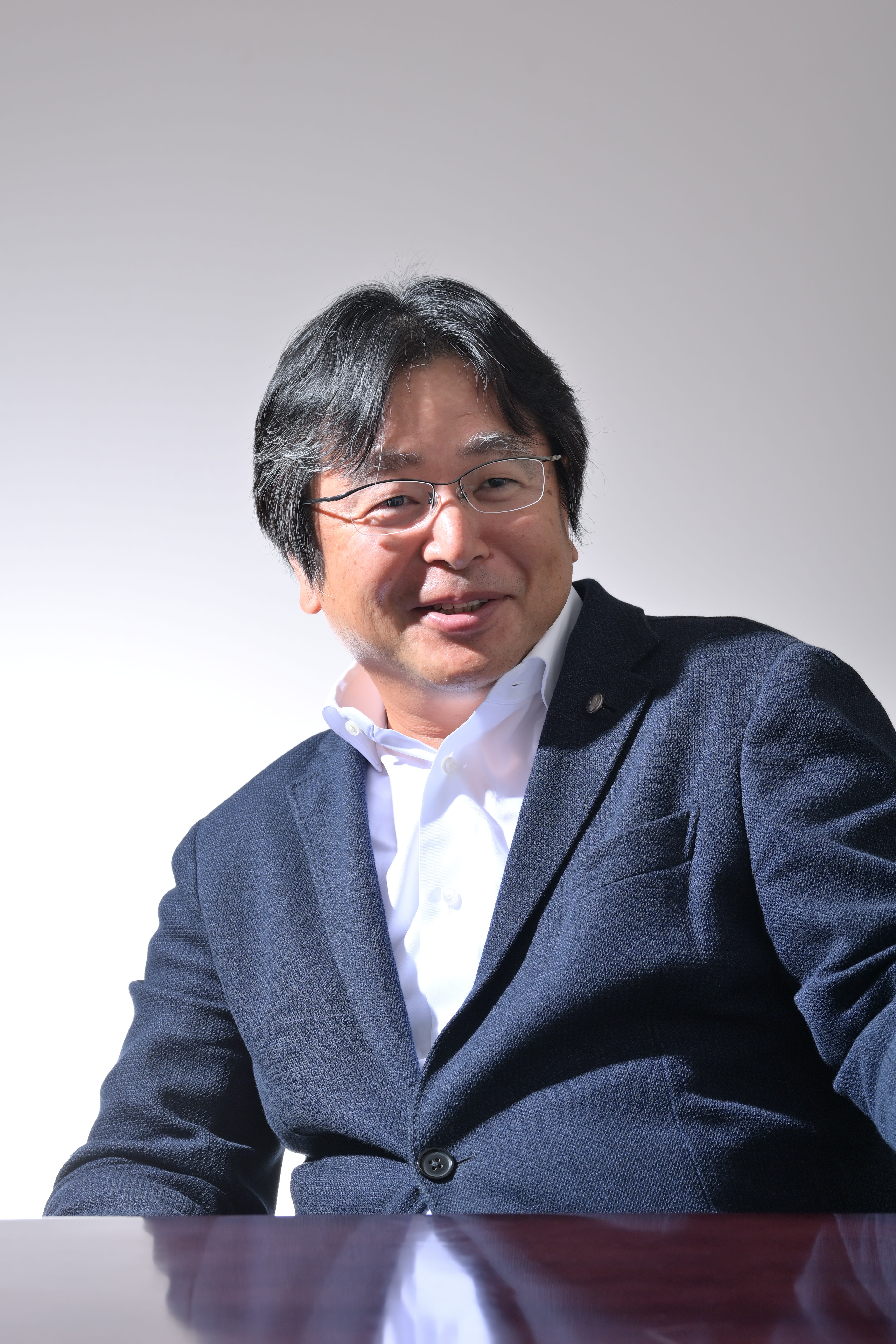 水留浩一氏(撮影:近藤宏樹)
水留浩一氏(撮影:近藤宏樹)
日系のユニゾン・キャピタル(以下、ユニゾン)に対して、英系大手のペルミラはグローバルなネットワークを誇り、外食産業の企業価値向上にも実績があった。
しかし、ファンドが頭脳戦で導入する改革や収益の向上策は、ほとんどユニゾンがやり尽くしていた。そんな中、ペルミラは、スシローのどこに企業価値の向上の余地を感じていたのだろうか。
世界的に定着したすし人気を背景にしたグローバル化の拡大が、大きな狙いの一つだっただろう。しかし、ペルミラが考えたスシローの伸びしろは、海外だけではなかった。
ペルミラ日本代表の藤井良太郎に話を聞いてみた。彼は東大法学部を卒業して大蔵省(現・財務省)に入り、ゴールドマンサックスなどで経験を積み、米系投資ファンド、コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)の日本法人立ち上げにも携わった。
「国内にも、まだまだ可能性はあると思っていました。例えば、職人1人でやっている街のおすし屋さんは、たくさんあるでしょう。職人の腕は確かに重要ですが、例えばシャリの味は、空気の含有量まで徹底的に調べましたが、スシローの『すしロボ』のシャリは決して遜色がない。おいしいネタを国内外から直接調達しているスシローが、何重にも卸にコストを払って魚を調達している街のおすし屋さんにネタの質で負けるわけがない。街のおすし屋さんは廃棄によるロスも多く、経営効率も決して良くない。スシローには、さらなる成長の可能性を感じていました」
そうなると、重要なのは誰をリーダーに据えるかだ。実は、当時スシロー内には覇権争いによる亀裂が生まれていた。それを制することができる人間が必要だったのだが、どのように選ぶかがペルミラの課題であった。







