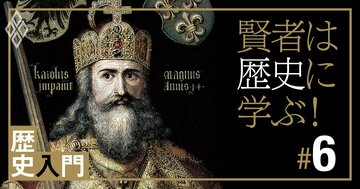歴史家ティモシー・スナイダーの『赤い大公 ハプスブルク家と東欧の20世紀』(訳:池田年穂/慶応義塾大学出版会)は、“高貴な血”を受け継ぐハプスブルク家の王子ヴィルヘルム(ヴィリー)の、歴史の激動のなかで忘れ去られていた数奇な人生を発掘し、それを東欧やウクライナの現代史と重ね合わせて高い評価を得た。原題は“The Red Prince; The Secret Lives of a Hapsburg Archduke(赤いプリンス ハプスブルク大公の知られざる人生)”。
本書の紹介文では、「ヴィルヘルムは1920年代のパリで淫蕩の日々を過ごし、30年代にはヒトラーに傾倒してファシストになり、第二次世界大戦が始まるとナチス・ドイツとソ連に対してスパイ活動を働き、戦後、ソ連の秘密警察に拘束され、53歳でキエフの牢獄で悲惨な死を遂げた」とされる。
大公(Archduke)は公爵の上位の肩書(複数の公爵領を所有する「公爵の公爵」)で、神聖ローマ帝国ではハプスブルク家だけに許された。当初は家長が「大公」を名乗ったが、その後、ハプスブルク家の王子たちを“Archduke”と呼ぶようになった。
ハプスブルク家は400年にわたって神聖ローマ帝国の皇帝位を独占し、その全盛期はスペイン王を兼ね、中南米のスペイン領も支配下に置いて「日の没するとことなし」と呼ばれた帝国(君主国)を築いた。その名家の御曹司(ただし傍流)として生まれたヴィリーは、なぜ「赤い大公」と呼ばれるようになったのか。
この問いに答えるには、迂遠なようだが、神聖ローマ帝国の成立から話を始めなくてはならない。
![ヴィリーは、なぜ「赤い大公」と呼ばれるようになったのか?[前編]ハプスブルク家と神聖ローマ帝国](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/b/-/img_bb4504f116cb2c015305a29c8584366932844.jpg) ハプスブルク家最後の皇帝フランツ・ヨーゼフの棺(ウィーンの皇帝墓所) Photo:@Alt Invest Com
ハプスブルク家最後の皇帝フランツ・ヨーゼフの棺(ウィーンの皇帝墓所) Photo:@Alt Invest Com
バルバロッサは自らの帝国を「神聖帝国」と命名し、これによって世俗を支配する皇帝の権力は、来世を支配する教皇と対等になった
476年に西ローマ帝国が滅亡してヨーロッパは「戦国時代」に入るが、為政者、聖職者、知識人らのあいだでは、神はローマの再興を求めているとの共通意識があった。日本の戦国時代に、すべての武将が「天下統一」を目指したのと同じだ。
それを実現したのがゲルマンの一部族フランク国の王カール(フランス名シャルルマーニュ)で、現在のフランス、ドイツ、イタリアに相当する地域を支配し、スペイン(イベリア半島)やイギリス(ブリテン諸国)を除く西ヨーロッパ全域に勢力を及ぼし、800年にローマ教皇レオ3世により戴冠してローマ皇帝(カール大帝)となった。
814年にカールが没すると、カロリング家の長子ルートヴィヒ(敬虔王)が皇帝戴冠を受けたが、ゲルマン民族は長子相続ではなく男子均一相続のため、彼の死後、領地は3人の息子により分割されることになった。
長子ロタール一世は皇帝の称号とイタリア、および中部フランクを相続した。中部フランクはロートリンゲン(ロタールの国)とも呼ばれ、フランスとドイツの国境地域(ロレーヌ地方)にあたる。それに対して三子ルートヴィヒ(ドイツ人王)は東フランク王としてライン以東を、四子カール(シャルル禿頭王)は西フランク王としてライン以西を領有した。こうして、ライン川とアルプス山脈という自然の要害によってカール大帝の帝国は三分割され、ドイツ、フランス、イタリアの原型が生まれた。
その後のヨーロッパの歴史は、この3つの主要地域をめぐる諸侯の争いに教皇が加わって複雑怪奇な様相を呈する。中部フランクと西フランクのカロリング家が断絶したことで、ローマ皇帝の称号は東フランクに受け継がれるが、899年に東カロリング家も断絶した。
962年、東フランク国を継いだザクセン家のオットーが内紛に乗じてイタリア王の地位を奪い、ローマ教皇ヨハネス12世から戴冠を受けてオットー大帝として即位する。だがこの時点では、「ローマ帝国」の名は公文書には出てこない。オットーはドイツ王とイタリア王を兼ねる皇帝だったが、ヨーロッパ(ローマ)の統一にはフランス王の地位が欠けていたのだ。
1024年にザクセン朝が断絶し、フランケン公コンラート2世がドイツ王に選出されると、1034年に「ローマ帝国」という帝国名がはじめて公文書に登場する。中部フランク王国の遺領であるブルゴーニュ(ブルグント)の王家断絶の機に乗じて、コンラート2世がブルゴーニュ王になるからで、ドイツ王国、イタリア王国、ブルゴーニュ王国を支配したことで、カール大帝の帝国よりだいぶ小ぶりだが、ようやく「ローマ帝国」を名乗れるようになったのだ。
その直後から、ローマ(ドイツ)王は聖職者の叙任権をめぐって教皇とはげしく争うようになる。1077年、ローマ王ハインリヒ4世が教皇グレゴリウス7世から破門され、教皇が宿泊するトスカーナのカノッサ城の門前で許しを乞うたのが有名な「カノッサの屈辱」だ。
だがその後も皇帝党対教皇党の対立は続き、1155年に皇帝に即位したフリードリッヒ1世(別名は赤髭王=バルバロッサ)は、「教皇には世俗権力に介入する権利はない」として両剣論を唱えた。両剣とは教剣と政剣を表わす二振りの剣で、『新約聖書・ルカ伝』の「二振りの剣でよい」というイエスの言葉から、「皇帝は神に直接、世俗の統治を委託されており、帝国は神に直接、聖別されている」とした。バルバロッサは自らの帝国を「神聖帝国」と命名し、これによって世俗を支配する皇帝の権力は、来世を支配する教皇と対等になった。
ちなみにバルバロッサは、第3回十字軍の遠征の途上、(現在のトルコ南部にある)タウロス山脈のふもとのサフレ川で水浴中に溺れ死んでしまう。だがバルバロッサの不死の身体はサフレ川の川底を通り抜け、ドイツ南部チューリンゲンのキフホイザーの山中に地下帝国を築き、祖国ドイツが必要とするまで深い眠りに落ちるとされた。これが「バルバロッサ皇帝伝説」で、ナチス・ドイツが不可侵条約を破ってソ連を急襲したバルバロッサ作戦はこれに由来している。