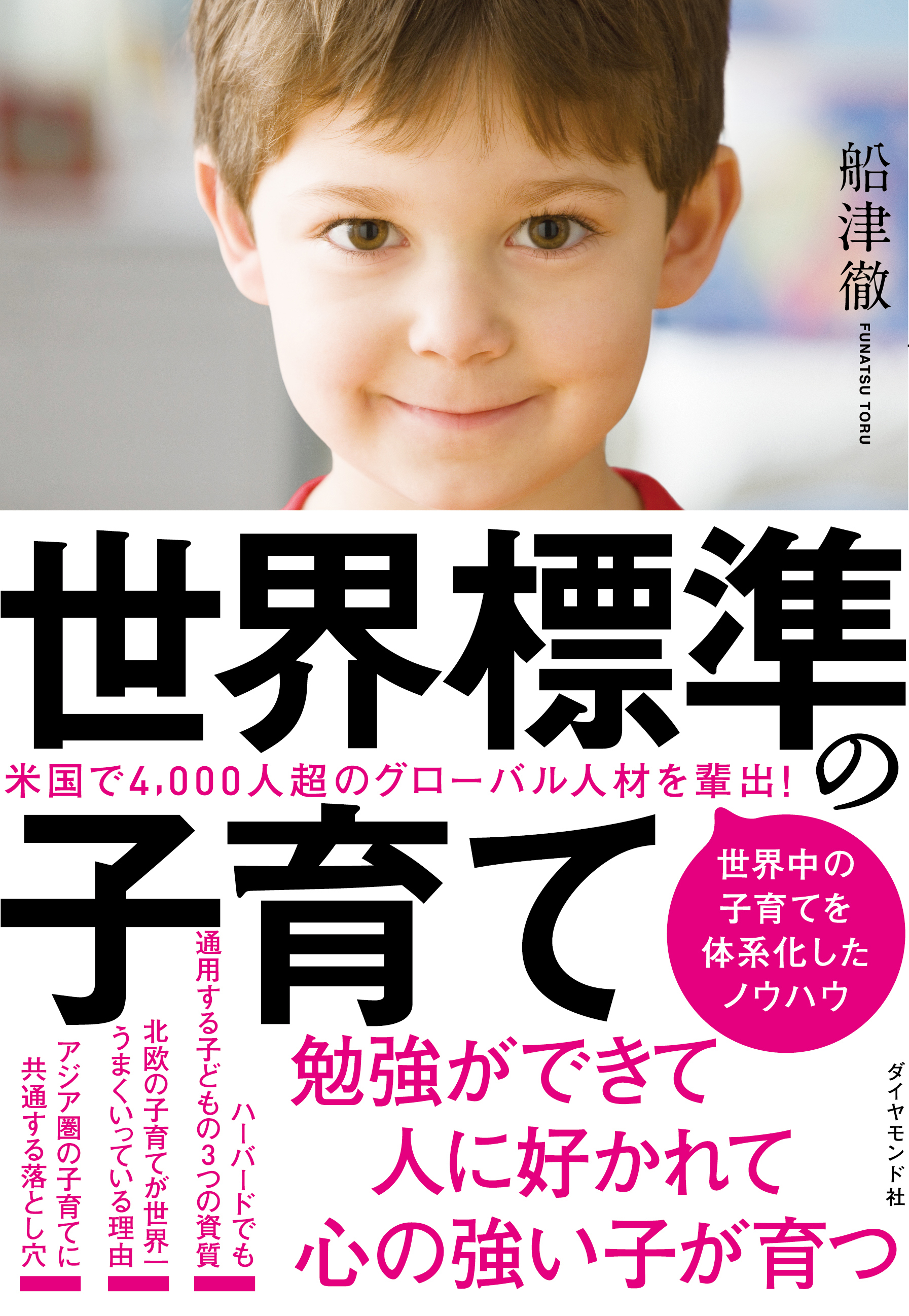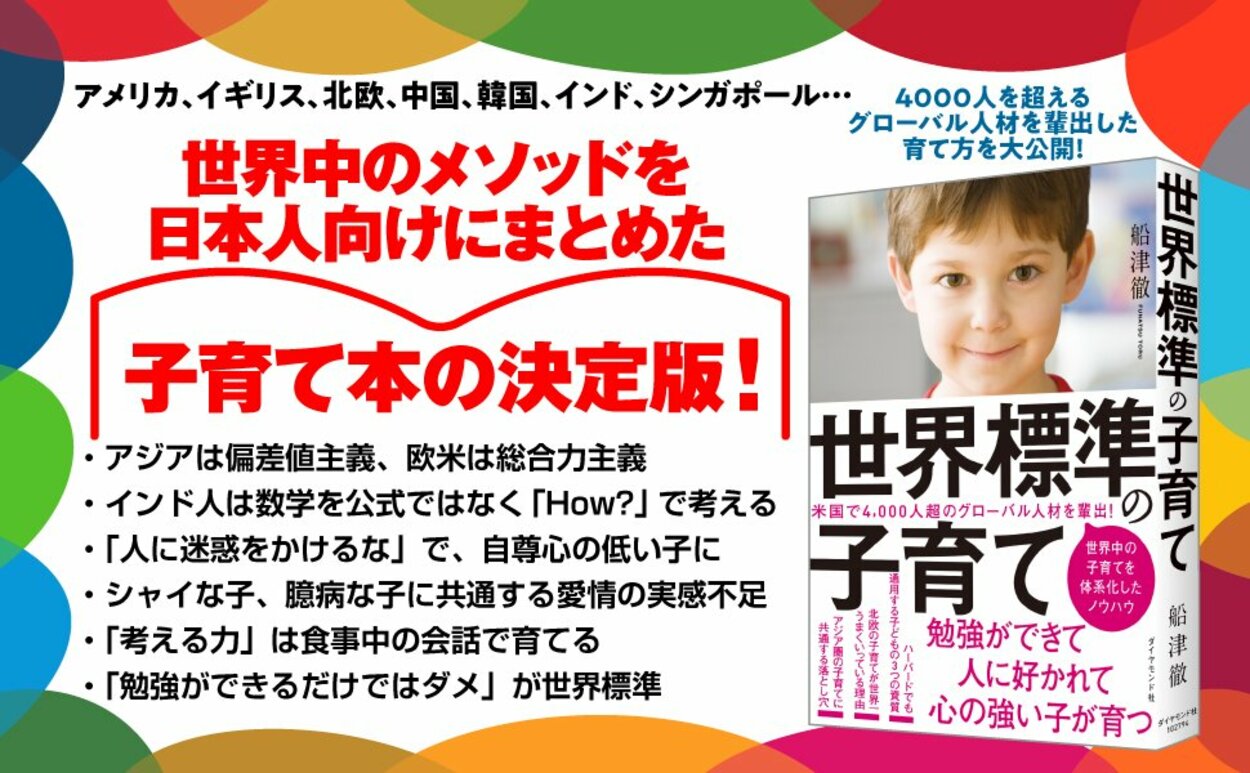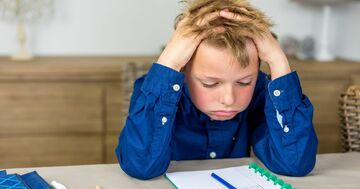子どもたちが生きる数十年後は、いったいどんな未来になっているのでしょうか。それを予想するのは難しいですが「劇的な変化が次々と起きる社会」であることは間違いないでしょう。そんな未来を生き抜くには、どんな力が必要なのでしょうか? そこでお薦めなのが、『世界標準の子育て』です。本書は4000人を超えるグローバル人材を輩出してきた船津徹氏が、世界中の子育ての事例や理論をもとに「未来の子育てのスタンダード」を解説しています。本連載では本書の内容から、これからの時代の子育てに必要な知識をお伝えしていきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
文字を教え始める時は、環境づくりに配慮する
文字を教えはじめる最適期は、子どもが「絵本に興味を持った時」です。一般的には3~4歳の頃です。
この時期の子どもに文字を教える時は「遊び」でなければいけません。くれぐれも「勉強」や「教育」にならないように注意してください。
文字を教える時は「家庭内の文字環境づくり」が重要です。
0歳~6歳の子どもは身のまわりの情報を何でも身につけられる優れた力(環境適応力)を持っています。
ですから、ひらがなチャート・カタカナチャートを子どもの目の高さに貼ります。また、文字ブロック、文字カード、文字マグネットなど、文字に関連したおもちゃを与えてみましょう。
子どもの持ち物には名前を書いてあげます。さらに、家中の物の名前をカードに書いて貼ります。
冷蔵庫には「れいぞうこ」、壁には「かべ」、床には「ゆか」、椅子には「いす」といった要領です。これで文字環境をつくることができます。
ゲーム感覚で遊びながらが基本
ひらがなチャートの文字「あいうえお」を指でさしながら一文字ずつ読んで聞かせます。
「これは“あ”だよ」とは教えず、一つひとつの文字を指し「あ」「い」「う」とはっきりと発音して聞かせましょう。
また、カードを並べて子どもの名前をつくって読む練習をします。家族全員の名前が読めるように教えてあげてください。
カード取りゲームで遊ぶのもいいでしょう。ひらがなカードを並べて、母親が「あ」や「い」と言って子どもにカードを取らせます。
コミュニケーションをとりながら遊び感覚で文字に親しませることが大切です。
ひらがな五十音を覚えたら、「いぬ」「ねこ」「さる」などの二文字言葉の読み方を教えます。文字カードや文字ブロックを使って練習しましょう。
子どもに文字を教える時は絶対に強制してはいけません。カード取りや言葉遊びを通して親子で楽しみながら教えてください。
文字を覚えるのは「ママ(パパ)と遊ぶ楽しい時間」と子どもが感じている状態が理想です。
五十音を覚えたら短い絵本を読ませてみる
五十音を一通り覚えると、子どもは簡単な本が読めるようになります。そうなったら、ひらがなだけの短い絵本(1ページに1~2行くらいの文字量)を与えて音読練習をさせます。
もちろん最初は上手に読めませんし、1ページを読むのに多くの時間がかかります。でも、必ず親は子どもが読み終わるまで横で聞いてあげてください。
そして読めたら「上手に読めてすごいね。またママ(パパ)にお話を聞かせてもらえると嬉しいな」と伝えてください。子どもは目を輝かせ誇らしげな顔を見せてくれます。
子どもが一人でスラスラとストレスなく本を読めるように導くことができれば、必ず本好きな子に育ちます。焦らず、時間をかけて、子どもを励まし続けてください。
子どもが自分で最初に読む本は、0~3歳の頃に母親が読み聞かせていた本、赤ちゃんの時に好きだった本です。
ストーリーやイラストが記憶に残っていますから親しみが湧きます。また文字数が少ないので初めて読む本として最適です。
くれぐれも難しすぎる本は与えないでください。子どもを本嫌いにしてしまいます。
なお、子どもが一人で本を読めるようになっても「読み聞かせ」は継続してください。この段階では、読めても内容が十分に理解できないのです。
しかし、同じ本を母親(父親)が読んであげるとストーリーの世界に入り込むことができ、理解が深まります。読み聞かせは小学2~3年生まで継続することが目安です。