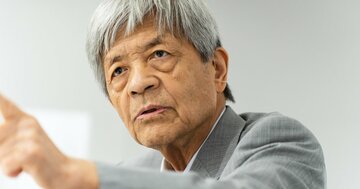日本は権威と権力を
分けたほうがうまくいく
源頼朝は、初めて武力で天下を取って武家政権を確立した。彼は『日本書紀』や『古事記』は読んでいないと思うが、それでも天皇を重視し、自分の上に天皇を置いた。
1980年代までは日本の歴史学者は反天皇制の立場を取る者が多かったが、1990年代からは天皇制を支持し、研究する学者が増えてきた。以前、天皇に関する本(『日本人と天皇 昭和天皇までの二千年を追う』中央公論新社、2014)を書いたのだが、その時、歴史や天皇制に詳しい学者たちに、なぜ、頼朝は武力で天下を取ったにもかかわらず、天皇を排除しなかったのかを聞いたことがあった。すると、どうも、頼朝は、「権威」と「権力」を分けたほうが統治が安定すると考えていたようだと言う。
執権となった北条家も、朝廷と争い、後鳥羽上皇を島流ししたが、天皇制は維持した。室町幕府を開いた足利尊氏も、後醍醐天皇と争い勝利したが、後醍醐天皇が奈良の吉野に逃れても殺さず、それぞれ南朝と北朝という形で天皇制が維持された。
薩長もそのようにしている。これが日本のおもしろいところだね。日本というのは、権威と権力を分けることで政治が安定する。これが日本の政治の根底にある。欧米など外国ではこうしたケースはめったにない。
第二次世界大戦での敗戦後に日本に来た、連合国軍最高司令官のマッカーサーもそうだ。昭和天皇の、戦争のすべての責任は私にある、といった言葉にマッカーサーが感銘を受けたという話や、天皇制をつぶすと日本が共産主義に傾くのではないかという懸念もあったともいうが、結果的に、マッカーサーは天皇に戦争責任を問わなかった。やはり、日本は権威と権力を分けたほうがうまくいくという考えもあったのだろう。
――3人目は誰でしょうか?
勝海舟だ。新政府軍が江戸に迫る中、西郷隆盛としっかりと話し合い、江戸が戦場になることを回避した。交渉力に長けた勝が幕府側にいなければ、江戸中が砲火に包まれていたといわれている。
先見の明があり、批判を恐れず信念を貫き通す。それらを活かす「行動力」と「交渉力」もある。勝がいかにこれらの能力に優れていたか。明治以降、新政府側にいた者と旧幕府側だった者、どちらからの評価も高いことが、そのことを証明している。