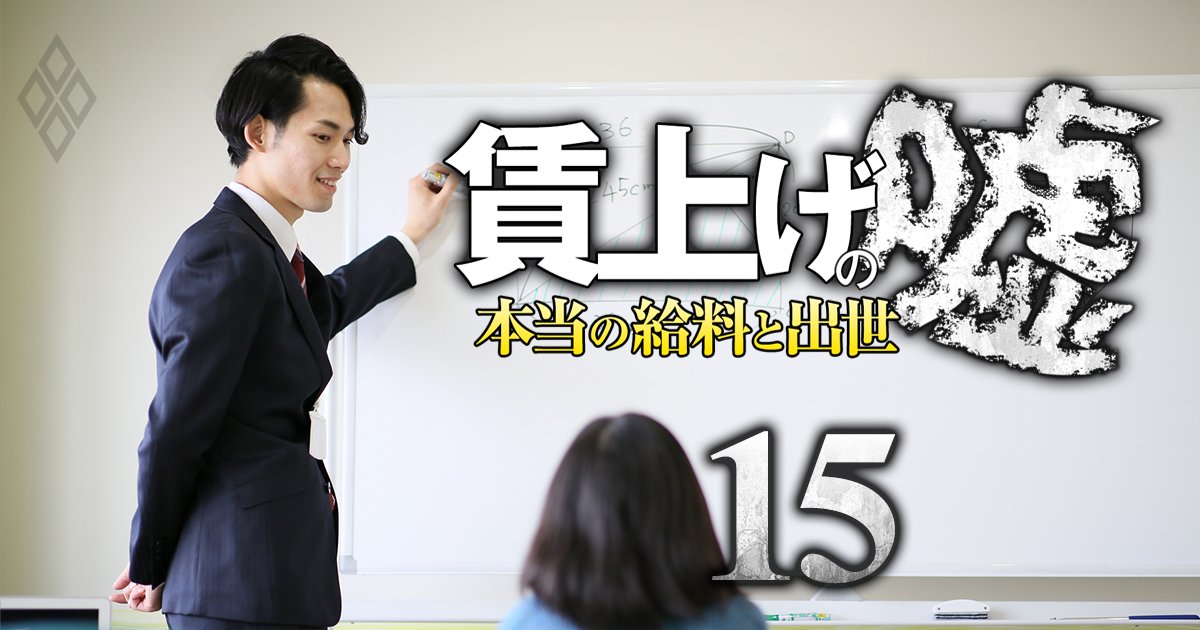今シーズンの京都には、川﨑に加えて22歳のGK若原智哉、24歳のDF麻田将吾とSAP出身選手が在籍。SAPの対象ではないものの、京都サンガU-18出身者も4人を数えている。稲盛氏が即断即決で整えた環境が、今ではチームの財産となっている。
選手のセカンドキャリアにも好影響
他のJクラブと一線を画すシステム
選手だけではない。京都の営業部で奔走している31歳の武田有祐さんはSAPの対象者であり、トップチーム昇格が見送られた中で立命館大学へ進学。卒業後はJ2のカマタマーレ讃岐で6シーズン、計110試合に出場したキャリアを持っている。
2019シーズン限りで現役を引退。セカンドキャリアとして古巣を選んだ2020年1月に抱いた心境を、自身のツイッター(@YusukeTakeda)でこうつぶやいている。ツイートの中で出てくる「紫の血」とは、黎明(れいめい)期から変わらないチームカラーのパープルを指している。
「やはり紫の血が流れていたみたいで…大切な時期の大半を育てていただいたクラブに少しずつでも恩返しをしていければと思います!ただいま」(原文ママ)
全寮制だからこそ、滋賀県出身の若原、長野県出身の麻田、そして山梨県出身の川﨑と府外から優秀な高校生たちが集まってくる。さらに立命館宇治高とのタッグが、文武両道に挑戦できる点で京都の下部組織の価値を際立たせる。サッカー以外でも日常生活を共有できるため、最も身近なライバルである同期生たちと、例えば勉強面でも切磋琢磨(せっさたくま)する状況が必然的に生まれる。
立命館大へ内部進学できる道も開けるため、川﨑のような大学生Jリーガーも可能になる。Jクラブは下部組織の保有を義務づけられているが、全寮制を取るクラブは限られる。さらに寮費も学費も免除される、他のJクラブと大きく一線を画すシステムを資金力と行動力、そして人脈で作り上げた点で、稲盛氏が残したSAPはユース選手の人生を豊かにする究極のお手本といえるだろう。
話を今シーズンの天皇杯に戻せば、ヴェルディとの準々決勝で快勝した京都は11年ぶり3度目のベスト4進出を決めた。ほぼ10年周期で訪れるタイトル獲得への挑戦権を求めて、10月5日の準決勝でホームのサンガスタジアム by KYOCERAにサンフレッチェ広島を迎える。
「サンガのみならず、日本の経済界においても非常に大切なキーパーソンを亡くしてしまったことについて、本当に悲しい思いでいっぱいですが、その魂は引き継がれていると思っています。稲盛名誉会長が常日頃言っておられたリーダーの精神や『正しいことをやりなさい』という教えは、サッカーにおいても非常に大事だと考えていますので、これからも良い報告ができるようやっていきたい」
ヴェルディ戦後に神妙な口調で勝利を振り返った曹監督は、指導の一部がパワーハラスメント行為と認定され、湘南ベルマーレ監督を2019年10月に辞した経験を持つ。日本サッカー協会から科された1年間の指導者ライセンスの停止処分が明け、生まれ故郷のクラブである京都で再出発を切ろうと決意した20年12月に、かつて稲盛氏が残した名言を羅針盤にすえた。
「チャレンジして失敗することが失敗ではなく、チャレンジしないことが失敗だ」
J1昇格を果たした昨シーズンも、J1残留争いに直面する今シーズンも、その中でベスト4進出を果たした天皇杯も、そして全国から金の卵が集まるSAPも、すべてはチャレンジの過程にある。あきらめる時こそが失敗と言い聞かせながら、京都は目の前に迫る荒波に立ち向かっていく。