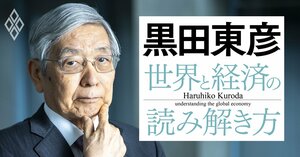「計画の立てすぎは幻想に浸ることと同じだ」 Photo by Nina Subin
「計画の立てすぎは幻想に浸ることと同じだ」 Photo by Nina Subin
2022年2月刊行の『The Power of Regret: How Looking Backward Moves Us Forward』(『後悔の力――過去を振り返ることが、いかに私たちを前進させるか』(仮題、邦訳版刊行予定)を著した米ベストセラー作家ダニエル・ピンク氏によれば、後悔は私たちを前進させ、人生をより良くするための源泉だ。後悔を感じることは「人間の証」であり、10年後の自分を想定し、何を後悔したくないかを自分自身に問いかけることが幸せになる秘訣だという。「わが人生に悔いなし」と言い切る人は自分を偽っているかソシオパス(社会的病質者)だと、同氏は指摘する。独自のオンライン調査で世界105カ国から1万6000人超の「後悔」を集めて分析したピンク氏に話を聞いた。(聞き手/ニューヨーク在住ジャーナリスト 肥田美佐子)
人生にとって何が重要な
決断になるのかを見極めるコツ
――前編で、「後悔」には4種類あるというお話を伺いました。まず、人生の基盤を築かなかったという後悔「ファンデーション・リグレット」。次が、大胆に行動しなかったという後悔「ボールドネス・リグレット」。そして、道徳や良心に関する後悔「モラル・リグレット」。4つ目が、人とのつながりや人間関係にまつわる後悔「コネクション・リグレット」です。
後悔の種類によって、その克服の仕方に違いはありますか?
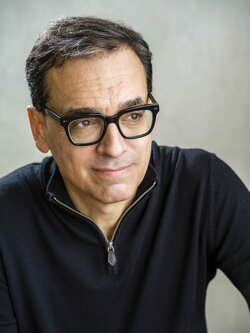 Daniel Pink(ダニエル・ピンク)
Daniel Pink(ダニエル・ピンク)1964年生まれ。作家。エール大学ロースクールで法学博士号取得。世界各国の組織を対象に経済や経営戦略についての講義を行うかたわら、「ワシントン・ポスト」「ニューヨーク・タイムズ」「ハーバード・ビジネス・レビュー」などに寄稿。『ハイ・コンセプト』『モチベーション3.0』などの著書はベストセラーとなっている。クリントン政権下ではゴア副大統領の首席スピーチライターを務めた。Photo by Nina Subin
ダニエル・ピンク(以下、ピンク) どの種類も克服法の基本構造は同じだが、1つ違いがある。
「action(行動)」に対する後悔か、「inaction(非行動)」に対する後悔かで、後悔の度合いが違う。やったことを悔やむ気持ちは、新たに何かをすることで一部を取り消すことができるが、やらなかったことに対する後悔は、どうすることもできないからだ。
例えば、誰かをいじめたことを後悔した場合には、謝罪という道がある。過去にいじめた人々を訪ね、片端から謝ることが可能だ。「タトゥー(入れ墨)など入れなければよかった」と後悔する人には、除去という選択肢がある。
行動したことは、行動しなかったことよりも、後悔の度合いが少し小さい。例えば、女性に多いと言われるが、夫との結婚を後悔しつつ、「でも、2人の素晴らしい子供に恵まれたから、まあいいか」と自分に言い聞かせることで、後悔が少し和らぐ。
だが、やらなかったことを悔やむ気持ちは、なすすべがない分、やったことを悔やむ気持ちよりつらい。特に年を重ねるにつれて、人は「行動したこと」よりも、「行動しなかったこと」に対する後悔の念にさいなまれるようになる。
――ポジティブに後悔の念と対峙(たいじ)し、今後の人生に生かしていくに当たって、最も注意すべきことは何でしょう?
ピンク 重要なのは「正しい後悔」をすることだ。
例えば、「ランチに、ピザでなくハンバーガーを食べてしまった!」とか、「黄色でなく、ブルーのシャツを着てしまった!」といった後悔は意味がない。人生をより良くするには、「何を後悔すべきか」がカギだ。
私たちは、人生で大きな意味を持つ決断が何かを知っている。それ以外の決断は、さほど重要ではない。だから、まずは、人生の基盤を築かなかったという「ファンデーション・リグレット」を回避すべく、毎日を過ごすべきだ。「自分自身や家族、チームのために『しっかりした基盤』を築く」ことを心がけよう。
大胆に行動しなかったことを悔やむ「ボールドネス・リグレット」も重要だ。人生を振り返り、「あまり充実した人生じゃなかった」「いろいろなことに挑戦するだけの勇気がなかった」などと後悔したくはないだろう?
道徳や良心に背く行動を取ったことを悔やむ「モラル・リグレット」も要注意だ。私たちは、常に正しい行いをするよう心がけるべきだ。人とのつながりや人間関係にまつわる後悔「コネクション・リグレット」も忘れてはならない。大切に思う人たちには、まめに連絡を取ろう。
だが、こうした後悔以外の後悔は、そのうち忘れてしまう。人生にとって何が重要な決断になるのかを見極めるコツは、10年後の自分に問いかけることだ。2032年の自分を想定し、今、どのような決断をすれば10年後に後悔しないで済むか、を考えるのだ。赤い車でなくブルーの車を買ったとしても、今晩何を食べたとしても、10年後の自分には関係ない。
だが、安定した人生の基盤を築き損ねたとしたら、そうはいかない。また、合理的なリスクすら取らない人生を送ったり、正しい行いをしなかったり、大切な人との関係をおろそかにしたりした場合も同じだ。10年後の自分に、どのような後悔をしたくないかを問いかけることで、自分の人生で大切なものとそうでないものが見えてくる。
本当に大切なものにフォーカスすることが、人生の幸福度を高める。