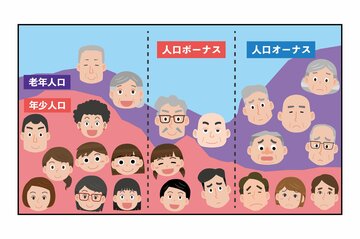「今年はどんな年になるだろうか?」という予想を、当たるも八卦、当たらぬも八卦で毎年書いている。
去年の予想では、世界は「リベラル化、グローバル化、知識社会化」の大きな潮流のなかにあり、日本でも世界でもそこから脱落しつつあるひとたちが増えているとして、「今年も経済格差/評判格差は拡大し、知識社会に適応できないひとたちの不満がつのり、『下級国民』によるテロリズムが散発的に起きるだろう」と書いた。周知のように7月8日、カルト宗教に家庭を破壊されたという理由で、41歳の孤独な男が安倍元首相を銃撃する事件が起きた。
もうひとつ、予想が当たったのは「イーロン・マスクのような超富裕層の“奇矯な”行動が社会に大きな影響を与える」としたことだ。一生のうちに物理的に使いきれる上限をはるかに超えた富(金融機関のサーバーに格納されたたんなるデータ)をもつ者たちは、生物学的な欲望を満たすことに興味がなくなり、社会的な評判を獲得することで「自己肯定感」を高めようとする。Twitterを買収したマスクの行動は、これで説明できるのではないか。
ウクライナ侵攻はこのままの状態で膠着状態に陥り、それが何年(あるいは十数年)も続く可能性が高い
昨年2月のロシアによるウクライナ侵攻は、私にとっては「ブラックスワン(ロングテールの端で起きるとてつもない出来事)」で、まったく予想できなかった。バイデンはロシアの侵攻を繰り返し警告しており、結果としてはこれが正しかったわけだが、読み間違えたのは私だけではない。
 Photo :metamorworks / PIXTA(ピクスタ)
Photo :metamorworks / PIXTA(ピクスタ)
侵攻が始まる1カ月前、ドイツ海軍トップのシェーンバッハ総監(海軍中将)が、インドで開かれたシンクタンクの会合で、「ロシアがウクライナに侵攻しようとしているとの欧米諸国の考えは『ナンセンス』だ」「(2014年にロシアが強制編入したクリミア半島は)なくなってしまった。(ウクライナ側に)戻ることはないだろう」と述べたとして引責辞任した。
トランプ支持者による連邦議会占拠事件(21年1月6日)の2日後、米軍トップの統合参謀本部議長が、中国人民解放軍のトップに電話で、中国を攻撃する意図はないと説明していた事実が暴露されが、たとえ敵対関係にあっても、軍のトップ同士はコミュニケーションを取り合っている。ドイツ海軍総監の発言も、たんに個人的な憶測を述べたのではなく、ロシア軍上層部からの情報に基づいていたのではないか。
無謀な侵攻はプーチンと一部の側近の独断で行なわれ、ロシア軍の現場指揮官たちも、まさかほんとうに戦争を始めるとは思っていなかったと考えれば、当初のロシア軍の混乱や醜態が理解できる。軍事専門家でも(あるいは専門家だからこそ)、独裁者の不合理な妄想を予測できなかったのだろう。
4400万の人口と広大な国土を要する国を短期間に侵攻・制圧し、傀儡政権を樹立することが不可能なのは、軍事の常識だった。その後の展開は専門家の予想どおりになり、ロシアは莫大な戦費と多数の兵士を犠牲にし、欧米の経済制裁を受け、実質支配していたクリミア半島とウクライナ東部に押し込まれて、なにひとつ得るものがないという結果になった。
追い込まれたロシアが核兵器を使い、NATOが武力で反撃する「第三次世界大戦(世界最終戦争)」のリスクは残っているものの、このままの状態で膠着状態に陥り、それが何年(あるいは十数年)も続く可能性が高いのではないか。アメリカも、ロシアに勝たせるわけにはいかないが、同時に、ウクライナがクリミアを奪還しようとして核戦争の引き金になる事態は避けようとするだろう。ウクライナも欧米の軍事・財政支援がなければ国を維持できないのだから、アメリカの意向を無視して戦線を広げることはできないはずだ。
問題は、この紛争をどのように決着させるかのシナリオを誰も描けないことだ。プーチンが失脚したり、死亡したりすることはあるかもしれないが、自分たちを「被害者」だと考えるロシア国民が、ウクライナに謝罪し莫大な賠償金を支払うことを容認するとは思えず、より過激な国家主義者が「民主的に」選ばれることになるのではなかろうか。
若者たちはじょじょに「現実(リアル)」から撤退し、ヴァーチャル世界(仮想空間)に移っていく
アメリカはグローバル世界の実験場で、「リベラル化、グローバル化、知識社会化」の潮流がどのような事態を引き起こすのかを教えてくれる。日本でも同様のことが5年、あるいは10年遅れて起きると考えれば、わたしたちの未来を予想する「水晶玉」でもある。
昨年11月の中間選挙で民主党(バイデン政権)が予想外に健闘したことで、トランプの影響力に陰りが生じ、24年の大統領選候補としてフロリダ州知事のロン・デサンティスが注目されている。民主党は副大統領のカマラ・ハリスに人気がなく、80歳を超えたバイデンに頼らざるを得ないようだ。いずれにしても、民主党/共和党という政治イデオロギーで「党派」がつくられ、社会が分断される構造は変わらないだろう。
「学歴・資格・実績」のみで労働者を評価するメリトクラシーが徹底されたアメリカでは、黒人やラテン系などが労働市場から最初に脱落し、次いでこうした「有色人種」を「福祉の女王」などと罵倒していた白人労働者階級(ホワイト・ワーキングクラス)が脱落して、トランプの岩盤支持層を形成するようになった。
そして現在、彼らを「レイシスト(人種主義者)」「ホワイトトラッシュ(白人のゴミ)」などとバカにしていた高学歴層のなかで、中位以下が高度化する知識社会から脱落しつつある。多額の奨学金の返済義務を抱えながら望むような仕事につけない彼ら/彼女たちは「不満だらけのエリート・ワナビーズ(エリートなりたがり)」と呼ばれ、民主党の大統領予備選では「社会主義者」のバーニー・サンダースを熱狂的に支持し、BLM(ブラック・ライヴズ・マター)の運動では警察の解体や刑務所廃止を求めている。
アメリカ社会は、Qアノンのような陰謀論を信じる右派と、資本主義を否定する「ラディカルレフト(過激左派)」「プログレッシブ(進歩派)」に引き裂かれつつある。両者はあらゆるところではげしく対立するが、共通するのは、第二次世界大戦後のアメリカを牽引してきた「リベラル」をはげしく批判・攻撃することだ。――こうした「反リベラル」は、ロシアのプーチン政権や中国の習近平政権にも共通するだろう。
アメリカの若者(2000年代になってから成人したミレニアル世代)はいったい何を考えているのか。興味深いデータを紹介しておこう。
ある調査では、民主国家に住むことが不可欠だと考えている(アメリカの)ミレニアル世代は32%にとどまった。4人に1人が民主主義は国家運営の手法として「悪い」か「非常に悪い」と考え、政府がその仕事を果たせない場合、軍部が政権を握るのは妥当であると考える人は70%を超えた。しかも、これらの数値は年々悪化してきた。政治に関心があるアメリカの若者は1990年には53%いたが、2005年には41%まで低下した。「軍による国の支配」がよいことだと考えるアメリカ人は1995年には16人に1人しかいなかったが、2005年には6人に1人まで増えた。さらに「議会や選挙に煩わされない強いリーダー」を支持するアメリカ人は1995年の25%から、2011年には36%まで増えた。2011年までに3分の1に達したということだ。(Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk(2016) The Democratic Disconnect, Journal of Democracy/ブライアン・ヘア、ヴァネッサ・ウッズ『ヒトは〈家畜化〉して進化した 私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか』藤原多伽夫訳、白揚社より引用)
社会のさまざまな制度が機能不全を起こしていることで、若者たちはじょじょに「現実(リアル)」から撤退しつつあるのではないか。学校や会社、あるいは核家族など、近代社会を支えてきた共同体が解体し、ひとびとは生活の重心を「より自分らしく生きられる」ヴァーチャル世界(仮想空間)に移していくと予想しておこう。