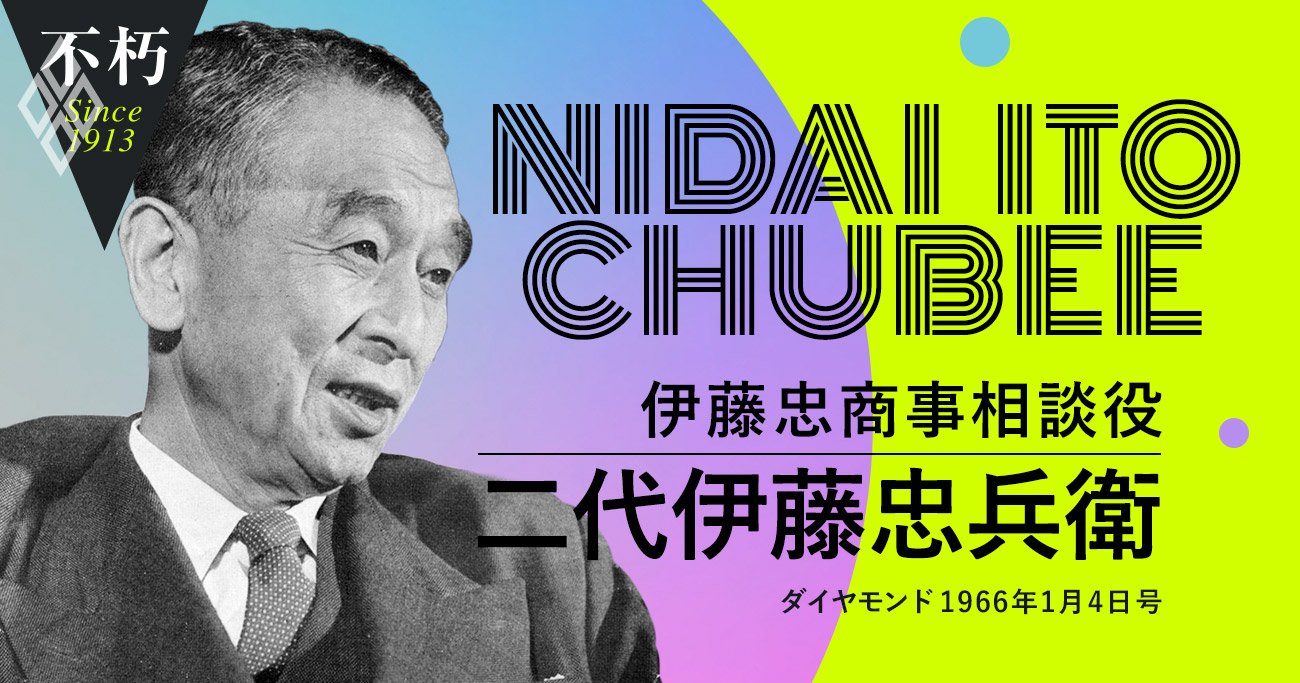
1903年に初代忠兵衛が没すると次男の精一が家督を相続し、二代伊藤忠兵衛(1886年6月12日~1973年5月29日)を襲名した。そして、初代が切り開いた事業を近代的に変革し、取り扱う商品の幅を広げ、現代の総合商社の形を作り上げた。
今回は「ダイヤモンド」1966年1月4日号に掲載された伊藤のインタビュー記事である。「私の“商社必滅論”」と題され、伊藤が商社経営の在り方について語っている。当時、総合商社は毎年のように勢力図が塗り替わる激動の様相を呈していた。
戦後、GHQ(連合国軍総司令部)による財閥解体政策によって、三井物産、三菱商事は解散および商号の使用禁止が命じられ、両社はそれぞれ百数十社に分散したため、50年の取扱高ランキングは(1)伊藤忠商事、(2)丸紅、(3)東洋綿花(現豊田通商)、(4)日綿實業(現双日)、(5)兼松と関西勢が上位を占めた。その後、51年に財閥解体に関する諸法令が廃止されると、三菱商事と三井物産の再統合が進み、55年のランキングは(1)三菱商事、(2)第一物産(三井物産)、(3)伊藤忠商事、(4)丸紅飯田、(5)日綿實業と変化する。さらに、記事が掲載された当時(65年)の取扱高順は、(1)三井物産、(2)三菱商事、(3)丸紅飯田、(4)伊藤忠商事、(5)東洋綿花、(6)日綿實業、(7)住友商事、(8)日商(現双日)、(9)安宅産業、(10)兼松となっていた。
これも固定的なものではなく、繊維鉄鋼商社の高島屋飯田と合併して丸紅飯田となっていた丸紅が66年には鉄鋼専門商社の東通を吸収合併することがすでに発表されていた。また、68年には日商と岩井産業の合併によって日商岩井が誕生し、9位だった安宅産業は77年に伊藤忠商事に吸収合併される運命をたどる。
生き残りを懸けた激しい競争が常に巻き起こっている業界であることから、伊藤は「売買業は永続性がない」として、「商社必滅」と表現する。そして生き残るためには規模を拡大するしかないと話す。また、面白いのは、日本銀行総裁や大蔵大臣などを歴任した井上準之助から授かったという「人格者を信用するな」という教えだ。忠義な人や人格者は、おおむね保守的な考えをするものなので、うのみにしない方がいいというのだ。「今日のように進歩の早い世界では、保守は一刻も許されない。前進あるのみである」という言葉は、今でも十分通用する金言である。(敬称略)(週刊ダイヤモンド/ダイヤモンド・オンライン元編集長 深澤 献)
専門商社は全滅?
売買業は永続性がない
 1966年1月4日号より
1966年1月4日号より
今から30年ほど前、日支事変(日中戦争)前後に、私は“商社必滅論”を話した記憶がある。“商社必滅論”とは、商社無用というような暴論ではない。また“生者必滅”という宗教的な無常感から言うのでもない。
世界的な傾向から見て、そういうものではないかという、結果論から言うのである。
かつて綿糸布は日本の基本工業品であったが、これを扱う綿糸商が、東京では全滅している。
大阪の八木商店は、1902(明治35)年の創立である。当時、私の本家は、すでに商売していたが、翌03年に、伊藤糸店として、表面に出た。これが今日の伊藤忠商事の母体である。現在、残っている古い店は、この2軒しかない。
綿糸業は今日、“午後3時の商売”といわれているが、当今、最大の取扱金額である鉄鋼を扱う鉄問屋も、一昨年、岸本商店が大倉商事に合併され、歴史ある店(問屋)は全滅した。
その中で、名古屋の岡谷惣助氏の店(現岡谷鋼機)が1軒残っていた。先年、惣助氏は亡くなったが、鉄問屋としては、岡谷だけだ、と私は言っていた。ところが、それは違う、と人を通じて私の耳に入れてくれた。
惣助いわく、「岡谷の家は『金物屋』ではない、『金具屋』である。伊勢大神宮の金具類を一手に扱わせてもらっている。その金具類が商売の基本になっている。一般の鉄も扱っているが、それは副業である。鉄だけを扱う金物屋だったらとうの昔につぶれてしまっている」というのである。
小売屋は消費者と直結しているが、一番計算の取りやすい商売は呉服屋であろう。
昔は、織物のことを“耳つきもの”といい、繊維屋を糸物屋といった。日本のどの町に行っても、必ずこの商売はあり、酒屋、呉服屋は一応、その町の旦那衆で通っていたものである。数年前丸紅の開業100年祝いをやったとき、お得意先を招いたが、大阪から西の方、神戸を加えて、100年間呉服屋をしているという家は5軒しかなかった。長崎、博多、山口のほかに2軒。準100年続いているのが1軒。商売はやめたが、家が残っているのが1軒。これを入れても7軒しかない。どこにもある商売であるが、100年続いている家はほとんどないといっていい。
私たちがお世話したもので、3度もつぶれ、そのたびに資金を貸し、人を入れ、時には家宝の掛け物などをお預かりして、再建してからお返ししたこともあったが、一時は良くなっても全てつぶれている。いかに売買業というものが永続性のないものであるかを、よく表していると思う。







