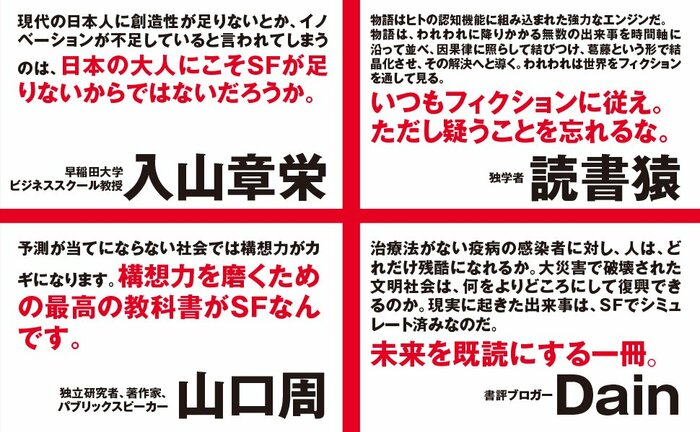『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。
なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。
『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』の著者の冬木糸一です。エンジニアとして働きながら、ブログ「基本読書」などにSFやらノンフィクションについての記事を、15年くらい書き続けています。
僕はSFを「現代を生きるサバイバル本」と位置付けています。理由は、イーロン・マスクを代表とする起業家たちのインスピレーションの源が、SFだからです。彼らは文字通り、今ビジネス、そして世界を動かしています。頭のいい人ほど、フィクションから発想を得ていると考えることもできます。
今回は本書のなかから「管理社会・未来の政治」関連の本を紹介します。
どんな作品か:「捏造された真理」を押し付けられる人々の悲劇
『一九八四年』
─「二足す二は四である」と言えなくなった世界
 ジョージ・オーウェル著/高橋和久訳、早川書房、2009年(原著刊行1949年)
ジョージ・オーウェル著/高橋和久訳、早川書房、2009年(原著刊行1949年)
監視社会を描いたディストピア小説といえば、真っ先に名前が挙がるのが、この『一九八四年』だ。読んだことはなくても、タイトルを耳にしたことがある人は多いだろう。20世紀を代表する傑作であり、時代を超えて読みつがれている物語である。
作者のジョージ・オーウェルは、キャリアの初期はルポルタージュ作家として、スペインの内戦体験を描いた『カタロニア讃歌』(1938)などを発表していた。その後は小説を執筆しながら、英BBCに入社して東南アジア向けの番組をつくったり、「トリビューン」紙の文芸担当編集長になったりと職を転々としている。
そんな最中、1945年に刊行されたのが、小説『動物農場』だ。豚や犬や猫が暮らす農場で、動物たちが人間に対して一斉蜂起し、すべての動物は平等であるという理想を体現した「動物農場」を設立する。ところが次第に、一部の動物が富や権力を独占するようになり……という、現実世界のソ連を彷彿とさせる作品だ。政治権力が腐敗していく普遍的な過程を描き出したこの小説は大ヒットを記録し、『一九八四年』と並んでオーウェルの代表作とされている。その4年後に『一九八四年』が刊行されるが、このときすでにオーウェルは重い結核を患っており、本作が最後の著作となった。
物語の時代設定は、タイトルどおりの1984年。刊行当時の人々からすると、30年ちょっと先の近未来に当たる。世界は旧アメリカ合衆国、旧イギリス、オーストラリア南部などを領有する〈オセアニア〉、欧州大陸からロシアの極東までを領有する〈ユーラシア〉、そして旧中国や旧日本を中心にアジア圏を領有する〈イースタシア〉の3大国に分かれているという状況だ。
物語の舞台であるオセアニアは、〈ビッグ・ブラザー〉なる人物が率いる党に支配された全体主義国家。街中では、テレビと監視カメラを兼ね備えた〈テレスクリーン〉が人々の行動を監視している。さらに、至るところに口ひげをたくわえた45歳くらいの男、すなわちビッグ・ブラザーのポスターが貼られていて、その下には“ビッグ・ブラザーがあなたを見ている”とキャプションがついている。その言葉のとおり、ポスターの男の目線は見る者の動きを追いかけてくるような印象を与える。
主人公であるウィンストン・スミスは、オセアニアの〈真理省〉に勤務する党員だ。真理省といっても、真理を追究する機関などではない。党にとって都合の悪い情報や記録をねじまげ、真理を「捏造」している組織だ。ここでウィンストンは、日夜党のために記録を改ざんして過ごしている。
党は3つのスローガン「戦争は平和なり」「自由は隷従なり」「無知は力なり」を掲げ、〈ニュースピーク〉と呼ばれる新しい言語を公用語としている。ニュースピークでは徐々に使用される単語が減らされており、最終的には使用者の「思考」を制限するのだ。
党員には、毎日2分間、党の敵に対してありったけの憎悪を表現する「二分間憎悪」が習慣づけられている。さらに、オセアニア国民は、嘘を嘘と知りつつ同時に真実であると信じるような「二重思考」の実践を要求される。
やがてウィンストンは真理省での仕事に違和感を覚えるようになり、党に禁じられた行為である「日記」の習慣をひそかに開始する。ある日の日記に、彼は次のように書き残す。
自由とは二足す二が四であると言える自由である。その自由が認められるならば、他の自由はすべて後からついてくる。(p125)
党への反発を強めながら日々を過ごしていたある日、ウィンストンは彼と同じく党の方針に疑問を抱く女性、ジュリアと知り合い、テレスクリーンの監視をかいくぐりながら密会を重ねるようになる。
反政府活動への意欲を高めつつ、二人の仲が深まっていく最中、ウィンストンは党の官僚であるオブライエンの自宅に招待される。オブライエンは、ジュリアと共にオブライエン邸を訪ねたウィンストンに、自分が党に反抗する秘密組織〈ゴールド同盟〉の一員であることを明かし、組織のためにどこまで尽力できるのかとウィンストンたちに問う。
意気揚々とゴールド同盟への忠誠を誓うウィンストンだったが、実はこれは、ウィンストンたちを捕らえるための罠だった。ウィンストンはジュリアもろとも身柄を確保され、党から苛烈な拷問を受ける。出している指の数を答えろと言われ、実際には4本であったとしても、党が5本だというのならば5本だと答えなくてはならない。繰り返し拷問を受けるうちに、ウィンストンは自然とその考えを受け入れるようになっていく。
最終的に、〈101号室〉と呼ばれる最も恐ろしい拷問部屋に連行されたウィンストンは、ついに最後までかばっていたジュリアをも裏切り、これをもって洗脳は完了する。ウィンストンは牢獄から解放され、日常を取り戻す。ある日公園で、同じく拷問を受けてきたであろうジュリアと再会するも、すでにお互いに対する感情はなく、少し会話を交わしたのちにあっけなく別れてしまう。《彼は今、〈ビッグ・ブラザー〉を愛していた。》─この救いのない一文で、物語は終わる。
どこがスゴいのか:為政者が情報統制に走るたび、何度でも立ち戻るべき作品
ここで描かれている「未来像」には、現代の感覚からすると古臭く感じられる部分も多い。社会を監視する役目は、テレスクリーンどころかとっくに見えないカメラへと移行しているし、インターネット上では発言の一つひとつまで捕捉される。市民の行動に対する誘導やコントロールは、SNS上でもっと巧妙な形で行われるようになっている。
それでも『一九八四年』は、何度でも立ち戻るべき作品だ。権力者は、その権力を維持するために、常に文書改ざんや監視体制の強化といった支配的な方向へと向かいたがる。したがって、ファシズムへの志向が消え去ることは決してないだろうとオーウェルは考えていた。実際、この作品で描かれた情景はいまなお各国で繰り返されている。
『一九八四年』が世に出てから70年余り。国家による情報統制が厳しさを増し、監視社会への懸念が高まるたびに、本作は注目を集めてきた。
近年の事例でいえば、2017年のトランプ大統領の就任式に関連して「オルタナティブ・ファクト(もうひとつの事実)」という言葉が物議をかもした。トランプ政権の報道官は、就任式に集まった群衆が「過去最大の人数」だったと自画自賛したが、実際にはそれを裏付ける統計や写真はどこにもない(むしろ空撮写真を見る限り、オバマ大統領の就任式に集まった群衆より明らかに少ない)。この報道を虚偽だと批判するメディアに対して、当時トランプの側近であったケリーアン・コンウェイは「(虚偽ではなく)もうひとつの事実」だと反論したのだ。この発言がまさに『一九八四年』的だということで、本作はまたしても注目を浴び、米アマゾンの書籍売り上げランキングのトップに急浮上している。このときのブームは日本にも波及し、翻訳書は4万部も増刷された。
国家や巨大な組織が、極端な形で市民の統制に走ったとき、人は自分たちがどのように行動し、何を感じるべきなのかというヒントを求めて本作を手に取る。
近年は、時代に合わせてアップデートされた、新しい『一九八四年』と呼ぶべき作品も登場している。アルジェリアの作家ブアレム・サンサルは、『2084 世界の終わり』の中で、宗教が支配するようになった全体主義国家の姿を描き出した。中国の代表的なSF作家の一人である郝景芳は、自身がまさに1984年生まれであることもあって、中国人の目線から『一九八四年』をひもといた長編『1984年に生まれて』を発表している。あと数十年もすれば、22世紀を見据えた『二一八四年』が登場し、オリジナルのDNAを後世へ受け継いでいくことだろう。
ジョージ・オーウェル
1903年、英国領インド生まれ。文学のみならず、20世紀の思想、政治に多大なる影響を与えた小説家。主な著作に『動物農場』などがある。
※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からの抜粋です。