偏差値35から東大合格を果たした現役東大生の西岡壱誠氏によると、頭がいい人の「ノートやメモの取り方」には共通点があり、それを真似することで、誰でも質のいいインプットやアウトプットができるようになるといいます。
本記事では、1000人以上の東大生のノートを分析した結果をまとめた『「思考」が整う東大ノート。』の著者である西岡氏に「伝わる文章を書くコツ」について話を聞きました。
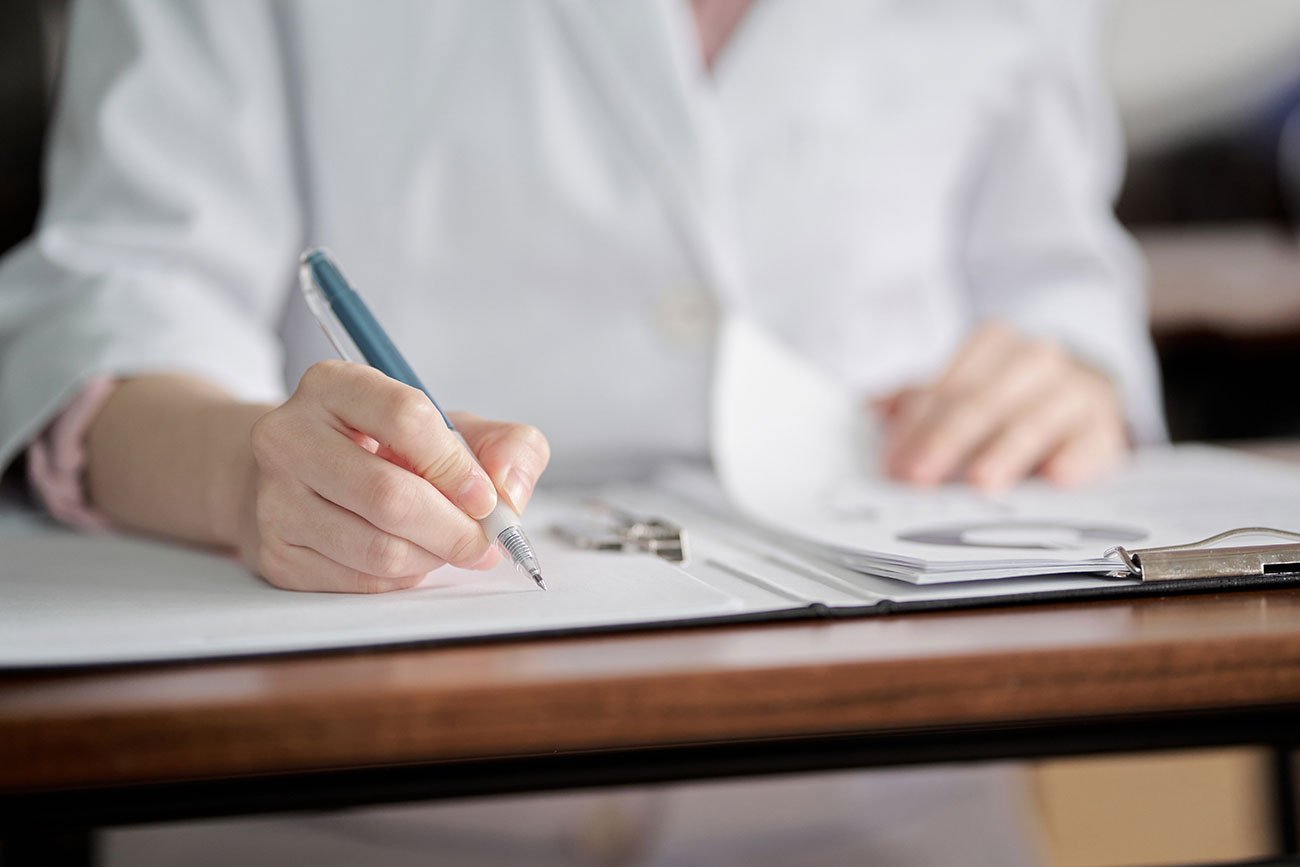 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
東大生のノートはきれい?
みなさんは、「きれいなノート」と聞くとどんなイメージを持ちますか?
インスタグラムをはじめとするSNSで「#勉強垢」で検索すると、色鮮やかできれいなノートが出てきます。いろんな色が使われていて、見た目がとてもきれいなノートに、たくさんの「いいね」が付いているのです。
「東大生のノートも、きれいなものが多いんでしょ?」とよく聞かれるのですが、正直SNSでたくさんの「いいね」がつくようなきれいなノートを作っている東大生というのはあまりいません。
むしろ、思考のスピードが速い分、ノートやメモを書く速度が速く、字はあまりきれいじゃなかったりします。色も、何色も使うということもなく、せいぜい黒ともう一色、多くても3色くらいの色を使っているだけの場合が多いです。
なぜ東大生のノートは簡素なのか?
なぜ、東大生のノートは簡素な場合が多いのか?
それは東大生がノートを取る「目的」が関係していると思います。こうした色鮮やかできれいなノートというのは、「あとから復習するときのために」作っている場合が多いと思います。復習の際に見やすくてテンションが上がるようなノートを作っているわけですね。
東大生は「あとから復習するため」にノートを取らない
しかし、東大生がノートを取る目的は「あとから復習するときのため」というよりも、「ノートを作って、情報を整理すること」自体である場合が多いです。もっと言えば、ノートを取る目的は、「あとから再現できるようにするため」である場合が多いです。
たとえばみなさんは、そのノートを取ってから1時間経ったあとに、白い紙を用意して、「ここにさっきのノートを何も見ないで再現してみてください」と言われたとして、みなさんはノートを再現できますか?
「1時間後ならできる」という人もいるかもしれませんが、それが「1日後」ならどうでしょう?「1週間後」なら?「1ヶ月後」なら?
ノートは、そんな風に「あとからそのノートを再現できるようになること」が目的です。
テストのための勉強であれ、知識を得るための勉強であれ、あとから「何を学んだのか」が再現できないのであれば、勉強の意味はなくなってしまいます。
ノートを取るのは、頭の中を整理して、そのノートを頭の中にインストールし、それを再現できる状態にするためです。東大生の中には、毎日夜寝る前に白い紙に今日勉強したこと・今日作ったノートを再現できるかどうかをチェックする勉強をしている人がいます。
学んだことをしっかりと自分の血肉にできているかをチェックし、頭に知識を定着させるわけです。
でももし、作ったノートがかなり複雑なものであったならば、あとから再現することは難しくなってしまいますよね。
だから、色をたくさん使ったり、複雑なことばかりが書かれているノートはそもそも作らないようにしているというわけです。この、ノートを取る「目的」を明確に持つということはぜひみなさんにも参考にしてもらえればと思います。



