“飲める人”がなりやすい傾向
飲酒量と期間、頻度が関係する
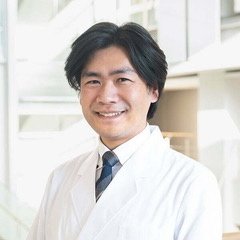 芝崎真裕星薬科大学組織再生学研究室講師
芝崎真裕星薬科大学組織再生学研究室講師
習慣的に飲酒をしていると、アルコールに対する耐性が生まれてお酒がないと物足りなく感じてしまうようになります。その状態で飲酒を続けていくと、お酒を飲まないと不眠や不安を感じてイライラするようになり、さらにお酒を飲んでしまうという悪循環に陥ってしまうのです。
「長期間に相当量の飲酒を行うと、脳内の報酬系(欲求が満たされる際に活性化して快感をもたらす神経系)の神経機能に変化が生じ、脳機能が障害を起こします。そして、本人の意思では飲酒をコントロールすることができなくなります。これがアルコール依存症です」
脳内への作用点が明確には分かっていないのですが、アルコールは脳内モルヒネと呼ばれる活力を上げる作用のある物質の流量を増やすといわれています。その結果、報酬系の神経にある各種タンパク質の機能変化を引き起こし、精神依存を発現させると考えられています。
自分の意思ではコントロールできなくなるのは、このように脳機能が障害を起こしてしまっているから。では、どんな人がアルコール依存症になりやすいのでしょうか。
「アルコール依存症は、“飲める人”がなりやすい傾向があります。アルコールを摂取する量と摂取した期間、頻度が関係するのですが、10年、20年といった長い期間、習慣的に多量のお酒を飲んだ場合に依存症になりやすいようです。また、人によっては若い年齢で、短期間の飲酒で発現することがあります」







