「大学院で研究を続けることがキャリアの選択肢の拡大につながる」という認識が一般化されることが大事であり、それを可能にするのがスタートアップです。アメリカの大学院はシビアな競争社会ですが、関連するスタートアップ企業が数多くあるため、安全弁として機能しています。つまり、いざというときには研究室のメンバーが参加するスタートアップや、教授がアドバイザーを務める外部のスタートアップに就職する、などの選択肢があることが重要です。
日本と違って大学の研究者が
大金持ちになれるアメリカ
アメリカにおいて大学は誰にでも門戸が開かれ、かつ、「お金も稼げる魅力的な場所」です。日本で大学の研究者というと、清く正しく美しく、貧乏とまではいかないものの決して豊かではないというイメージが定着しています。しかしアメリカでは、大金持ちの研究者というのは存在し、それが成功例として積極的に公報されています。
最近話題になった事例では、ハーバード大学医学部のスプリンガー教授が、コロナのワクチンで有名になったモデルナ(ハーバード大学発のスタートアップ企業)の創業期に投資して、モデルナの上場で4億ドル(約560億円)を得たというニュースがありました。
彼の総資産は驚きの19億ドル(約2600億円=Forbesによる推定)となっています。また、モデルナのプロジェクトリーダーのハーバード大学の研究者Dr.Kizzmekia Corbettは若い黒人女性であることも公報されています。
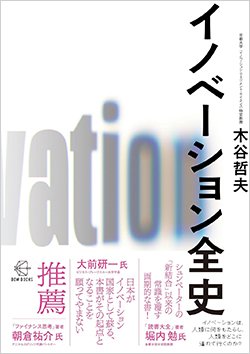 『イノベーション全史』(BOW&PARTNERS)
『イノベーション全史』(BOW&PARTNERS)木谷哲夫 著
つまり、「研究者でも大金持ちになれるチャンスがある」こと、「能力さえあれば人種や性別や年齢に関係なく責任ある立場で研究できる」こと、その2点をハーバード大学は積極的に発信しています。それにより、最優秀の人材を世界中から集めることができると考えるからです。
日本人男性がほぼ100%で人種差別、性差別に甘いイメージがあり、お金儲けは悪という価値観すらある日本の大学では、海外から優秀な研究者は来ません。
現状はそのように残念な状態ですが、しかし裏を返せば、これまで何も努力もしていないということは、ちゃんと経営努力をすれば将来の伸びしろが大きいということでもあります。これから成功パターンのロールモデルを作っていくことが、世界中から優秀な人材を惹きつけることになるはずです。







