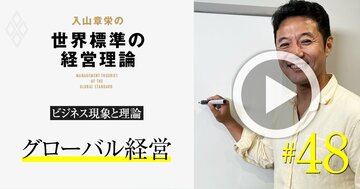写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
ライドシェアとフードデリバリーで知られる「ウーバー」が生んだ、好きな時に好きな場所で働ける「ウーバリゼーション」は、地球環境にも影響する革命的な変化を世界にもたらすものだ。2024年4月2日には、Uber Japanがタクシー会社による自家用車活用事業(ライドシェア)の導入支援を順次開始することを発表。シェアリングエコノミーの波は着実に広がり始めている。木谷哲夫『イノベーション全史』(BOW&PARTNERS)の一部を抜粋・編集したものです。
クラウドサービスから
誕生した「ライドシェア」
スマートフォンの個人ポータル化、クラウドサービス、通信衛星地図データ、自動翻訳技術、本人認証と決済技術の進化など、さまざまな技術進化がコンバージェンス(融合)したIoTで、「ソフトウェアが世界を食い尽くしている」代表的な事例として、ライドシェアがあります。
ウーバーは、トラビス・カラニックともう1人の創業者であるギャレット・キャンプによって、2009年に設立されました。きっかけは、サンフランシスコであまりにもタクシーがつかまらない、「今、この場で乗りたいのに、どんなに手を上げてもタクシーは止まってくれない」という2人の実体験に基づいています。
車両を所有しないのはクラウドサービスがコンピューターをシェアするのと同じ発想です。クラウドの利点は、アプリ開発やサービス運用にハードウェアの調達を必要とせず、リソースへの初期投資をゼロに抑えられる点ですが、ウーバーも車両は保有せずにアプリ開発とその機能向上に全力投入することができました。
現在、我々が海外に旅行し、現地の空港についてまずやることは、グーグルマップなどの地図アプリを開き、目的地をクリックし、地図の中に現れるライドシェアサービスから1社を選び、クリックし、値段や車種を確認し、クリックすることです。そうすると待ち合わせ場所、車種とナンバーがわかるので、数分後には乗車できます。
道中はリアルタイムで目的地までの経路上の今どこを走っているのかが表示されるため、これまでのように変に遠回りされる心配もありません。
ドライバーとの会話も不要で、すべてがアプリ上の日本語だけで完結します。価格は従来のタクシーよりはるかに安く、代金は最初に引き落とされており、両替して現地通貨を用意する必要も、あとになって支払いでもめることも、ぼったくりの心配もありません。