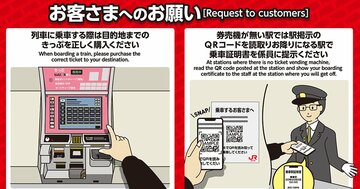JRと大手私鉄の適用ルール
実は業界全体では少数派
ここでどちらの主張が妥当なのか議論するつもりはない。だが、問題を先送りにしていては、当事者はいつまでも救われない。事態を打開するのは、鉄道事業者の従来の主張とは全く異なる考え方である。
ここまで「鉄道事業者は」と、障害者割引の適用ルールについて、あたかも一枚岩のように書いてきたが、JRと大手私鉄のほとんどがそうであるだけで、鉄道業界全体ではむしろ少数派なのである。
大手私鉄で唯一、古くから距離無制限の単独利用割引(以下、単独割引)を認めているのが西日本鉄道だ。西鉄は精神障害者の追加も他社に先駆けて行っており、この分野に積極的な印象だ。
また、中小私鉄では、単独割引を認める事業者が少なくない。例えば元国鉄・JRの第三セクター鉄道では、輸送密度上位5社のIRいしかわ鉄道、愛知環状鉄道、あいの風とやま鉄道、しなの鉄道、伊勢鉄道は、いずれも経営転換後、単独割引を設定した。
輸送密度下位で経営が苦しい南阿蘇鉄道、由利高原鉄道、錦川鉄道、長良川鉄道、わたらせ渓谷鉄道なども導入しており、経営規模の問題ともいえないだろう。
「三セクは自治体主導の半公営鉄道だから社会政策的な割引を導入しているのだ」という声があるかもしれないが、岳南電車、銚子電鉄、津軽鉄道、秩父鉄道など、純民間資本の中小私鉄も認めていることから、それが決定的な要素とも言い難い。
興味深いのは京成グループだ。京成は現在の営業制度では100キロ以下の単独利用を認めてないが、2022年9月に完全子会社化した新京成電鉄、株式の50.84%を保有する北総鉄道、また関連会社の小湊鉄道、舞浜リゾートラインは、単独割引がある。一方で、今年4月26日に完全子会社化した関東鉄道には単独割引はないなど、グループ内でまちまちだった。
そこで京成電鉄は6月1日の精神障害者追加に合わせ、単独利用時の「片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります」という制限を撤廃する。大手私鉄では西鉄に次いで、関東では初めての無制限の単独利用を認める事業者となる。
2025年4月に新京成電鉄を吸収合併することが決まっており、同じ事業者に2つのルールが存在する事態になることを避ける目的もあるのだろう。中小でも大手でも、やってやれないことはないのだ。