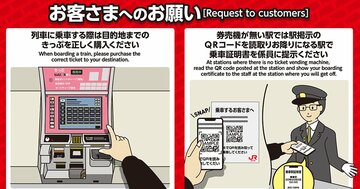単独割引を福祉政策の肩代わりではなく
ビジネスの視点で積極利用すべき
では単独割引を導入する事業者が、動きの鈍い国や自治体に代わって障害者福祉に力を入れようと考えたのかというと、そういうわけでもないだろう。鉄道が社会福祉政策の肩代わりは筋違いだとしても、(言葉は悪いが)自社の利益のため積極的に利用するという考えはあってしかるべきだからだ。
障害者手帳の保有者に対する割引措置は公共施設、交通以外にもテーマパーク、映画館、ミュージアム、カラオケなどさまざまな施設で導入されている。社会貢献も意識しているのだろうが、それが新たな顧客開拓につながるという判断があるのは間違いない。
ここで思い出されるのが、小田急と京急の取り組みだ。小田急は2022年3月から小児IC運賃の全区間50円均一化、京急は2023年10月から同75円均一化した。総人口に占める6~12歳の割合は5.7%(2023年10月1日現在)だが、小田急は「小児運賃収入は微々たる額なので、小児と移動する家族が増えればプラスになる」として、子育て家庭を沿線に取り込む狙いを説明する。
厚労省が2016年、2020年に行った調査によれば、総人口に占める在宅の障害者の割合は、身体障害者が3.4%、知的障害者が0.8%、精神障害者が4.6%で計8.8%だ(複数の障害がある人はそれぞれに計上)。ただし、身体障害者は65歳以上が占める割合が多いため、0~64歳に限れば総人口の0.9%になる。
国連総会が2015年に採択した「SDGs(持続可能な開発のための17の国際目標)」は今や至る所で目にする。鉄道事業者も2019年頃からプレスリリースに、この取り組みはSDGsのどれに当てはまるかを記載するなど、こぞってPRしている。
だが、それらの取り組みはSDGsと関係なく決定した後に、それらしいものを当てはめたにすぎない。都合のいいものだけを追い、本質的なところから目を背けるのではSDGsとはいえない。
SDGsには障害者福祉に関する項目がいくつもある。「目標1 貧困をなくそう」「目標3 すべての人に健康と福祉を」「目標8 働きがいも経済成長も」「目標10 人や国の不平等をなくそう」そして、「目標17 パートナーシップで目標を達成しよう」。
福祉政策の肩代わりではなく、潜在的な需要の掘り起こしと企業のイメージアップのため、ひいてはSDGs達成のために取り組む私鉄がもっと現れてもいいのではないか。要は大義名分があれば鉄道事業者は動くし、それが多数になれば他社も追随する。
なんとも主体性がなく情けない話だが、鉄道事業者を動かすロジックを組み立てることが現状打破の近道である。とはいえ当事者である障害者が「自分たちをマーケティングしてくれ」とは言いづらい。どうか鉄道関係者は胸に手を当てて、できることはないのか考えてほしい。