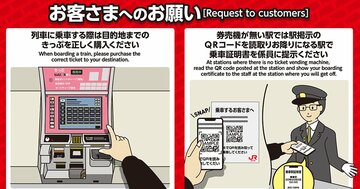今の時代にそぐわない
障害者割引適用のルール
割引を拡大する事業者と当事者の間に、どんな隔たりがあるのだろうか。
国立国会図書館の調査報告『公共交通における障害者・高齢者運賃割引制度』によれば、障害者割引制度は1949年に制定された身体障害者福祉法に基づき、介護者を必要とする身体障害者が乗車する際に両者の運賃を半額とする旨の規定が国鉄運賃法に追加されたことに始まる。
1952年に障害の等級による「第1種」「第2種」の区分を設け、「100キロを超える場合の単独乗車の割引」を追加した。1991年に知的障害者、今回、精神障害者が追加されたが、制度の基本的な骨格はこの頃から変わっていない。
その上で、精神障害者追加後の制度をまとめると、運賃が5割引きになるのは次の2つのケースだ。
(1)第1種の身体・知的・精神障害者とその介護者が同乗する場合、本人および介護者の両者
(2)第1種・第2種の身体・知的・精神障害者が単独乗車し、なおかつ距離が100キロを超える場合
しばしば誤解されるが、障害者が1人で鉄道を利用するほとんどのケースで運賃の割引は適用されない。介護者と一緒に利用する場合は双方が半額、つまり2人で1人の運賃で利用できるというわけだ。
1人で101キロ以上(他社線との連絡運輸=1枚の切符で発行できる範囲を含む)の利用では、新幹線などを利用した場合でも運賃のみが半額となり、往復割引など他の割引制度とは併用できない。つまり日常的な鉄道利用は対象外となる。
これに対して前述の署名サイトでは、現状について下記のように紹介し、100キロ以下でも単独利用を認めるように訴える。
皆さんは、障がい者が鉄道を使って移動する際、「介護者が同伴」または「単独の場合は101キロ以上の移動」でないと、障がい者割引が適用されないというルールがあることをご存知でしょうか。
このルールはJRや小田急電鉄など、多くの鉄道会社が決めているものです。しかしこのルール、実は旧国鉄時代に定められたとても古いもので、バリアフリー化が進んで障がい者が1人でも移動できる今の時代にはそぐわない制限になっています。
このルールはJRや小田急電鉄など、多くの鉄道会社が決めているものです。しかしこのルール、実は旧国鉄時代に定められたとても古いもので、バリアフリー化が進んで障がい者が1人でも移動できる今の時代にはそぐわない制限になっています。