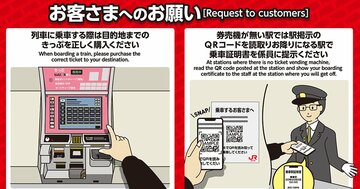社会政策的な割引の原資を
民間企業が負担すべきなのか
2023年4月のTBS系「news23」は、「障害者は介護者と二人で一人ではない。一人の人間として扱ってほしい」という当事者の声や、バスやタクシー、航空、フェリーなどには単独利用割引があることを紹介し、「鉄道の謎ルール」と報じた。
ただ、鉄道側から言えば(業界にいた筆者の感覚としても)、鉄道は障害者を1人の人間とみているからこそ、1人で移動できる人には通常の運賃を求めている。制度が創設された当時、第1種・第2種に該当する重度の障害者が1人で移動するのは困難であるため、介護者を実質的に無料としているという考えだ。
鉄道事業者には一般の人が想像する以上に、「鉄道は低廉な運賃で広く誰でも利用できる公共サービスであり、運賃区分、利用区間、利用設備が同じであれば運賃、料金も同一であるべき」との思想が強いのである。その代わり、全利用者から収受した運賃で、誰でも使いやすいようにバリアフリー設備を整備するというわけだ。
とはいえ、一般の利用者と障害者では置かれた立場は違うという反論があるだろう。事実、厚生労働省の「障害者雇用実態調査」によれば、就労する身体障害者の平均年収は250万円程度で、日本の平均年収から200万円も低い。苦しい生活の中、鉄道の割引を拡充してほしいという声は切実だ。
だが、鉄道事業者はそもそも、社会政策的な割引を鉄道事業者が負担することに否定的だ。
鉄道にはさまざまな割引がある。例えばJR本州3社は旧国鉄の流れを引き継ぎ、通勤定期券の割引率を5割以上としているが、国鉄時代は6割、7割あるいはそれ以上の時代もあった。これは都心で電車通勤が増え始めた1920年代、また戦後のインフレ下において、庶民の負担軽減を目的に割引を拡大したことに由来する。
また、通勤定期以上に大幅な割引がされている通学定期券は、本人および家族の学費負担を軽減目的としたものであるし、学生旅客運賃割引(学割)も学生の帰省の援助策として設けられたものだ。
これら社会政策的な割引の原資は、国が鉄道を直営していた時代であればまだしも、独立採算的な公共企業体として設立された日本国有鉄道(国鉄)や、民営化したJRが負担するのは筋違いで、国や自治体が文教費や社会福祉費で負担をすべきだと訴えてきた。