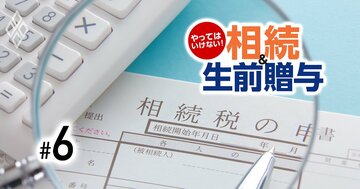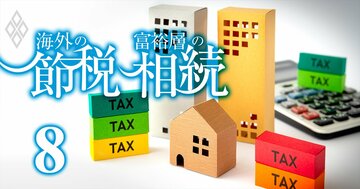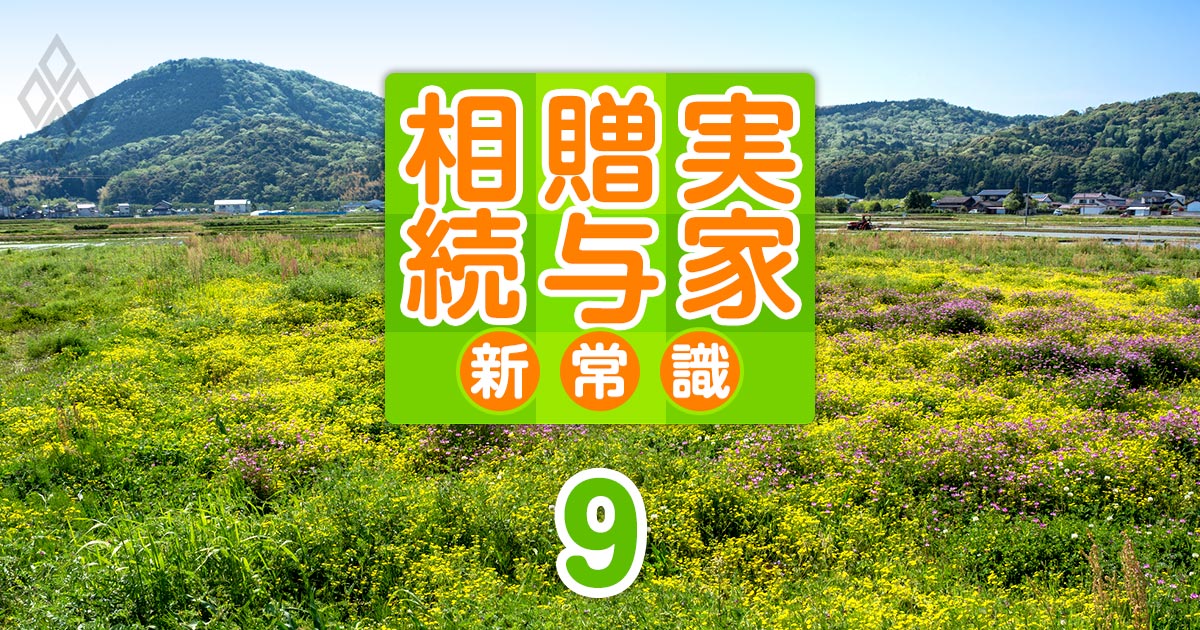 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
所有者不明の土地への対策の一環として新しくできた、相続土地国庫帰属制度。相続した不要な田畑や宅地など“負動産”を国に引き取ってもらえる制度で、2023年4月に始まってからちょうど1年が経過した。まだ実例は少ないものの、大方の予想に反して、専門家たちからは「意外に使える制度だ」との評価を得ている。特集『法改正で知らない間に損をしない!相続・贈与・実家の新常識』(全13回)の#9では、23年秋に田舎の田畑を相続した記者が、相続での制度の使い勝手や実態を、体験を踏まえて徹底検証した。(ダイヤモンド編集部編集委員 藤田章夫)
相続した使い道のない不動産を
国が引き取ってくれる制度がスタート
“負動産”の相続は大変だ。この言葉を、記者自ら実感するとは想像していなかった。
2023年秋に養子縁組をしていた伯母が亡くなり、兵庫県にある田舎の田畑を相続した。広さは4反半で約4500平方メートルにもなる。かつては米や野菜を作っていた。しかし高齢の伯母は10年ほど前から耕作しなくなり、定期的に雑草を刈るだけのいわゆる耕作放棄地になっていた。
 Photo by Akio Fujita
Photo by Akio Fujita
この田畑を相続し、途方に暮れた。処分しようと不動産会社や農協などに相談したのだが、返ってきた答えがこれだ。
「ただでも引き取り手はいませんよ。いらない田畑を売りたいという人が列を成している状態で、登記費用を全額負担したとしても難しいですね」
農地を相続すると、かなりやっかいな事態に直面する。農地を売却したり、宅地に変更(農地転用)したりするには、農地法の壁が立ちはだかるからだ。
というのも、農地を売却するには相手先が「営農計画を持っていること」「農作業に常時従事すること」などの要件があるため、週末農家では買い手になれず、売却先は農家か農地所有適格法人などに限定されるからだ。
しかもややこしいことに、相続した田畑は市街化調整区域内にあった。都市計画法により、住宅開発を抑制するように指定された区域のことで、住宅地にするなど他の用途に転用するのが困難なのだ。
そのぶん固定資産税は年間1万円未満と格安だが、1回当たり10万円以上かかる草刈りを年に2~3回は行わねばならない。維持費ばかりがかかる、まさしく“負動産”を抱えることになってしまった。
買ってくれそうな人がいないか、不動産会社や農協を回って話を聞いた。しかし前述のように、ただでも買い手は現れない。田舎の農家はもはや高齢者ばかりで、これから農地を買おうという人など皆無だ。その一方で、先祖から引き継いだ土地とはいえ、不要な農地を手放したい人が山のようにいるのが実情なのだ。
そうした中、まさしく“干天の慈雨”というべき制度が23年4月27日から始まった。それが、相続した不要な不動産を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度(以下、帰属制度)」だ。
もしかすると、記者が相続した田畑で使えるのではないか。そう期待したものの、始まったばかりの制度で、まだ実例は少ない。専門家に話を聞いてみると、「意外に使える制度だ」と評判だ。
次ページでは、帰属制度や負動産の処分に詳しい荒井達也弁護士のアドバイスと共に、帰属制度の相続での使い勝手や実態を、記者の体験を踏まえて徹底検証する。