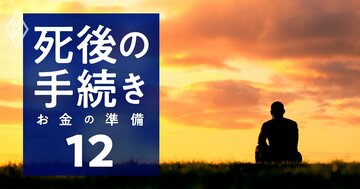Photo:SetsukoN/gettyimages
Photo:SetsukoN/gettyimages
親が認知症などになり判断能力が著しく低下すると、銀行での手続きや法律行為ができなくなる。そうした際に、親を支援してくれるのが成年後見制度だが、使い勝手の悪さから法改正に向けた議論が行われている。特集『法改正で知らない間に損をしない!相続・贈与・実家の新常識』(全13回)の#12では、後見制度の実態から法改正の議論の方向性までを詳述した。(ダイヤモンド編集部編集委員 藤田章夫)
認知症を患う人は600万人に上るが
成年後見制度の利用者数はわずか25万人
世界一の長寿国、日本。WHO(世界保健機関)が発表した2023年の統計によれば、日本人男女の平均寿命は84.3歳で、世界で寿命が最も長い国となっている。
長生きするのは喜ばしいことだが、その一方で、高齢化に伴い認知症を患う人の数が25年には700万人に達すると推定されている。実に、65歳以上の5人に1人が認知症になると予測され、相続の場面においても大きな問題となっているのだ。
というのも、認知症になって判断能力が不十分になると、遺産の分け方を決める遺産分割協議が成立しないなど、法的な決め事ができなくなってしまうからだ。
例えば、遺言書を残さずに父親が亡くなり、母親と子供たちで残された財産を法定相続分とは異なる形で分けようとしても、母親が認知症を患っていたら、遺産分割協議は無効になる。こうした場合には、母親に成年後見人を付けるしか手はない。
この成年後見人とは、認知症や精神上の疾患などにより判断能力が低下し、法律行為の結果を判断できなくなった「成年被後見人」をサポートする人のことだ。
親が成年被後見人になるとどうなるか。日常生活のある程度のことなら家族が本人に代わってできるが、銀行での手続きや不動産の売却、介護施設への入所などは本人の意思が必要となるため、家族であっても代わりはできない。
相続の場面においても同様で、生前贈与はできないし、成年被後見人が作成した遺言は無効と判断される可能性が高いという。そこで、遺言を作成するような身分行為についてはできないものの、本人を代理して法律行為を行える制度が、成年後見制度というわけだ。
この成年後見制度ができたのは、2000年4月のことで、介護保険制度と共に施行されている。身体を介護保険で、判断能力を後見制度で共にサポートするのが狙いだ。
こうして見るといい制度に見えるが、利用者はかなり少ない。厚生労働省は20年時点の認知症高齢者の数は約600万人と推定しているが、成年後見制度の利用者は約25万人しかおらず、わずか4%程度にすぎない。
理由は、家族が本人に代わって手続きを行っていることが多く利用するメリットを感じにくいのに加え、制度の使い勝手が悪く、利用者からの不満が絶えない点が挙げられる。そこで現在、法制審議会の民法部会で制度改革について議論が進められている。
次ページでは、制度の中身に加え、どのような点に不満が多いのか、また、法制審の改革の方向性について詳述していく。