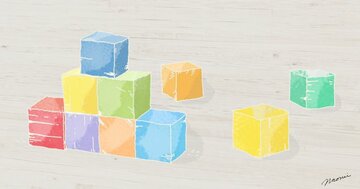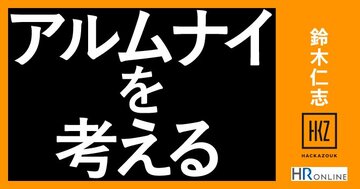世代間コミュニケーションの難しさを感じているビジネスパーソンに読まれている良書がある。書名は、『なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の選び方』『難しい相手もなぜか本音を話し始めるたった2つの法則 入門・油田掘メソッド』――著者は、どちらも、元NHKキャスターの牛窪万里子さんだ。25卒内定者向けメディア「フレッシャーズ・コース2025」にも出演している牛窪さんは、これまでに5000人以上をインタビューしてきた「聞く」「話す」ことのスペシャリストであり、フリーアナウンサーが所属する企業の経営者でもある。「HRオンライン」が、そんな牛窪さん自身の発する言葉に耳を傾けた。(ダイヤモンド社 人材開発編集部、撮影/菅沢健治)
受ける仕事に対しては、“本人の意思”が大切
NHKのキャスター、リポーターとして活躍した経歴を持ち、現在は「ラジオ深夜便」(NHKラジオ)のインタビュアー(*1)のほか、講演会やセミナーの講師など、幅広く活動している牛窪万里子さん。牛窪さんは、フリーアナウンサーが所属する株式会社メリディアンプロモーションの経営者でもある。まず、組織(チーム)を束ねるリーダーとしての役割を尋ねた。
*1 牛窪さんは、「ラジオ深夜便」で、23時台&朝4時台「明日への言葉」のインタビュアーを務めている。
牛窪 2002年に設立した弊社に、現在は10人ほどが所属しています。それぞれのメンバーと業務委託契約を交わし、クライアントの依頼を受けて、一人ひとりが仕事の現場に向かうスタイルです。経営者である私の重要な役目は、受けた仕事とメンバーの個性をマッチさせること。それをスムーズにするために、メンバーの「強み」を知っておくことが不可欠です。強みは一人ひとりで違いますから、そのメンバーがこれまでに何を行ってきたかを把握し、本人が望むことをヒアリングしたうえで、どのような仕事がマッチするかを一緒に考えます。そして、受注した仕事を受けるか受けないかを相談して決めていきます。
本人が「(仕事を受けることが)難しい」と感じたら、私は無理には勧めず、意思を尊重するようにしています。仕事はモチベーションが大切ですから、いくら条件がよくても、やる気がなかったら、うまくいきません。もちろん、本人のモチベーションを上げていくことも、私の仕事になります。

牛窪万里子 Mariko USHIKUBO
株式会社メリディアンプロモーション 代表取締役
フリーアナウンサー
元NHKキャスターとして「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」などに出演。現在は、NHK「ラジオ深夜便」のインタビュアー、「身近なことからSDGs」のパーソナリティを務めるほか、司会やコミュニケーションアドバイザーとして、さまざまな講演会やイベント、セミナーなどで活躍している。書籍『なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の選び方』『難しい相手もなぜか本音を話し始めるたった2つの法則 入門・油田掘メソッド』ほか、著書多数。
牛窪さんと約10人のメンバーは、ひとつのチームではあるものの、一般的な企業のように、同じ職場で同じ仕事に携わることはほとんどない。そうした状況もあって、牛窪さんは、メンバー一人ひとりとこまめにコミュニケーションをとり、それぞれが受けた仕事の後に、“アフターケア”を行うことを心がけているという。
牛窪 メンバーに仕事をオファーするときだけではなく、終わった後も、必ずヒアリングをするようにしています。順調に仕事を終えたとしても、本人としてはうまくいかなかったと感じることがあったりするので、仕事現場での様子をつぶさに聞くようにしています。現場に私が同行したときは、終わってから食事に誘ったりして話を聞きますし、直接に会話ができなくても、電話やメールでやりとりをしています。普段から、ちょっとした空き時間にお茶をするなど、対話する時間を作るようにしています。
みんなそれぞれに、プロ意識や仕事への信念を持っているのですが、なかには「自分の能力が足りないから、その仕事は受けられない」と断ってくるケースも。このような、自分で限界を作ってしまうメンバーへの対処法として、どこに能力の不足を感じているのかをヒアリングしたうえで、「やってみれば、世界が広がるかもしれない」「こういう考え方もあるのでは?」と、本人の固定観念を柔らかくほぐしていくことも。仕事を受けるかどうかを迷っているときは、「できるか、できないか」ではなく、「やるか、やらないか」で決断するように促しています。人は未経験のことに対しては誰もが不安を感じるものですが、そこを突破すると可能性は広がっていくものです。
メンバーの個性を理解しながら、背中を押すつもりで言葉を投げかけ、決して無理強いせずに、クライアントの意向と本人の意思を折り合わせていくことが肝心だと思っています。