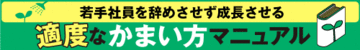「私たちの世代は、世の中が良くなるとか、経済が成長し続けるとはあんまり思っていないんです」という、新人ナカムラ。バブル崩壊後に育った世代の世界観は、私たち上司世代とは決定的に違っている。
今回は、20代の若手社員たちがどのような時代の中で育ってきたのかを検証してみたい。それによって、なぜ若手が「成長実感」を強く求めるのか、そして、なぜ早々と会社に見切りをつけるのか。その理由の一端が見えてくる。それは、とりもなおさず「適度なかまい方」のための前提でもある。
バブル崩壊の年
新入社員は小学校1年生だった
突然ですが、40代の読者諸賢は、小さいころにどんな未来を思い描いていたでしょうか。 高度経済成長は終盤に差し掛かっていたとはいえ、1970年の万博、アポロの月面着陸など、明るい未来を感じさせるビッグ・イベントが目白押しだった少年時代。遥かな未来と思っていた21世紀になってみると、まさかというような冴えない時代。「未来って、こんなにしょぼいもんだっけ?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
一方、いまの若手たちは、幼いころにどんな未来を思い描いていたのか――。
「ものごころついてから、ずっと暗いことばかりなんです」と新人ナカムラは言います。話しを聞いてみると、彼(女)たちの就労観、3年以内に会社を辞めてしまう諦めの良さ(?)も、育ってきた時代の影響がきわめて大きいことがわかってきます。今回は、そのことを検証してみたいと思います。
まずは下の年表を見てください。新人ナカムラが生まれてからこれまでに起こった事柄をまとめた年表です。これに上司である私の社会人歴を並べてみました。私がダイヤモンド社に入社した年、新人ナカムラは2歳でした。
| ◎今年の新入社員は「バブル崩壊」の年に小学校に入学した |
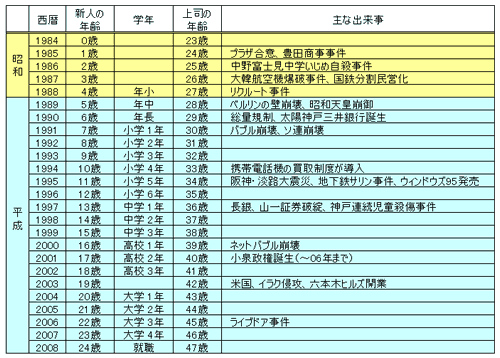 |