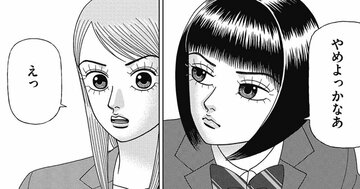加藤は、大学は「真理を探求する研究」を行い、「社会的に有意義な人材を養成する教育」を行う場であるが、「そのような方面に女性の能力が向いていないということは、一般的にいえるのではなかろうか」と論じていた。
また、この社会には女性に対する差別があるのは確かだが、それにもかかわらず活躍している女性もいる。「打ち破れない差別ではない」のだから、自分の能力不足を「タナにあげて社会を責めるなら“女子大生とは気楽な稼業ときたもんだ”といいたい」と批判した。
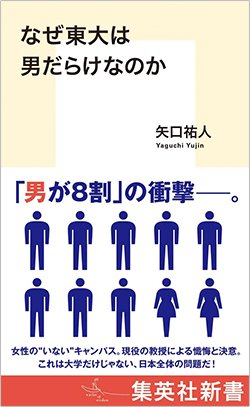 『なぜ東大は男だらけなのか』(集英社)
『なぜ東大は男だらけなのか』(集英社)矢口祐人 著
とはいえ、このような「気楽な」女性を大学から追い出す必要はない。そうではなく、女性たちには教養を高め、「家庭的能力」をみがくための「女子学部」を設けるべきだと加藤は提案する。
もちろん「家庭的能力」のみならず「社会的能力の2つを持つ女性は、女子学部以外に、いまのとおり進めばいい」。しかし社会の差別を打ち破れない程度の女性は、共学の大学では女子学部に入ればいいという主張であった。
加藤の論は『毎日新聞』では男性による投書の「代表的な意見」として紹介されており、尾崎と同じく、大学を女性向けの花嫁学校と割り切る考えのものだった。
このように、当時の大学は女性の学生の存在をある程度は許容しながらも、教職員から学生に至るまで、その能力を疑問視し、男性に都合の良い価値観から判断する意識が広く共有されていた。