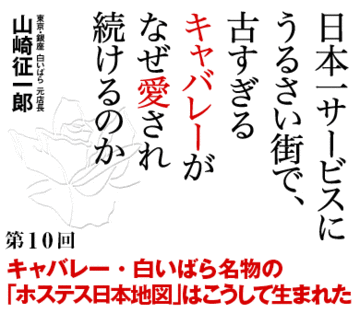Illustration by MIHO YASURAOKA
Illustration by MIHO YASURAOKA
「昭和の女帝」真木レイ子は、総理大臣の吉田茂が大磯の自邸で開く自由党幹部会に参加を許されている実力者だ。『小説・昭和の女帝』の第二章(#3~#17)では、時を戦前に遡り、レイ子が「政界の黒幕」や「フィクサー」と呼ばれた権力者たちの知遇を得ることになった秘密に迫る。(『小説・昭和の女帝』#3)
戦前の新橋のバーで、将来の大物政治家と邂逅
19歳の春、レイ子はコーラスグループに所属していた。
劇場や放送局で脚光を浴びるのは無上の喜びだったが、年齢的に曲がり角に来ていることは自覚していた。グループの中で、彼女はもはやベテランで、後輩に先を越され、歌手デビューされてしまったことも一度や二度ではなかった。
なぜ、デビューさせてもらえないのか。理由はいくつか思いつく。
最も大きな理由は、男勝りの性格だ。彼女は子供のころから竹馬など男の子の遊びばかりしていた。野球チームを作り、投手をやったこともあった。コーラスグループではマネージャーや仲間とぶつかることが多く、浮いた存在になっていた。
女性にしては長身で、和装が似合わないことも理由の一つだ。三味線や長唄など芸事を習ったこともあったが、日本髪のかつらを着けると男性より大きくなってしまう。肩幅が広いので、華奢な女の子たちと並ぶと悪目立ちするのだった。
しかし、幼いころからの夢だった芸の世界に区切りをつけることはできなかった。このまま終わりたくなかった。
レイ子には、父の記憶がない。ものごころつく前に母が結婚した男に育てられた。育ての父は新聞配達店を経営しており、経済的な苦労はなかったが、裕福といえるほどでもなかった。実父がどこにいるか分からないことは子供心に寂しく、悔しい思いをした。自分には、優しくて金持ちの本当のお父さんがいて、いつか迎えにきてくれる……。幼心にそんな淡い期待を抱いたこともあった。
育ての父が、実の父ではないと知ったのはいつ頃のことか。それが気になって、尋常小学校に入ってから母に聞いたことがあった。「ねえお母さん、本当のお父さんがいるって、私が知ったのはいつのこと?」と。母は少し戸惑ったような顔をして、「三つか四つぐらいのときじゃないかしら」と言った。レイ子は少し考えて、ぞっとした。「本当のお父さんがいて、いつか迎えにきてくれる」と、自分に言い聞かせたのが、母だったことをうっすらと思い出したのだった。
母の再婚相手である新聞配達店の経営者は、風采の上がらない小太りの男だった。おまけに母より十も年上で、レイ子の目からみても釣り合いの取れていない夫婦だった。
そういう冷酷な大人の現実を突き付けられて育ったからか、母がかわいそうな一人娘に恰好だけは贅沢させてやろうと洋服などにおカネをかけたからか、レイ子は、プライドが高く、負けず嫌いに育った。
だが、高等小学校に上がると、レイ子は自分とは格の違う女の子がいることを思い知らされることになった。お気に入りのセーラー服を着て入学式に行くと、そこには別世界に住むような女の子がいた。ゆるくカールさせた髪に大きなピンクのリボン、かわいらしいピンクのドレス。お供の者がぞろぞろとついて歩いていた。歌も踊りも自分のほうが上手いのに、学芸会で主役を演じるのは彼女だった。先生たちは皆きれい事を言うが、結局、金持ちの子を大事にするのかと憤りを感じた。
男の子から「芸者の娘」と馬鹿にされ、自分の家庭の複雑さを思い知らされたこともあった。
ただ、十代になると、「自分は美しい」という自負が芽生えていた。有名になって、自分を見下した人たちを見返してやりたかった。その気持ちは二十歳を前にしても弱まることはなかった。
◇
彼女には、コーラスグループとは別の仕事があった。新橋のバーでホステスをしていたのだ。夜の仕事は、歌やダンスのレッスンでくたくたになってから始まる。注文ごとに客がおカネを払うお店で、粗野な客が多かった。
耐え難かったのは街に立ち込めるどぶの臭いだった。それをかき消すためなのか、皆が強い香水をつけ、たばこをひっきりなしに吸った。店内のトイレからは排泄物の臭いが漏れていて、出勤するたびに慣れるのに時間を要した。というか、客と一緒に酔ってしまわなければ、やっていられないのだった。
昭和の女帝
小説・フィクサーたちの群像
千本木啓文著
<内容紹介>
自民党の“裏面史”を初めて明かす!歴代政権の裏で絶大な影響力を誇った女性フィクサー。ホステスから政治家秘書に転じ、米CIAと通じて財務省や経産省を操った。日本自由党(自民党の前身)の結党資金を提供した「政界の黒幕」の娘を名乗ったが、その出自には秘密があった。政敵・庶民宰相との壮絶な権力闘争の行方は?