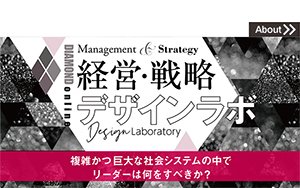さらに責任の所在やプライバシーの問題など、法整備や社会の合意形成には時間がかかり、多くの専門家は人間とAIが協働する形が主流になると予測している。よって、ここしばらくはAIを使いこなせる人材が、次の旬な人材になるだろう。
AIの分析結果を活用しながら、人間がより高度な判断や創造的な作業を進めることで、意思決定の迅速化と質の向上が見込まれる。しかしながら、これらはあくまで現行のAI水準における議論であり、将来的にどの程度まで代替が進むかは未知数である。
また、AIの開発前提として「人間のために支援する」という視点があることも忘れてはならない(AIがAIのために意思決定するような時代が来れば、そのときは、想像すらできないが、AIにとって都合の良いタイプの人間が旬になるだろう)。
技術が進化するほど
「共感力」が武器になる!?
別の視点から言うと、このように技術が進めば進むほど、人間らしさや思いやりの重要性が増すのは確実であろう。自動化の広がりによって差別化要因となるのは「人の痛みを理解し、寄り添う」ような“情”の領域である。
医療や介護などでは患者の安心感を支える役割がますます大切になり、ビジネスでも論理的な回答づくりはAIに依存しつつも、顧客の気持ちを理解して解決策を提示する共感力が企業の強みとなる。リーダーシップにおいても、心理的安全性を提供しながらメンバーを引き立てる手腕が注目されている。
こうした流れから、テクノロジーが高度化するほど、人間らしい関係性が新たな価値として一層見直されていくと考えられる。
コロナ禍でリモートワークが普及しても、アフターコロナでは、「やはり対面」「やはり出社」がハイブリッド的に選択されていることからもそれは明らかだろう。
いずれにせよ、今日旬だからといって明日なお旬であるかどうかはわからない。しかもその転換スピードが異常に早い。現状に安住することなく、絶えず変化し社会の変化に対応していかなければ取り残される恐ろしい時代になっている。少なくとも、そしてこの異常性を平常と考えるメンタリティーに変えなければならないだろう。
(プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役 秋山 進、構成/ライター 奥田由意)