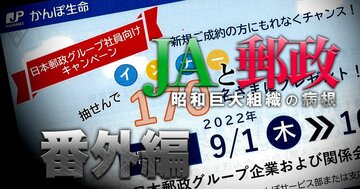まともな営業ではとてもこなせないノルマ。局員たちは競うように乗り換え契約を続け、次第に乗り換えを提案できる客もいなくなった。指導役の「インストラクター」を務める同僚に尋ねても「俺らも、どうやって教えていいか分からん」と言う。
堂々と、乗り換えを客に勧めるよう不適切な指示を出す幹部がいる一方で、会社からは「適正な営業をしましょう」と形だけの指示文書が送られてくる。
「これ以上、お客さんに迷惑をかけたくない。もう限界です」
男性の表情には、絶望感がにじんでいた。
「2年話法」なる
不適切な勧誘
乗り換え契約に関しては、他にも証言があった。
中国地方の渉外社員が明かしたのは、乗り換えに伴う「2年話法」だ。
渉外社員たちは、本来は目的外の利用が禁止されている、ゆうちょ銀行の貯金データを閲覧しては、2年分の保険料が支払えそうな顧客を物色する。自宅を訪問し、「まずは2年間、加入してみましょう」と勧め、2年分の保険料を前払いさせる。そして、2年がたつと、同じような保険に乗り換えさせるのだ。
なぜ2年かといえば、担当した契約が2年以内に解約されれば、渉外社員は契約に伴って受け取った営業手当を返納しなければならないというペナルティーがあるからだった。
私が入手した内部資料には、契約からの経過期間ごとの解約件数を記した折れ線グラフが載っており、2年経過直後の解約件数が突出している。
ひどい場合は、2年が経つたびに乗り換えを繰り返させられている顧客もいた。こうした不自然な契約は、上司が承認しているし、委託元のかんぽ生命も把握していた。
局員たちはこの他にも、契約を取るためのさまざまな不適切な手口を証言した。
当時、郵政グループの社内規定では、70歳以上の高齢者に営業する際は、家族の同席が必須とされていた。だが、息子や娘が同席すれば手間がかかり、断られる可能性も高くなる。
このため、「家族が遠方に住んでいる」「本人が希望しない」といった場合には家族同席が必要ないという例外規定を悪用し、高齢顧客に「同席は必要ありませんよね」などと誘導する渉外社員もいるという。