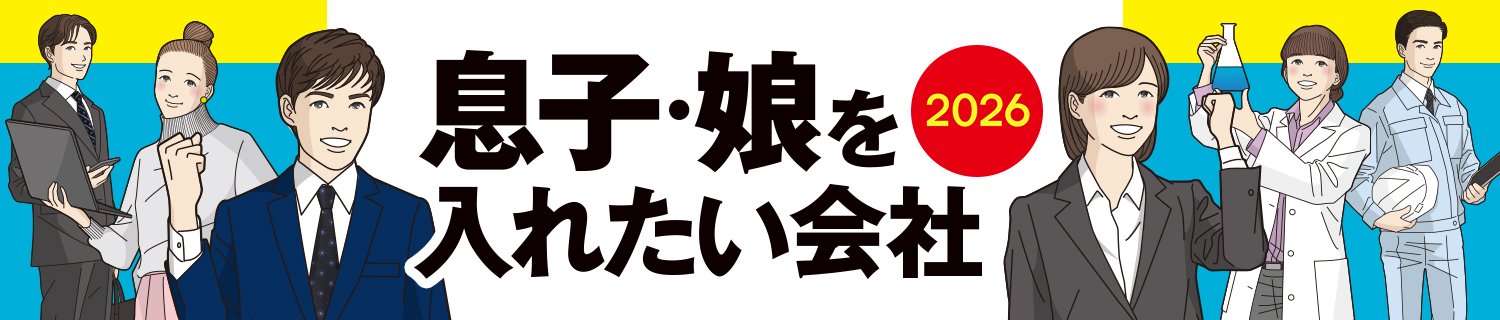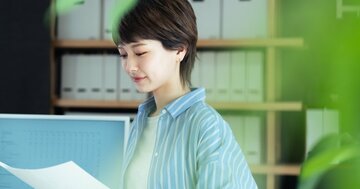大学の教職員の間でも、早期化への懸念は広がっています。ある大学の教授は、「ゼミが一番忙しい3年生の時期に就活が重なり、学生は精神的に大きな負担を抱えている」と言います。具体的なケースとして、1月後半に面接選考が入ったことでプロジェクトの成果発表会に6人中3人が参加できない事態になったことがあったそうです。
学生を早く確保したいという企業側の気持ちも分からなくはないとしながらも、「『ゼミ活動を半年間頑張ってきたのに……』と、本人たちも苦渋の決断をせざるを得ずにとても悔やんでいた」と語っていました。
4割強の学生が就職先を
「安易に決めた」と感じている
年々進む早期化の流れは、学生の進路決定にどのような影響を与えているのでしょうか。
25年卒の就職確定率は91.7%となり、当研究所での調査開始以来の最高値となりました。一方で、就職先決定を振り返り、どのような考えを持っているか聞いたところ、「安易に決めてしまったと感じる」について「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」と回答した学生は43.6%いることが分かりました。
この、「就職先決定を振り返ると、安易に決めてしまったと感じる」割合は、「就職先を確定するにあたり、自分が重視する基準が分からなかった」という学生では65.8%、そうでない学生では31.1%となり、大きく開きが出ています。つまり、自分なりの選社基準や軸があいまいなまま就職活動を進めていた学生ほど、進路決定に対しての確固たる自信や納得感が低いと考えられます。
さらに、「安易に決めてしまったと感じる」学生は、そうでない学生と比べて入社予定企業等での勤続期間の意向が短い傾向も出ています。
25年卒では、エントリー(採用選考への応募)数は前年より減っているにもかかわらず、内定率は高くなっています。内定獲得という観点だけで見れば、学生にしてみれば“効率的な”就職活動ができているといえるかもしれません。