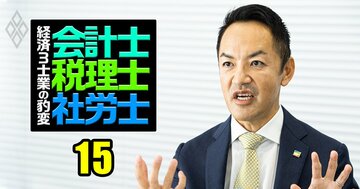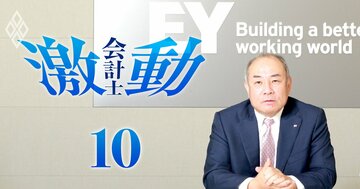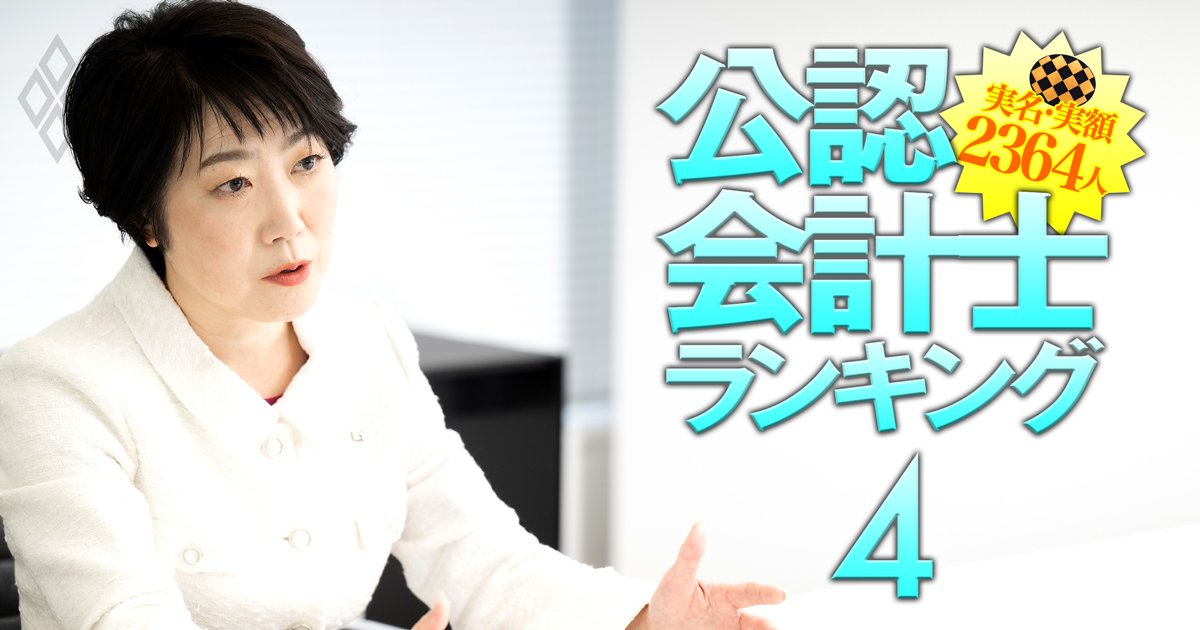 Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
監査証明業務の売上高で、監査法人トップのEY新日本有限責任監査法人。規制強化や公認会計士の監査離れなど、業界が抱える課題についてどう対策を打つのか。特集『公認会計士「実名」「実額」2364人ランキング』の#4では、片倉正美理事長を直撃した。(聞き手 ダイヤモンド編集部副編集長 片田江康男)
サステナ情報の開示義務化は
監査法人にとってチャンス
――2027年3月期から、時価総額3兆円以上の東京証券取引所プライム市場上場企業でサステナビリティ情報に関する開示が義務化されます。監査法人にとってチャンスなのでしょうか。
もちろんチャンスです。監査法人はISSA5000(国際サステナビリティ保証基準)に即した保証業務を担うことになると思いますが、売り上げが得られるだけではなく、人材育成としても大切な機会です。
今は財務数値だけで企業の価値は測れません。その企業がサステナビリティにどう対応しているのかなどが企業価値を測る大きな要素になっています。そうした非財務情報の保証業務を理解することは、会計士の能力を高められますし、監査法人にとってはビジネスの拡大につながると考えています。これほど良い一石二鳥のテーマはないのではないかとさえ思っています。
――サステナ保証は公認会計士の独占業務ではなく、他の専門家もできる業務です。公認会計士はサステナ情報の保証業務を担う人材として優位性があると考えているのでしょうか。
ブティック系のコンサルティングファームには専門性を持つ方もいると聞いています。監査法人や公認会計士ではない人たちも、サステナの保証をどんどんやればいいと思います。
一方で、サステナ情報の開示を行う企業にとっては監査を依頼している監査法人が必ずあります。すでに会社をよく知っている監査法人が保証を担ってくれるメリットは大きいと思います。
サステナ情報の開示義務化とその保証業務は、チャンスだと明言するが、足元では監査証明業務における課題も存在する。若手公認会計士の監査離れと監査法人からの離脱は続き、公認会計士に対する年収面での競争力低下も顕著だ。放っておけば、将来的な監査の劣化に結び付くことも考えられる。それらについてどう対策を打つのか。次ページで直撃した。