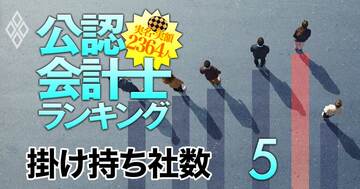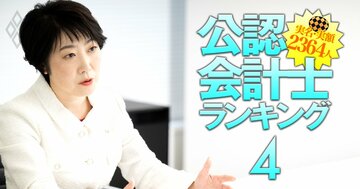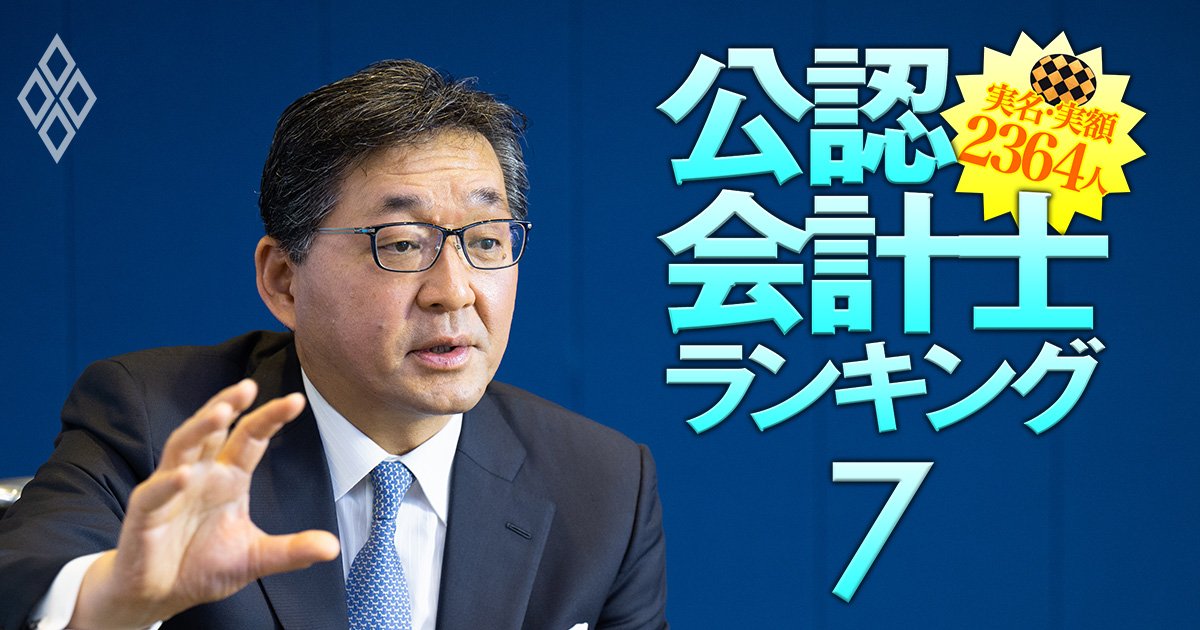 Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
あずさ監査法人は、東証プライム上場企業の中で時価総額の大きい大企業の監査を多く担当している。また20年前からサステナビリティ情報の開示が義務化されることを見越して投資を続け、準備を進めてきた。今の状況をどう見ているのか。特集『公認会計士「実名」「実額」2364人ランキング』の#7では、あずさ監査法人の山田裕行理事長に話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部副編集長 片田江康男)
サステナ情報の保証は監査法人が担うべき
監査で培った体制の活用は企業にプラス
――サステナビリティ情報の開示が、時価総額3兆円以上の東京証券取引所プライム市場上場企業でスタートします。独立系コンサルティング会社などが非財務情報の保証業務を行うことも考えられますが、現状をどう捉えていますか。
企業は財務情報に加えて非財務情報を開示することになりますが、その両方とも企業のアクティビティから生まれていることを考えると、お互いに非常に強い関連性があります。例えば、ある企業がある設備をリニューアルして2040年までに二酸化炭素排出量を削減するという非財務情報を開示していた場合、財務情報では40年までに設備の償却のスピードを速めたり、あるいは減損したりするなど、情報は整合している必要があります。
これを財務情報の監査をしている監査法人とは別の法人がチェックすることは、企業にとってよいことなのかと考えると、そうではないだろうと思います。財務と非財務の情報を、関連性を踏まえてチェックできる人が担った方が、企業にとっても社会にとってもベネフィットは大きいはずです。結果的に、担い手は監査法人になると思います。
それに監査や保証を行うには、企業との間で金銭的な利害関係がないなど、独立性が要求されています。当法人はそれを実現できるプラットフォームがあります。世界ベースで常時チェックをしているプラットフォームを持っているのは、おそらく監査法人以外にありません。このプラットフォームを使って非財務情報の保証を提供した方が、企業にとってもコストの低減につながりますし、社会に対しても価値を提供できると考えています。
――あずさ監査法人は、四大監査法人(監査法人トーマツ、あずさ監査法人、EY新日本監査法人、PwC Japan監査法人)の中でもいち早く非財務情報の開示へ向けて準備してきました。現在の状況を見越していたのでしょうか。
サステナ情報の開示において、あずさ監査法人が四大の中で優位性があることは業界内では共通認識になりつつある。なぜ競争力を持つことになったのか。若手公認会計士の監査離れや処遇、パートナーになるために必要な能力、出世の条件まで、山田理事長に話を聞いた。