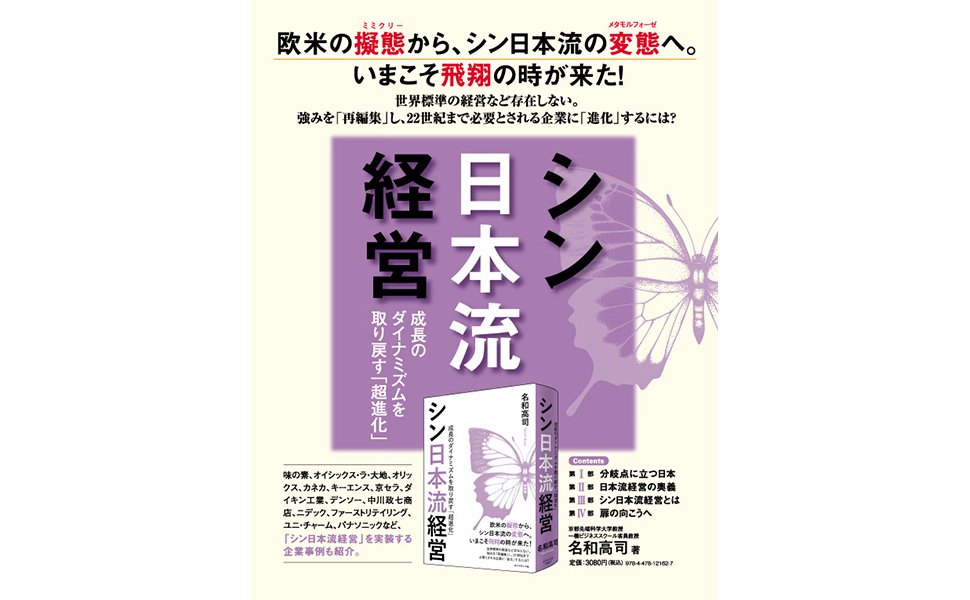幸福度という曖昧な指標に
どこまで意味があるのか
これをどう評価すればいいのか。だから日本はダメなのだと読むのか、それとも、これから改善の余地が大きいと考えるのか。そもそも幸福度が低いのは、期待値が高いことの裏返しでもあるはず。逆に幸福度が高いのは、単に自己満足度が高いだけにすぎないのではないか。さらに言えば、幸福だと感じることが本当に幸福な状態なのだろうか。幸福度という曖昧な指標をうんぬんすること自体、どこまで意味があるのだろうか。
幸福は探し求めるほど手に入らない。メーテルリンクの童話ではないが、夢から覚めてみると、幸せの青い鳥は意外にも自分の鳥かごの中にいたりする。もっとも、それが青い鳥にとって幸せであるとは限らない。物語の最後には、青い鳥は遠くへ飛び立ってしまうのだ。
ウェルビーイングや幸福を標榜する人々の声をよく聴いてみると、その定義はまちまち。もっと言えば、あまり深く考えていないというのが実態だろう。「幸せ」ということに目くじらを立てる人はまずいない。不幸になりたいなどと、本気で思っている人もいないだろう。だったら、定義うんぬんなどという硬いことにこだわらず、とりあえず幸福を未来の旗頭に掲げようではないか。一人ひとりが自分の幸福を実現する社会、ということでいいのではないかと思えてくる。
究極の幸福などという状態は、定義しようがない。だとすれば、少なくともウェルビーイングという「静的な状態」を指す言葉は不適切だろう。筆者は、どうせなら「Well」ではなく「Better」という比較級、「Being」ではなく「Becoming」という動詞に変えることを提唱している。「Better-becoming(ベタービカミング)」、終わりのない旅といったところか。求道精神に近いともいえるであろう。
そう考えると、本格的にウェルビーイングを志向する企業は、実は正しい意味での成長企業であることに気づかされる。