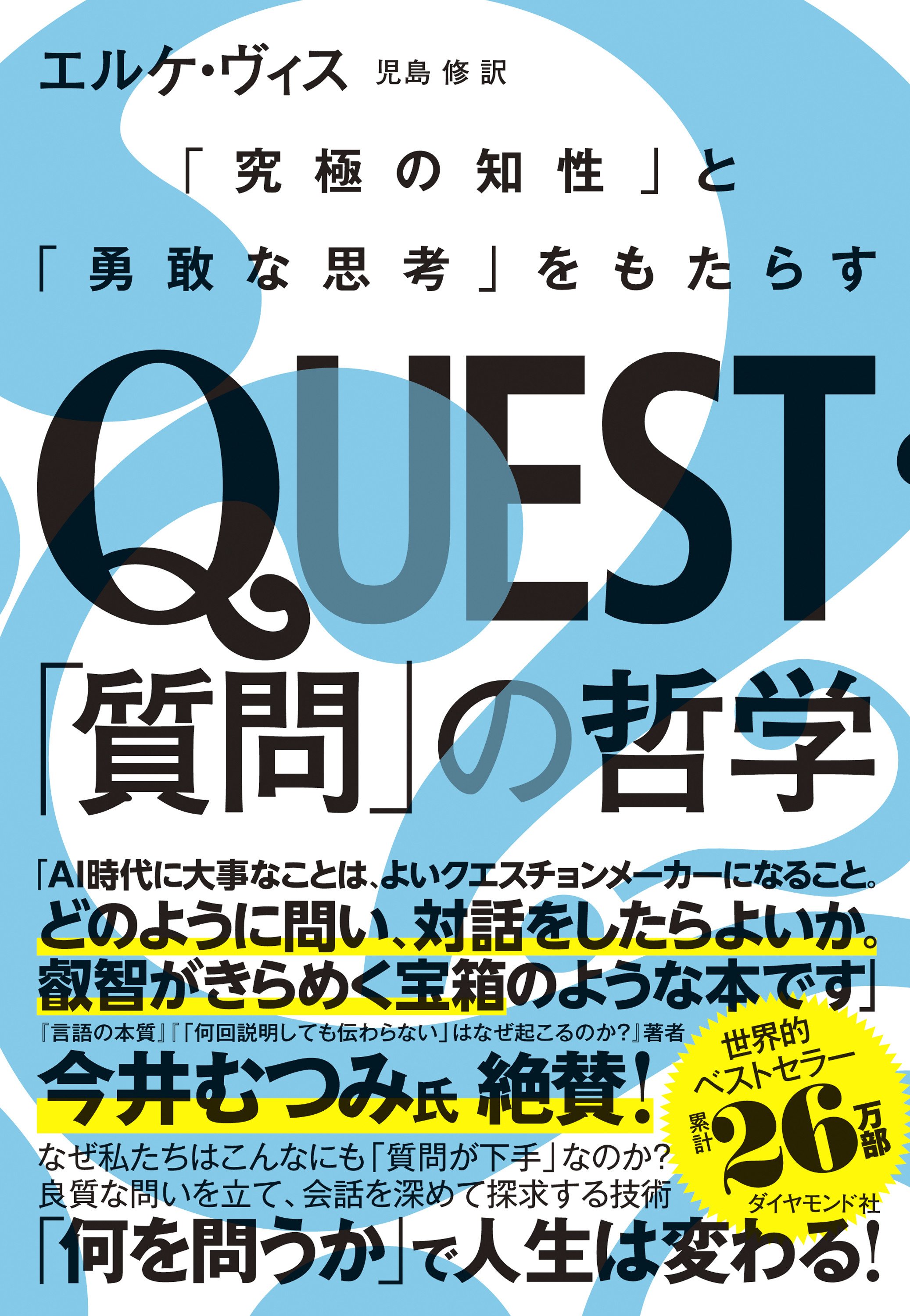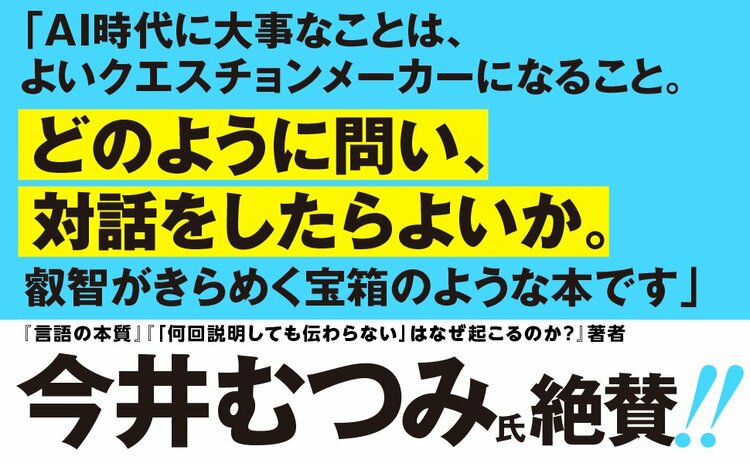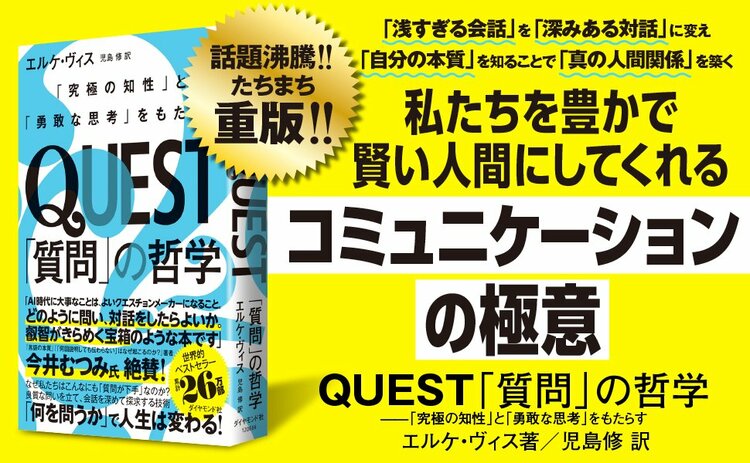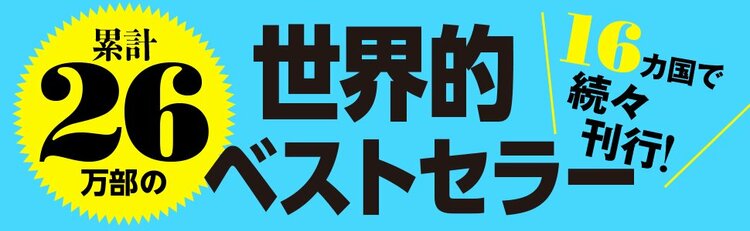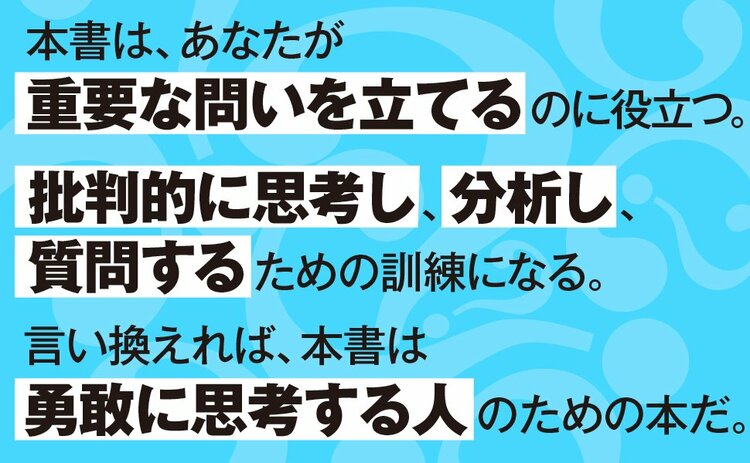「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「質問」と「答え」がつながっているか確認する
自分の質問に相手がきちんと答えているかどうかを確認するための一番簡単な方法は、会話の中身を一時的に脇に置き、質問と答えの構造に注目することだ。
イエス/ノー形式の質問は、実際にイエス/ノーの答えを引き出しているか?
相手に2つの選択肢を与えたとき、実際にどちらかが選ばれているか、それとも漠然とした関連性のある話が始まっているか?
「何時ですか?」と尋ねたら、相手は実際に時間を教えてくれたか、それともまったく違う話をしたか?
尋ねたもの以外の答えが返ってきていたら、会話の軌道を修正しなければならない。
通常は、同じ質問を繰り返すだけで十分だ。
相手が質問に正しく答えていないことを上から目線で指摘するよりも効果がある。
例として、先日私がアムステルダムの路面電車の車内で耳にした会話を紹介しよう。
A「これからお寿司でも食べに行かない?(イエス/ノー形式の質問)」
B「そういえば、この前、お寿司を食べに行ったんだ。とにかくたいへんだったよ。混雑してて、店の対応も悪く、注文したものをもってくるたびに何かが足りないんだ。ウェイターはずっと大声で叫びながら走りまわってたよ」
ここでは、Aが「これから寿司を食べにいくかどうか」とクローズド・クエスチョンで尋ねているのに、Bは最近の寿司屋での体験談を始めてしまう。
会話が一致していないのは明らかだ。
話題が当事者にとって身近で、直接的な影響が大きい場合、事態はさらに厄介になる。
利害が絡むと、人は難しい質問を避けようとしたり、答えがわからないことを認めたがらなかったりするからだ。
例を見てみよう。
タリクとアンはサムの両親だ。
サムは最近、友人のピーターと夜に外出し、薬物に手を出してトラブルを起こしてしまった。
アン「サムに、ピーターと一緒に外出しないように言うべきかしら?」
タリク「ピーターはいい子だと思う。でも、この前の夜の一件については心配だね。行動にかなり問題があったように思う……」
アンはイエスかノーかの質問をしているのに、タリクは自分の考えを話している。
一応会話は成立しているが、それは表面的なものだ。
タリクの答えは曖昧で、結局イエスなのかノーなのかがわからない。
このような場合、まず質問にイエスかノーで答えてから、自分の意見や懸念事項を話すといい。
そうすることで、問題を深く考えられるようになるし、次の質問もしやすくなる。
最初にイエスかノーを答えて自分の立場をはっきりさせるのは簡単ではないし、自分の考えが相手の目にさらされるような落ち着かない気持ちにもなるが、会話は明確になる。
例を見てみよう。
アン「サムに、ピーターと一緒に外出しないように言うべきかしら?」
タリク「うん、そうすべきだと思う」
アン「なぜそう思うの?」
タリク「前回トラブルを起こしたからさ。ピーターはいい子なんだけど、サムに悪い影響を与えている面もある。しばらく、例えば3カ月くらい、一緒に外出するのは禁止すべきだろうね。どう思う?」
今回はタリクの立場が明確になり、彼がそのことについてどう考えているのかもはっきりと示されている。
彼の答えとアンの質問は、組み合わさっている。
(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)