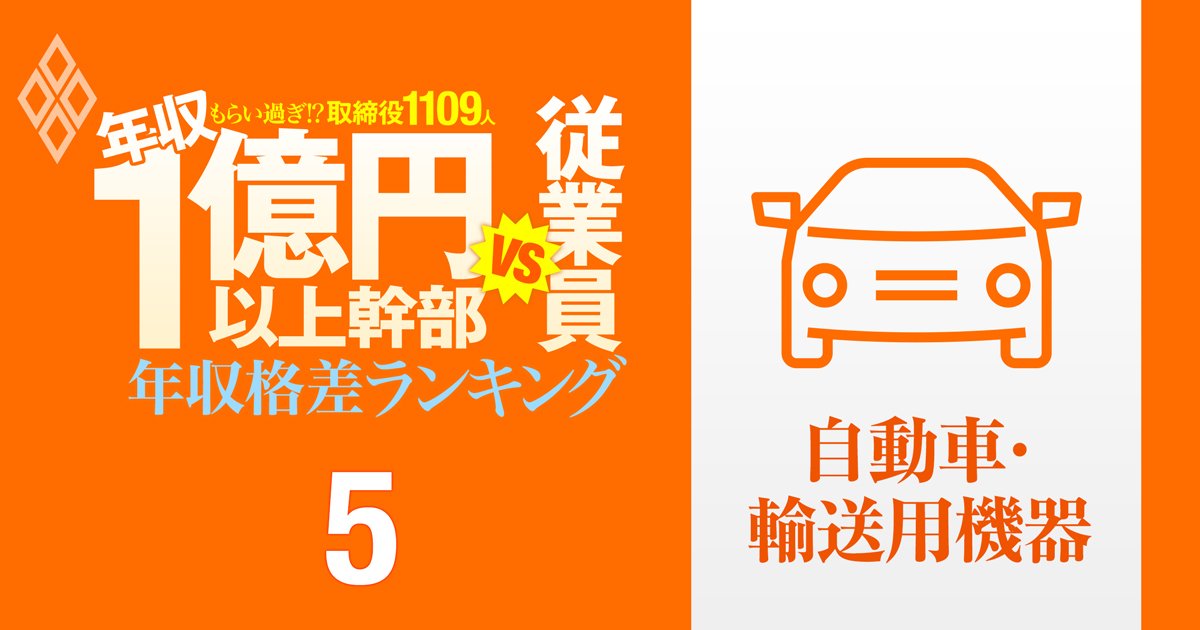「タスク」or「人間関係」稲盛氏はどっち?
非常に好ましい状況では、すでにチームはまとまっており、リーダーはタスク達成に集中すればよい。非常に好ましくない状況、例えば混乱した危機的状況では、リーダーが強い指示で方向性を示し、タスク遂行を強力に推し進めることが求められる。
一方、状況のコントロールのしやすさが「中間的」な場合、つまり、リーダーとメンバーの関係は良いが仕事内容が曖昧であるとか、仕事内容は明確だがリーダーの権限が弱いといった状況では、「人間関係指向型」のリーダーがより有効である。
このような状況では、リーダーがメンバーとの良好な関係を築き、信頼を得て、協力を引き出すことで、状況の不確かさや権限の不足を補う必要があるとされた。
稲盛氏のリーダーシップをコンティンジェンシー理論に照らし合わせてみよう。
稲盛氏のスタイルは、高い目標設定、徹底した採算管理、会議での厳しい要求などから、明らかに「タスク指向型」の特性が強い。もちろん深い人間愛を持ち、「全従業員の物心両面の幸福」を追求したが、仕事の成果に対する妥協のなさ、目標達成への執念は、タスク指向型の特徴を色濃く示している。
稲盛氏がリーダーシップを発揮した局面を考えると、多くの場合、フィードラー理論がタスク指向型リーダーに有利とする状況に合致する。京セラ創業期は、資源も実績もない中で未知の分野に挑む「非常にコントロールしにくい」状況であった。
会社が成長し組織が確立すると、リーダーとしての権限は強固になり、タスクも明確化されて「非常にコントロールしやすい」状況へと変化した。そしてJAL再建は、まさに組織存亡の危機であり、極めて「コントロールしにくい」状況であった。
フィードラー理論に基づけば、これらの状況下で稲盛氏のタスク指向型のリーダーシップが有効性を発揮したのは、理論的な裏付けがあると言える。
しかし、稲盛氏の経営を単なる状況適合の結果と見るのは早計である。