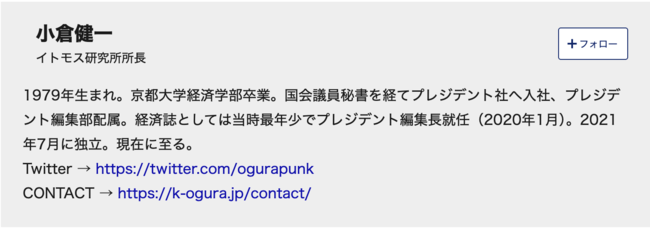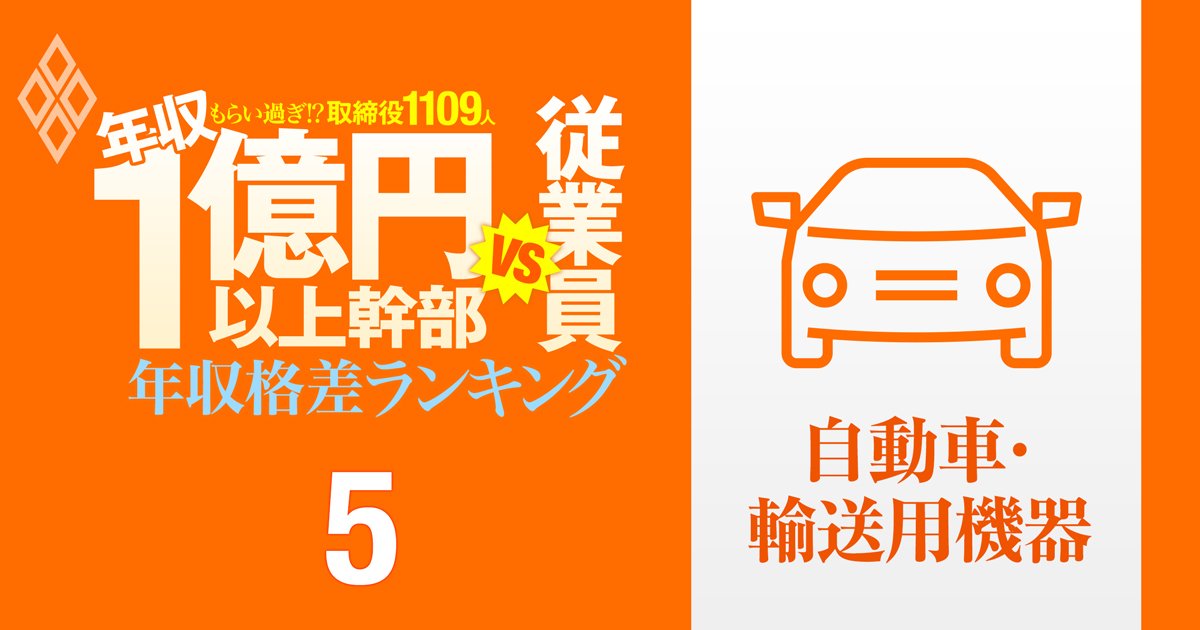「人間は変わらない」vs「人間は変われる」
 Photo:EPA=JIJI
Photo:EPA=JIJI
稲盛氏は、フィードラーが「人間関係指向型」が有利と考える「中間的な状況」においても、安易に人間関係に流れることを良しとしなかっただろう。
むしろ、そのような状況においてこそ、リーダーが自らの哲学を明確に示し、組織全体のベクトルを合わせ、状況をよりコントロールしやすい方向へと積極的に変革していく努力を重視した。
稲盛氏は、単に状況に適応するのではなく、状況自体を自らの意志と努力で創り変えようとしたリーダーであった。つまり、現場に危機感を持たせ、高い目標を掲げることで、成果が出やすい「タスク指向型」へと組織を変えていったのだ。
稲盛氏は「経営とはトップの意志である」と断言する。目標を達成するためには、「潜在意識に透徹するほどの強く持続した願望」が必要であり、「誰にも負けない努力」を自らが率先して行うことが不可欠だと説く。
この強烈な意志と努力こそが、状況の好意性を高め、組織を目標達成へと導く原動力となる。フィードラーは人間は変われないと考え、状況に相応しいタイプのリーダーを配置することを考えたが、一方で稲盛氏は「人間は努力で変わりうる」と考えたのである。
おそらく多くのビジネスリーダーは、フィードラーのいう「中間的な状況」を任されることが多いだろう。しかし、そこからどうやって全員を仕事に集中させ、成果を求める組織へと変貌させるのか。稲盛哲学の本質がそこにある。