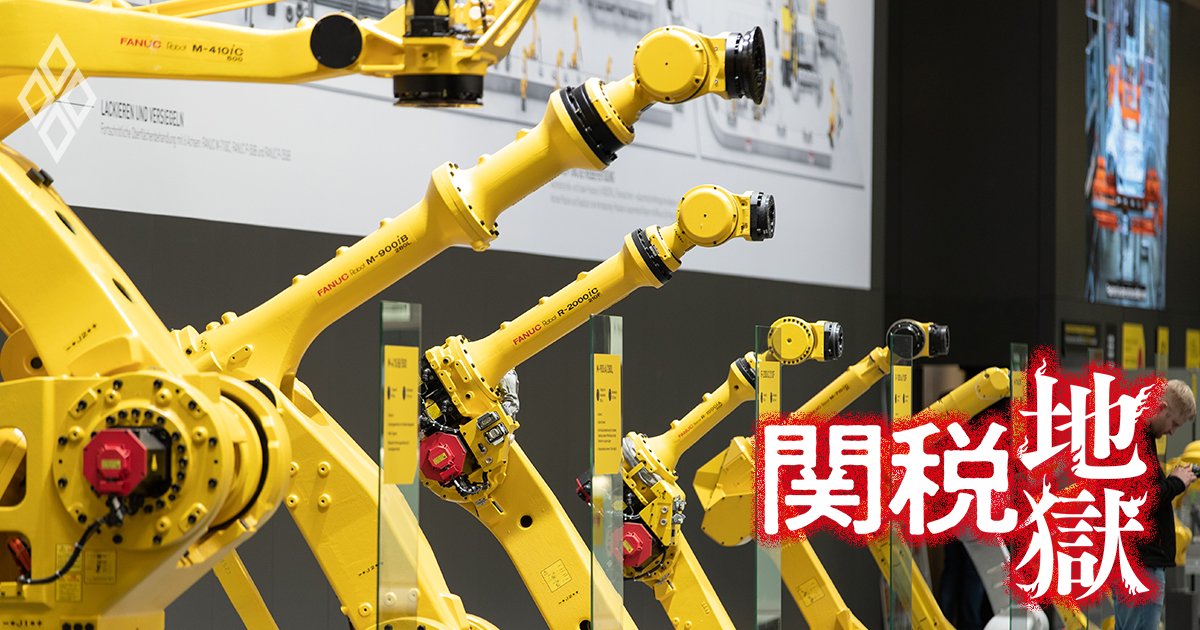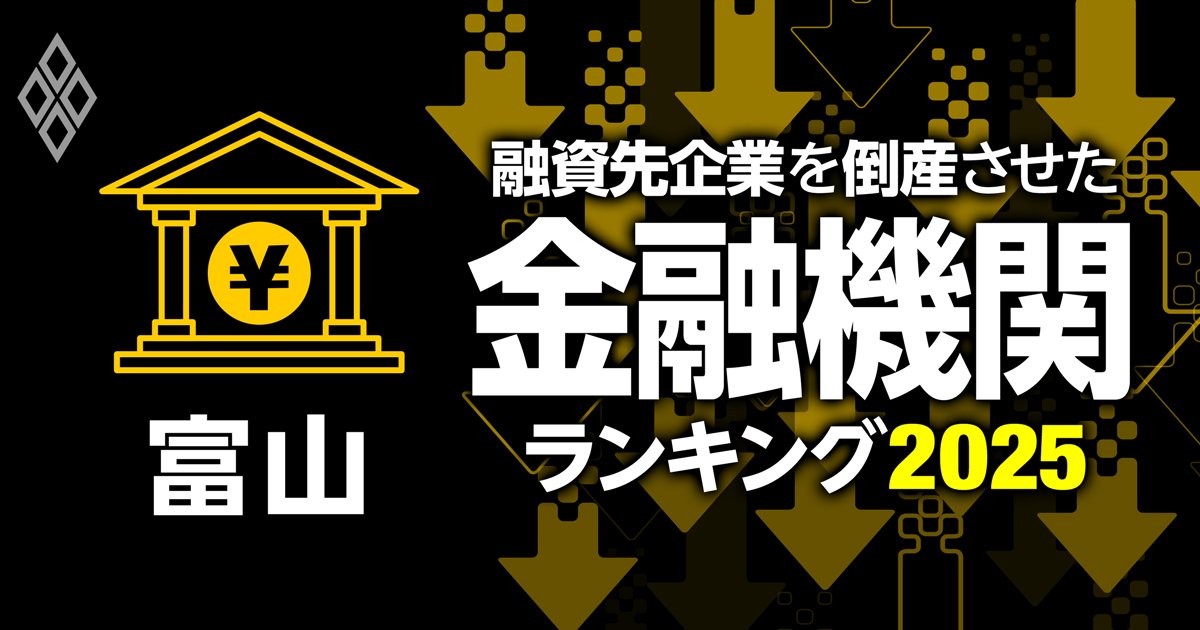2024年度以降の3年間で
約2400社の100億円企業が誕生か?
2023年度時点で「100億企業」ではないものの、同期以前3期の売上高伸び率(平均)を元に、2024年度以降3期以内に「100億企業」となる可能性がある企業『NEXT 100億企業』を抽出すると、国内企業のうち2398社が該当していることが判明した。
具体的には、2024年度に610社、2025年度に816社、2026年度に972社、新たに「100億企業」となるポテンシャルを秘めている。『NEXT 100億企業』のうち、業種別で最も多いのは「卸売業」の725社。次いで「製造業」の592社、「サービス業」の407社となった。
『NEXT 100億企業』を都道府県別に見ると、「東京都」「大阪府」「愛知県」「神奈川県」の大都市圏では、3年間でそれぞれ100社以上の「100億企業」の誕生が見込まれる。「福岡県」(88社)や「北海道」(71社)などでも、大都市圏に迫る数が「100億企業」となることが期待される。
「売上高100億円」に向けたハードルや到達までのアプローチは、業種や地域によって大きく異なる。たとえば「製造業」の「100億企業」出現率は2.57%と相対的に高く、全業種平均の2倍を超えるが、到達に要する平均年数は55.7年にのぼり、「不動産業」や「サービス業」と比べて長い時間がかかる。また、「100億企業」に成長した企業の経営者の年齢は50歳代以下の比率が高くなる傾向もみられた。
これらを踏まえると、中小企業全体への画一的な政策アプローチでは支援効果が発揮できない可能性がある。今回打ち出された政策を軌道に乗せるためには、業種や地域、ビジネスモデル、経営者の能力など、多様な企業形態や成長過程(フェーズ)にあわせたきめ細かなサポートが求められるだろう。
今回の「100億企業」政策の根底には、地域経済やサプライチェーンの振興がある。日本のさまざまな地域に新たな「100億企業」(=成長企業)が数多く生まれてくれば、その事業力を生かして収益確保が進み地域経済の活性化にもつながるだろう。
また、M&Aによる事業領域の拡大も成長過程における有効な選択肢となる。事業再生局面にある中小企業のロールアップ(集約化・統合)を通じて、産業の保護や雇用の維持、さらには賃上げ効果も期待できる。国内に推計22万8000社存在する「ゾンビ企業」の出口戦略としても位置付けられるなど、トランプショックに直面する国内企業の新陳代謝が、今後さらに進む可能性もありそうだ。