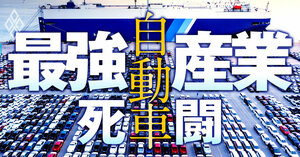Photo:Chip Somodevilla/gettyimages
Photo:Chip Somodevilla/gettyimages
間違った政策が崩す米国への信認
米国債、価格下落に続き「格下げ」
各国に高率の関税を賦課するトランプ関税政策が、国際貿易を混乱させ世界経済の不透明感を一気に強めているが、これはアメリカの経済や財政の持続性に対しても疑問を生んでいる。
相互関税発動などを機に、アメリカ国債が下落(長期金利上昇)したのに続き、5月16日には、格付け会社ムーディーズ・レーティングスが、国債の格付けを最上位の「Aaa」から「Aa1」に引き下げた。
直接の理由は、巨額財政赤字と金利コスト増大だが、これも市場関係者の間でトランプ政策などによるドルやアメリカ国債への信認が低下していることを示すものだ。
トランプ経済政策の基本的な考えは、「対外赤字(経常収支あるいは貿易収支における赤字)は、アメリカにとっての損失である」ということだ。
そこで、貿易赤字を縮小させるために、外国からの輸入に関税をかけて輸入を減らし(できればゼロとし)、その分を国内で生産しようとする。
しかし、この考えは間違いだ。
事態は全く逆であって、サービス収支なども含めて対外赤字を継続できているのは、国民が国内で生産する以上に消費や住宅投資などができることで、アメリカにとって望ましいことなのだ。
トランプ政策は、この「繁栄の基本メカニズム」を崩そうという愚策といってよい。