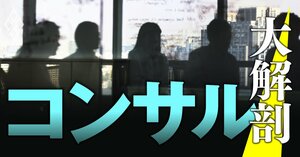写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
人事、採用、マネジメントをはじめ、人間関係の困りごとを解決する連載第10回は、「仕事ができる人」になるためにできることを解き明かす。自分でも鍛えることができる「コアスキル」という概念とはなにか。また、仕事ができる人に共通する「当たり前水準」と、その向上の方法について解説する。(人材研究所ディレクター 安藤 健、構成/ライター 奥田由意)
「あんなに優秀じゃないから、敵わない」?
実は逆転できる可能性があった!
「仕事のできる人」の明確な定義は難しいものですが、私は実務経験から、時代や仕事を超えた普遍的な「コアスキル」があると考えています。前回は仕事ができる人には、
1. 自己認知
2. 当たり前水準の高さ
3. 意味づけ力
4. 自己効力感
という4つのコアスキルがあるとお話しし、1の自己認知について詳しく解説しました。自己認知とは自分のことを正確に理解する能力で、フィードバックをもらったり、ゲームの視点切り替えのように、常に自分を後ろから見るカメラがあることを想像して、自分の行動を振り返ったりすることで鍛えられます。
今回は仕事ができる人のコアスキルとして、共通な要素の2つ目、「当たり前水準の高さ」について説明します。当たり前水準とは、「どこまでやったら自分として頑張ったと言えるのか」という感覚のことです。
同じ能力の人でも、成長の仕方や伸びに大きな差が生まれるのはなぜか。あるいは、当初能力が低いと思われていた人が、優秀だと言われていた人を追い越すのはなぜか。それは当たり前水準の違いによるところが大きいのです。
例えば2人の社員がいるとします。Aさんは元々の能力はあまり高くなく、手際も良くないのですが、「自分はまだまだだ」(当たり前水準が高い)と常に考える性格です。一方のBさんは元々能力が高く、器用で、何をやらせても早く理解し習得できます。ただ、「この程度のことならすぐできる、周りからも評価されているし、このままでいい」(当たり前水準が低い)と考えます。