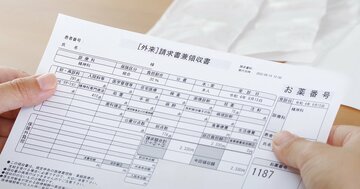写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「将来の医療費への備え」というと、民間の医療保険が思い浮かぶ人がいるかもしれない。しかし、その前に自分の「健康保険」についてよく知っておいてほしい。医療にかかるお金は健康保険によって変わってくるのだ。今回の参院選でも注目されている医療費について、改めてポイントを押さえておこう。(ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役 深田晶恵)
なにかと話題の「高額療養費制度」
これからどうなる?
今年3月、石破茂首相が「高額療養費制度の負担限度額引き上げを見送り」したことは記憶に新しい。
医療費には一定の負担限度額が設けられており、病院で3割などの一定割合を支払ったとしても、超過分は払い戻しが受けられる。これが「高額療養費制度」。限度額以上の負担がないのはとてもありがたく、頼りになる制度だ。
この高額療養費の限度額を2025年8月から段階的に引き上げる改正案が昨秋決まった。改正が発表されると、多数の反対意見が出てネットでは大炎上。さらに長期にわたる治療が必要ながんなどの患者団体から「事前に意見を求められていない」と不満と批判の声が続出し、引き上げの全面凍結を求めた意見表明がされた。
世論と患者団体の批判の結果、異例の「見直し案実施の見送り」が決まったのである。
実はこの春、首相が表明したのは「見送り」であり、改正の「凍結」ではない。秋までに方針を再検討するとしている。一方、立憲民主党は今回の参院選の公約で「高額療養費の引き上げを行わない」と表明。
このように、なにかと話題の高額療養費制度だが、健康なときには恩恵を受けることがないせいか、空気のような存在でそのメリットをしっかり認識している人は多くない。秋以降の見直し議論に向けて、改めて仕組みをしっかり理解しておこう。
絶対に知っておいてほしいのは、病気になったときの医療費負担がみんな同じではないこと。「医療にかかるお金」の違いは、2つの要素がある。
1つ目の「所得によって限度額は異なること」はみなさんご存じだろう。ただ、それだけではない。
実は、加入の「健康保険」によっても医療にかかるお金は全く異なる。これが2つ目の要素。このことは多くの人がご存じない。筆者が講師を務めるセミナーで参加者に聞いてみると、健康保険により医療費負担が異なることを知っている人は100人いたら、3人程度。認知度はかなり低い。
自分が病気をしたときの「限度額」を知ることはとても重要。さっそく、制度の仕組みと合わせてみていこう。