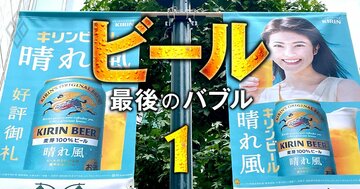今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1967年4月24日号に掲載された記事『白兵戦の様相を呈してきた“ビール戦争”』を紹介する。67年4月、宝酒造がビール事業からの完全撤退を決め、“ビール戦争”は新局面に突入していた。記事では、独走態勢を固めるキリンビールに対するサッポロビールとアサヒビールの巻き返し策に焦点を当てているほか、宝と同じ後発組のサントリーが前年比5割増の販売を目指し、この年に投入した二つの“切り札”について紹介している。サントリーの反転攻勢策とは。(ダイヤモンド編集部)
宝酒造がビール事業からついに撤退
宝のシェア巡り大手4社の白兵戦に
「ビール部門の分離については、昨年(編集部注:1966年)の秋から検討をしていた。覚悟はできていたが……。考えてみると、不思識な巡り合わせだ。分離が決まったのが、4月8日。その10年前の同じ日、東京の問屋さんを木崎工場(群馬県)にご招待して、出荷記念パーティーを開いた。社長が留守だったので、私が皆さんの前であいさつを述べた。それが昨日のことのように思えてならない……」
こうしみじみと語るのは、宝酒造の柿田三郎専務である。さる4月8日、ついに、宝の京都ビール工場の譲渡が決まった。買い主は麒麟麦酒、買収価格は34億円。ここに宝は、ビール事業から完全に手を引くことになった。この25日には、正式調印が行われる予定である。
宝は、ビール部門で年7億円以上に上る赤字を出してきた。ビール部門の分離で、多額の赤字負担から解放される。“苦節10年”の努力は実らなかったが、とにかく大きな赤字部門がなくなる。一方、麒麟は操業度が100%を超え、今年中にも新工場建設の具体化に迫られていた。監督官庁である大蔵省の言葉を借りるまでもなく、今回の買収は、業界の“設備調整”の上からも大きな意義がある。
しかし問題は、そう簡単に片付けられるものではない。一つは、ビール部門分離後の宝の動向である。赤字部門の解消で果たして懸念の復配が実現するかどうか。もう一つは、宝の脱落でビール業界がどう変わっているかである。
米国や欧州では、毎年、数多くのビール会社が集中、合併を繰り返している。多数競争から寡占化へ、これがビール業界の趨勢であるが、これによって値引き、乱売が減少し、業界の正常な発展が望めるならよい。しかし“ビール戦争”の実態は、そう簡単なものではない。
宝脱落後、業界は早くも慌ただしい空気に包まれている。簡単に言えば、宝のシェア、わずか1.5%の奪い合いに各社がしのぎを削っているのだ。宝がビール業界に進出を図ったのは、その成長力に着目したためである。焼酎や合成酒、みりんでは“総合酒造会社”としての発展は期待できない。その夢をビール事業に託したわけだ。
その夢も、今回の分離で泡と消えた。ビール部門の赤字が解消し、そろばんの上ではプラスになるが会社の成長、発展という大きな目的からは後退する。宝はここで、ビールに代わる成商品の育成という新しい課題を抱えたことになる。
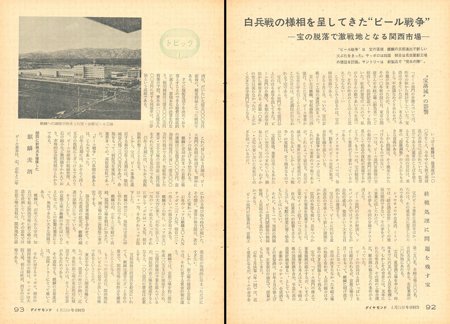 「ダイヤモンド」1967年4月24日号
「ダイヤモンド」1967年4月24日号
信用の失墜も痛い。長年培ってきた事業を放棄することは、企業のイメージ低下につながる。株主、従業員への影響もさることながら、実際の営業に響く懸念もないとはいえない。それに、もう一つ。当面の問題として、ビール部門閉鎖後の戦線整理、人員縮小をどう進めていくかである。ビール部門の従業員は、京都工場250人、木崎工場300人、合計550人である。全従業員の20%強に当たる。
宝は、蒸留酒工場を中心に、昨年までに650人の人員を整理した。しかしその背景には、5年にわたる年月と、その間の工場合理化、組合側の協力などの条件がそろっていた。ビールの出荷は6月いっぱいまでは続けられるが、京都工場は7月1日をもって、麒麟に明け渡すことになっている。売却が決まらなかった木崎工場の処置と併せ、人員の縮小は今後の大きな問題として残る。
宝では、「ビール部門の廃止で事業規模は縮小するが、いまのところ減資する考えはない。木崎工場の活用計画を含め、早急に次の発展計画を練る」としている。