また、一方では働きぶりを厳正に評価した上で降格も含めて運用できる制度にするなど、多くの企業がミドルシニアの多様な働き方に適応した新たな取り組みについて、試行錯誤しながら導入を検討している。また、短い時間でも働けるような勤務体系を用意するなど、個々人の選択肢を増やすこともひとつの潮流になっている。
意欲や能力がある人には、年齢にかかわらず高い報酬を支払う。逆にそうでない人には、それ相応の報酬を設定する。
高い報酬と引き換えに
高ストレスな働き方が続く
こう言うと高い報酬が良いと思うかもしれないが、そのためには現役時代と変わらぬ高い成果を創出する必要があるということでもあり、公正な評価が行われるということでもある。
そう考えれば、そうしたストレスの高い働き方を続けるということは万人にとって望ましいものとはならないだろう。企業としては、定年後の働き方や処遇のバリエーションを増やし、従業員側にはキャリアの自己選択を求める。同一労働・同一賃金の考え方を貫く中で画一的な制度を見直す方向性が、今後の人事制度の大きな潮流になっていくと考えられる。
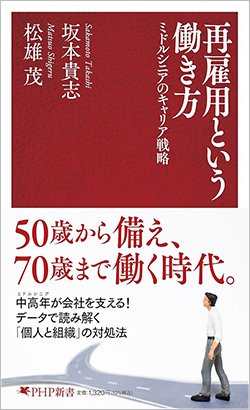 『再雇用という働き方 ミドルシニアのキャリア戦略』(坂本貴志・松雄 茂、PHP研究所)
『再雇用という働き方 ミドルシニアのキャリア戦略』(坂本貴志・松雄 茂、PHP研究所)
たとえば三菱UFJ信託銀行は再雇用になった行員の給与を最大で4割上げるが、これは全員が対象ではない。また、今まで再雇用では週4日の勤務を前提にしていたものをフルタイムに拡大し、希望者や本当に働いてもらいたい人には現役世代と同じ働き方を適用している。
カルビーは、現場の社員の中で専門性が特に高い人を選び、65歳以上になっても雇用し続けるシニアマイスター制度を導入している。ここで選ばれるためにはそれ相応の努力が必要になるだろう。シニアマイスター制度を満たす優秀な人材は、おそらく再雇用者の中でもごく一部ということになるとみられる。
サントリーも同様である。年齢で区切り、役職や収入が一律で落ちる60歳の壁をなくし、優秀な人材に報いる制度に改革している。
ここで挙げた多くの企業では、すべて一律だった年齢による給与の減額をやめ、実力次第では、現役世代と同じ報酬を支払う方向に変わりつつある。企業人事がミドルシニア社員活躍のために目指すべき方向性は、やはりここにあると考えられるのである。







