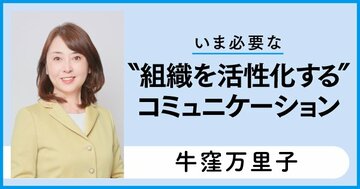渋幕の「自調自考」の精神に基づいた学びとは……
そうした学校をつくり上げているのが、「自調自考」という渋幕の教育目標である。「自調自考」は、自己表現的な「自ら調べ、自ら考える」ことと、自己理解的な「自らを調べ、自らを考える」の両方の意味が込められている。外に向かうベクトルと内に向かうベクトルで、一見、逆方向に見えるが、それが接続していくのが渋幕の学びである。
つまり、自己理解と自己表現は両輪であることを教育目標が伝えている。そして、この教育目標が、授業、行事、部活動、生活という、あらゆる学校活動の土台になっている。
昨今、世間一般的に、社会人のアウトプット力が重視されているように私は感じている。しかし、自己表現する力は「自分が何を伝えたいのか」「何を変えたいと思っているのか」「何に幸福を感じるのか」といった自己理解がなければカタチだけのものとなる。カタチだけ整ったプレゼンテーションが虚しいのは多くの方が感じていることだろう。
世界に広がる、自己の感情に目を向ける教育
実は、こうした教育を実践しているのは渋幕だけではない。全国の学校において、少しずつであるが、自己理解と自己表現の両輪の学びは広がりつつある。
例えば、SEL(ソーシャルエモーショナルラーニング/社会性と情動の学び)という教育アプローチは、ソーシャルスキルとエモーショナルスキルを高めていく。
ソーシャルスキルは、「社会人基礎力」と呼ばれてきた力と重なり、他者とつながるコミュニケーション能力や自己管理力などを指すものだ。その必要性はビジネスパーソンであれば理解しやすいのではないだろうか。
エモーショナルスキルは感情に目を向けた学びだ。「自分はいま、何を考えているのか」「他者はどんな心の状況にあるのか」などを捉え、それと付き合っていく力を養う。SELという言葉こそ使っていないが、渋幕の実践は自身の感情に目を向けて、どうしたいのかを捉え、自己決定することを非常に重視している。
SELの学びは2015年にアメリカをはじめとする世界各地に広がり、教育移住で人気を博してきたシンガポールで全校導入されている(*2)。そして、日本においても、急速に導入が拡大しており、複数の自治体で取り組みがスタートしたり、有名校が活動を始めたりしている。
*2 参考書籍=下向依梨著『世界標準のSEL教育のすすめ 「切りひらく力」を育む親子習慣』(小学館/2024年7月刊)
なぜ、このSELの学びが重視されるようになってきたかといえば、自律において、自己理解や自己認知が不可欠だという実感が広がりつつあるからではないかと私は考えている。
例えば、就職活動の際に「自分がどんなキャリアを歩みたいかわからない」「何が好きかわからない」という若者は少なくない。「自分が何をしたいのか」という小さな自己理解と自己決定を重ねてこなければ、就職という大きな自己決定をすることはかなり難しい。進学、就職、転職、結婚など、あらゆるフェーズにおいて、自己理解と自己決定する力が求められる。
自分の人生を自分で決めていくために、つまり、自律型の人材になっていくための土台として、自己理解の力が求められているのだ。