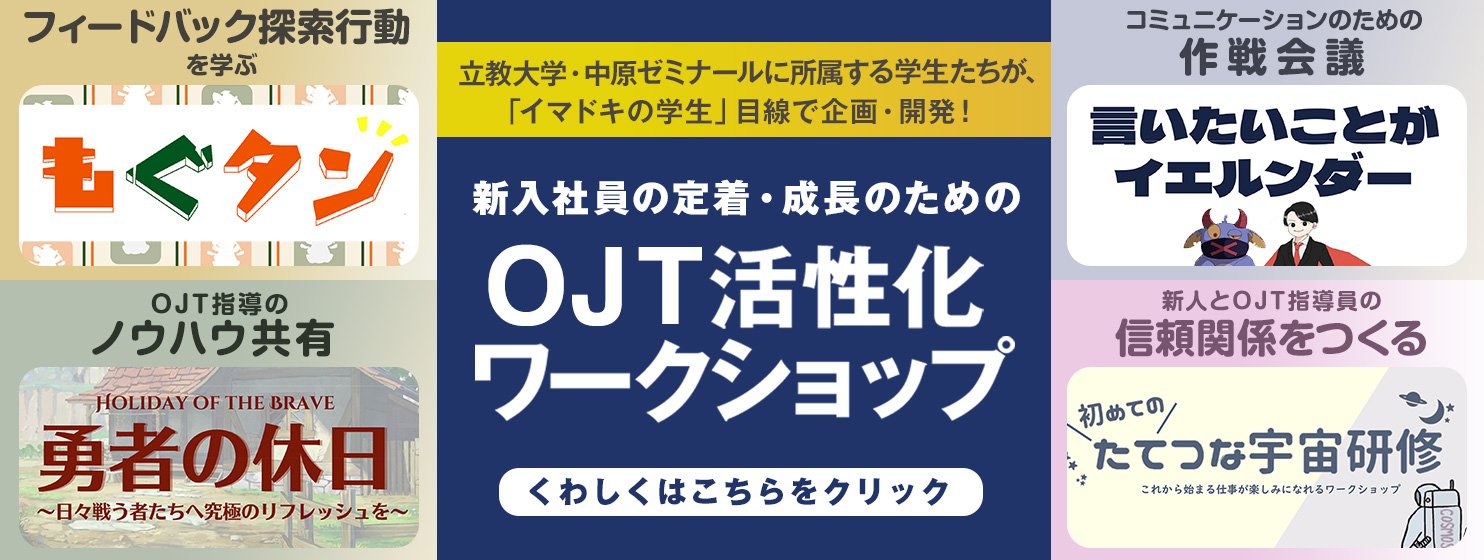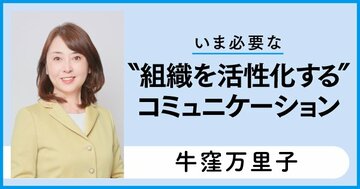新たな価値を生む“自律型人材”を育てていくこと
本来、人の学びは“線”で表現されるべきなのに、学校教育と企業教育は地続きで考えられることが少なかった。まずは、企業が学校教育を理解することが、その溝を埋める第一歩になると考える。
また、“接続”といったときに注意すべきことがある。「企業で扱いやすい人を育ててほしい」という期待を伝えるだけでは、新たな価値を生む人材は育たないということだ。重要なことは、ビジネスの現場と学校の現場が一緒になって対話しながら、新たな人材像を描いていくことではないか。
残念ながら、旧態依然の学校もまだあるが、少しずつ、自分を理解し、自己決定の場面を増やしていく活動が広がりつつあるのは事実だ。2035年にはこうした教育が浸透した子どもたちが企業に入社すると予測される。つまり、入社してくる若手は、自分の心に目を向けて、語り、行動できる人材だ。若者たちは、キャリアに関しても、自分の考える社会的意義を体現したいと考えるようになる。
新卒者にどうしたら企業は選ばれることができ、彼らの力を伸ばせるのか。少なくとも、若手の自己決定の場面を増やしていくことは重要だろう。女性管理職の割合だけでなく、管理職や経営層の年齢のダイバーシティもいっそう見直していく必要がある。そして、企業のパーパスと個人のパーパスの重なり合いを意識した採用・育成も重要だと感じる。「自社が何のために社会に存在しているのか」が明確化され、それが事業や育成など隅々にまで浸透していることで、共鳴する入社者が増えていくだろう。
また、現状、社内で自己理解を促す場面はどれくらいあるだろうか。
渋幕の校舎の1階。多くの生徒が行き交う場所に、「挑戦は自己認知の具現」という言葉が掲げられている。若者や子どもたちに「挑戦しろ」「チャレンジが大事だ」というが、その手前にある自己認知をする機会を設けているだろうか? 自己認知がなければ、挑戦は生まれない。
学校教育と企業教育を接続させて、ともに自律型人材を育てていく――私は、その橋渡し役として、今後も多くの学校と人材育成の現場の方々のお話に耳を傾けていきたい。