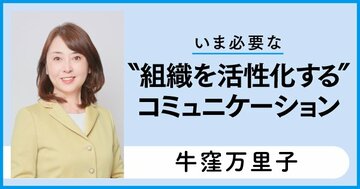企業の嘆きと探究学習で起きている問題は地続き
もう少し、学校教育の大きなうねりを紹介する。それは「探究学習」である。小学校から高校まで探究学習を実践しているので、すでにご存じの方も多いだろう。高校では「総合的な探究の時間」だけでなく、「古典探究」や「地理探究」などの一般科目にも“探究”が冠されるようになった。
探究学習について、私が最もたくさんの悩みの声をいただくのが、「子どもが問いを立てられない」という問題だ。探究学習では、「課題の設定→情報の収集→整理・分析→まとめ・表現」というサイクルをスパイラルに回していくことになる。「課題の設定=問いを立てる」というスタート地点に立つことができない子が少なからずいる。
「問いを立てる」ということは、「これから、何を探究学習していきたいか」を決めるということだ。だから、先生が「自分の好きなことから探したらいいんだよ」「身の回りの出来事で違和感を覚えたり、課題を感じたりしたことはない?」と促すが、高校生くらいになると「好きなことなんてありません」「別に課題と感じることも……」という反応となる。中には、大人の目を気にして忖度し、「こんな問いを学校で探究学習できるはずがない」と最初から口に出さない子もいる。ここにも、自分の関心に目を向けられない自己理解の壁が立ちはだかっている。
私は子どもたちに問題があるのではないと考えている。生まれた時は「なぜ?なぜ?」を繰り返していた子どもたちの探究心を、社会が削いできてしまった結果ではないかと思う。
そして、この状況は新規事業が生まれない日本、イノベーションが生めない企業の状況と重なってくる。「自分の心の温度が上がることに目を向けられていない」「自分の疑問やモヤモヤから端を発して、調べ、行動して、何かを創り出す動きができない」、あるいは、「企業の組織において、自身の問いに従って探究(新規事業)するような環境が整備されていない」といったことも挙げられるだろう。
「イノベーションが生まれない」という企業の嘆きと、学校の探究学習で起きている問題は地続きなのだ。