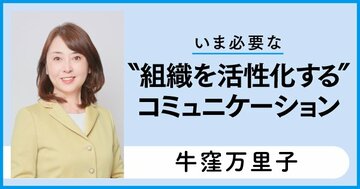自分で必要な学びを自己決定しながら進めていく
当然ながら、「言われたことをしている」だけでは自律型人材は育たない。自分が何をすべきなのかを判断できる力が必要である。
昨今、「子どもに委ねる学び」と呼ばれる取り組みが各校に広がっている。手法でいうと、「自由進度学習」などがそれにあたる。自由進度学習とは、教員が示した目標をもとに、児童・生徒自身が計画を立て、自分のペースで学習を進める手法のことだ。個別化された学びを実現する学習方法として注目されている。
例えば、単元の目標が担当の先生から示されて、その目標に到達するための手法やペースは子どもたちが自分で選択をする。友達同士で話し合いながら進める子もいれば、タブレットでヒントを得ながら学ぶ子、本や教科書を開きながら黙々と進める子などがいる。どこで学ぶかを自由にしているクラスもあり、机に向かって学習する子ももちろんいるが、床に座って解いてもいいし、廊下に出て学んでいる子、(事前に、教員が学校図書館司書に連絡を入れておき)図書室に行く子もいる。教員は自由に学ぶ子どもたちの間を循環して、困っていそうな子には声をかける。
先生の話を黙って聞き、ノートを取る授業が当然と考えてきた大人がこの様子を見たら、「大丈夫?」と不安になるかもしれない。しかし、こうした手法の狙いには、授業についていけない子も、授業が退屈に感じる子もなくしたいという思いがある。授業の中での成長が「0歩」の子をなくしていこうとする学びだ。
こうした学び方が、一般的な公立学校でも行われるようになってきている。
必要なのは、手法の目新しさへの賛否ではなく、「子どもに委ねて」「子どもに自己決定の機会をつくっていく」こと。そして、「一斉授業が悪い」という短絡的な考えではなく、転換すべきは、大人が与えて、大人が主導する教育観だ。