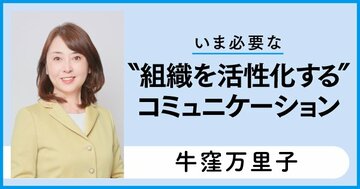「最近の若手社員は何を考えているか、わからない」「自分たちの頃の常識が通用しなくなっている」――そうしたことを口にするビジネスパーソンは少なくない。今後、どういった若者たちが自社に入社してくるのかを予測するためには、現在の子どもたちが受けている学校教育を知ることが重要だ。長らく、学校教育と企業教育は接続されてこなかった。しかし、「自律型人材を育てる」という意味では、学校教育も企業教育も同じ目標を目指しているのではないか――教育ライターの佐藤智さんが、“学校教育の現在”を10年後の企業の状況に接続させて解説する。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
2035年に企業に新卒入社する、現在の中学生たち
現在(2025年)の中学1年生が企業に就職する年は、大学卒業の22歳であれば2035年、大学院修士課程卒業の24歳であれば2037年となる。「約10年後にどのような新人が入社してくるか?」を予測する際に大切なことは、現在の学校教育に目を向けることだと思う。
もちろん、人柄や能力は学校教育だけで形成されるものではなく、持って生まれた資質や家庭環境の影響も大きい。ただ、学校教育を受ける多感な時期に「どのような環境で集団生活を送ったか」「集団の中で何が当たり前とされていたか」は知らぬ間に自身に浸透している。だからこそ、学校教育の状況を知ることで、未来の企業で働く世代を大まかに捉えられるのではないか、と私は考えている。
本稿は、学校の現状を参考にしながら、「若者たちが魅力を感じる企業をどうつくっていくか」「どういった企業教育を構築していくと効果的か」を考える材料にしてほしい。
自分のことを思いきり語る、中学・高校の生徒たち
1000人以上が収容できる大講堂。聴講者がぎっしりいる中で、講師に対して、「はい!」と手を挙げて英語で自己紹介をし、自身が抱いた講演の感想と質問を語る――これは学校取材の一コマ。忘れ難い光景だ。
私はこれまで1000人以上の先生にインタビューをしてきた教育ライターである。取材の中で出合った学校のひとつ――渋谷教育学園幕張中学校・高等学校。通称、渋幕(しぶまく)。東大合格者数が14年連続でトップ10入りし、中学受験でも難関校であることから、いわゆる“進学校”と認知している人も多いだろう。
では、みなさんの思い描く、“進学校”とはどのような学校だろうか? 大量の勉強をこなし、先生の指示をしっかり守り、大人の示す進路を目指す生徒たちがいる学校……そんなイメージかもしれない。
しかし、渋幕では、まったく異なる環境がつくられていた。
私は『渋幕だけが知っている「勉強しなさい」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』(*1)という書籍を書いた。1年半の時間をかけて、先生だけでなく、在校生や卒業生にも話を聞いた。
*1 佐藤智著 『渋幕だけが知っている「勉強しなさい」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』(飛鳥新社/2025年5月刊)
取材で感じたのは、生徒全員が「自分について、とてもたくさん語る」ということである。「みんなと同じです」「普通です」などの言葉は一切ない。一つの質問に対して、中1から高3までの生徒が、「自分は◯◯だと思う。なぜならば〜」と語り出す。面接練習のように型通りの話をしているのではない。自身の原体験や信念を踏まえて、言葉を選ぶ。
この力はどう育っているのか?
渋幕はチャイムが鳴らない、校則はほぼない、研修旅行(修学旅行や遠足)は現地集合・現地解散、進路指導はしない、といった特徴を持つ学校だ。チャイムが鳴らないので授業が終わったことに気づかずに教室の後ろで寝ていて移動教室に遅れたり、研修旅行で寝坊して予定していた新幹線に乗れずに集合時間に間に合わず、一人でタクシーで追いかけたりすることが日常的に起こる。
つまり、生徒たちは規律や管理ではなく、自己決定のもとで行動をしている。