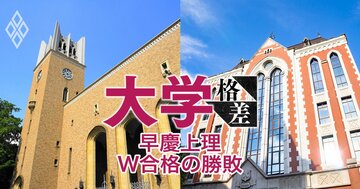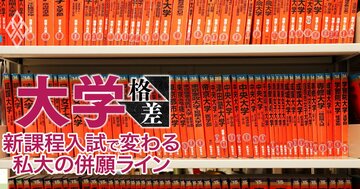Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
早稲田大学の学部生数が減少している。一般入試では数学の試験や大学入学共通テストを必須化して志願者数が減り、内部進学の推薦基準もハードルが上がった。志願者数の減少は入学検定料収入に、学部生数の減少は入学金や授業料などの収入に響く。自ら首を絞めてはいないか――。特集『エスカレーター校 クライシス』(全15回予定)の#7では、学校法人早稲田大学の「裏・成績表」を作成し、偏差値や志願者数など表の情報からは見えない内情に迫った。(ダイヤモンド編集部副編集長 臼井真粧美)
早稲田内部進学の推薦基準に
英語外部試験スコアが入った
早稲田大学に内部進学するルートは二つある。一つは早稲田大と同じ学校法人が運営する付属校、早稲田大学高等学院あるいは早稲田大学本庄高等学院に入ること。どちらも内部推薦枠が100%用意されている。
もう一つが連携先の別法人が運営する系属校ルートで、早稲田実業学校は約100%の内部推薦枠、早稲田中学校・高等学校は約50%、早稲田渋谷シンガポール校は約80%、早稲田摂陵高等学校(2025年4月より早稲田大阪高等学校に名称変更)は約10%、早稲田佐賀中学校・高等学校は約50%の枠をそれぞれ持つ。
内部推薦枠の高い学校に入れば、エスカレーター式で早稲田大に進学する確度が高まる。ただ受験競争に勝って付属校や系属校に入学できたとて、油断はできない。
ほぼ全員が内部進学ルートに乗る早稲田実業では最近、「内部進学のハードルが上がっている」という不安の声が漏れるようになった。早稲田大の政治経済学部、国際教養学部、社会科学部、文学部、文化構想学部の各学部が、TOEFLなどの英語外部試験で一定レベル以上のスコアを取ることを内部推薦の基準に盛り込んだからだ。
早稲田大は21年度の入試改革以降、看板の政治経済学部で数学の試験を必須化したり、大学入学共通テスト必須の学部をどんどん増やしたりして、一般入試のハードルを上げた。こうした姿勢が内部推薦にも及んでいるのだ。
早稲田大の学部生数は減少している。12年度に4万3974人だったのが、24年度に3万8040人まで減った(通信教育課程を除いた人数)。一般入試の志願者数は入試改革後に10万人の大台を割り、減少基調に転換している。見渡せば、名門エスカレーター校であっても、定員割れ続きで大学や付属校の募集を停止するところが相次いでいる。
入学者の学力レベルを強化する早稲田大の試みは、自らの首を絞めることにならないのか――。
次ページでは、早稲田大を擁する学校法人の実力をあぶり出した「裏・成績表」を大公開する。ダイヤモンド編集部が独自に設定した六つの指標で、稼ぎ、教職員の充実度、定員割れの状況などを総合的に評価した通信簿のようなものだ。
果たして、早稲田大には持続的に発展していけるような競争力が備わっているのか。入学志望者が絶えず、OB・OGにとって愛する母校であり続けられるのか。