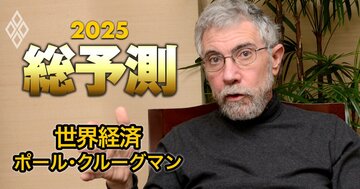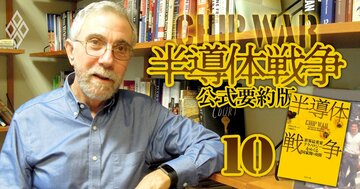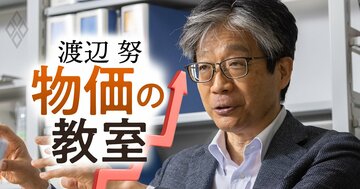2016年に首相官邸で開催された国際金融経済分析会合に出席した米プリンストン大学のポール・クルーグマン名誉教授(左)と筆者 Photo:JIJI
2016年に首相官邸で開催された国際金融経済分析会合に出席した米プリンストン大学のポール・クルーグマン名誉教授(左)と筆者 Photo:JIJI
新政権発足や株価の最高値更新など、大きな経済イベントが起こるたびに、専門家によるさまざまな見通しが発表される。前日本銀行総裁の黒田東彦氏が執筆するダイヤモンド・オンラインの連載『黒田東彦の世界と経済の読み解き方』の今回のテーマは、「エコノミストの悲観バイアス」。黒田氏が評価する4人の経済学者と、日本のエコノミストの悲観バイアスがもたらす弊害とは。
悲観的な見通しを述べがちな日本のエコノミスト
長年続いたデフレで「悲観バイアス」が強化?
日本では、エコノミストが楽観的な見通しを述べて外れると、「アホかバカか」と批判されがちである。ところが、悲観的なことを述べて外れても批判されない。そのため、エコノミストに「悲観バイアス」があるように思われる。
この悲観バイアスは、1998年から2012年まで15年間にもわたって予想外に長く続いたデフレで、強化されたように見える。
確かに98~12年のデフレ期には、物価上昇率は平均-0.2%程度のデフレで、名目賃金も平均-0.9%下落。経済成長率は平均0.6%と、1%程度の中期的な潜在成長率を下回った。失業率は平均4.6%と完全雇用水準の3%を大きく上回っており、就職氷河期(93~04年)ともかなり重なっていた。
しかし、13年から始まったアベノミクス(大胆な金融緩和、機動的な財政運営、構造改革による成長戦略の三本の矢)の下で、日本経済はデフレを脱却。物価は2~3%上昇、経済は1%台前半の安定成長軌道に復帰しており、失業率も2%台半ばの超完全雇用・人手不足の状況にある。
にもかかわらず、エコノミストは、トランプ関税の影響や世界経済の分断化、デジタル化の遅れなどを挙げて、悲観的な見通しを述べている。
一方、株価はこのところ極めて好調で、日経平均株価は10月下旬に5万2000円を突破した。これは、日本企業の収益が史上空前のレベルに達していることを反映したものであり、PER(株価収益率)は18倍程度であって、過去の平均の16倍程度に近く、“バブル”とはいえない。1980年代後半に、PERが50倍や70倍の水準に達して、完全にバブルだった状況とは全く異なる。
もちろん、現在の日本企業の収益を押し上げている一つの要因は円安である。輸出企業の収益を増加させている1ドル=150円台の円安が、120~130円程度の為替水準に戻れば、企業収益が減少し、株価にも影響が出てくるとは思われる。それでも、90年代のバブル崩壊による株価の暴落のようなことは、起こりそうにない。