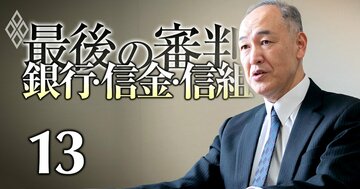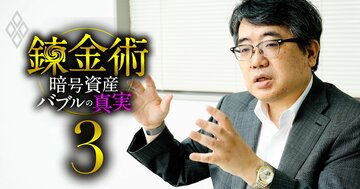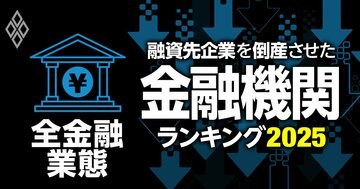Photo:Bloomberg/gettyimages
Photo:Bloomberg/gettyimages
金融庁は、金融機関の健全性が損なわれる前に、経営改善の対応を促す「早期警戒制度」を見直す。人口減少や金利変動が与える影響を加味し、収益性や健全性にもたらすインパクトをより精緻に捕捉するためだ。長期連載『金融インサイド』の本稿では、このタイミングで見直しに動く背景と制度上の問題点に加え、金融庁内部でひそかに検討される“新たな活用案”を明らかにする。(ダイヤモンド編集部 高野 豪)
「転ばぬ先の杖」の早期警戒
金融庁が制度の見直しに着手
早期警戒制度は2002年、自己資本比率規制(バーゼル規制)上で問題のない金融機関に対し、健全性の維持・向上のために早めの経営改善対応を促す仕組みとして導入された。
この制度は、監督指針にも「必ずしも直ちに経営改善を求めるものではない」と記されているように、強制的に措置されるものではない。一定基準を下回ると自動的に発動する「早期是正措置」に対し、その一段階前の「転ばぬ先の杖」(同庁)的な制度とも位置付けられる。
金融庁は制度の運用にあたり、持続可能な収益性や将来にわたる健全性、信用リスクなどに関する具体的な指標を設けている。その指標の水準に抵触した金融機関に対し、原因分析や対話を通じた改善を促す立て付けだ。改善が必要と判断した場合、検査の実施や報告徴求命令なども発出できる。
10月28日、首相の諮問機関である金融審議会の作業部会で、この制度の見直し案が示された。金融庁が将来の人口動態を示す公的データや金利の見通しなどを加味してシナリオを設定。関連する指標に反映し、より深度あるモニタリングを行うのが特徴だ。
イメージしやすいように例を出そう。公的データが示す人口動態を基に、預金者の年齢構成と掛け合わすことで、相続で流出する可能性の高い預金量が予測できる。有価証券運用では、金利上昇シナリオを当てはめることで、保有債券の含み損が将来どれだけ拡大するかを把握できる。
このような分析を基に、金融機関に対してより将来を見据えた改善対応を促せるというわけだ。作業部会に出席した委員らが、この見直し案におおむね賛成したことを踏まえ、同庁は「(制度を)見直していきたい」との意向を示す。
制度見直しには監督指針の改正が必要となる。今後、作業部会の報告書で方向性を示し、26年6月末までに改正案が公表される見通しだ。
では、なぜ金融庁はこのタイミングで制度見直しに動くのか。取材を通じて見えてきたのは、他の制度との関係と制度運用面での課題だ。
次ページでその実態を解き明かし、取材で浮上した金融庁の新たな活用案について、つまびらかにする。