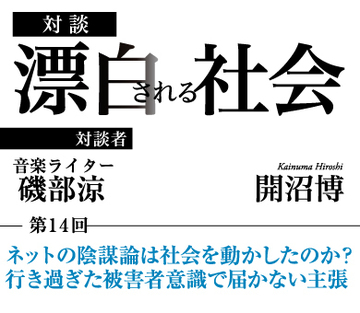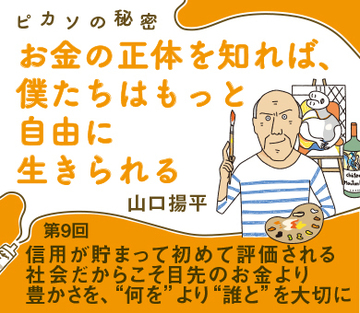売春島や歌舞伎町といった「見て見ぬふり」をされる現実に踏み込む、社会学者・開沼博。そして、クラブ規制で注目を浴びる風営法の問題に正面からぶつかり、発信をつづける、音楽ライター・磯部涼。『漂白される社会』(ダイヤモンド社)の刊行を記念して、ニュースからはこぼれ落ちる、「漂白」される繁華街の現状を明らかにする異色対談。
両氏による対談最終回では、社会運動を継続するために何をすべきなのか、そのヒントを探る議論へと話は深まる。
カッコよさの現実に気づくと冷めてしまう
開沼 ふたたび方法論に戻ってしまいますが、風営法の問題について、磯部さんはこれからどういう活動をされていきますか?
 磯部涼(いそべ・りょう)
磯部涼(いそべ・りょう)音楽ライター。1978年、千葉県千葉市生まれ。1990年代末から商業誌への寄稿を開始し、主に、日本のマイナーな音楽の現場について執筆してきた。著作に、『ヒーローはいつだって君をがっかりさせる』(太田出版)、『プロジェクトFUKUSHIMA!2011/3.11-8.15 いま文化に何ができるか』(K&B)、『音楽が終わって、人生が始まる』(アスペクト)がある。
近年は、日本のクラブ業界においてタブー視されてきた風営法の問題解決に取り組み、同問題をテーマにした『踊ってはいけない国、日本』(河出書房新社)と、その続編『踊ってはいけない国で、踊り続けるには』(同)の編著者を務めた。
撮影:植本一子
磯部 前に述べたように、風営法改正運動に関してはオープンとクローズのバランスが重要だと考えているので、現段階では公にできないことも多いのですが、別に大それたことをやろうとしているわけではなく、例えば業界に対して地域との関係性の構築を促すだとか、まぁ、言ってみれば、凄く地味でつまらない行動を続けていきたいと思っています。
今日の話は、自分が、社会運動の地味さに嫌気が差してアンダーグラウンドに向かっていったところから始めました。つまり、また振り出しに戻ったということなのかもしれません。地味な社会運動でしか動かせない、変えられない現実があることに、ようやく気づいたというか。
開沼 一周して戻ってきたと。
磯部 いまの若い人たちの間でも、社会運動に対する興味が高まっていると言われますが、実際はどうなんでしょうね?
開沼 僕が大学に入学したのが2003年ですが、ちょうどその頃は「ホリエモン前夜」だったんですね。渋谷でIT企業がボコボコ生まれて、「ビットバレー」なんて言われていたのが90年代末から2000年前後。その後、ITバブルは崩壊しましたが、その残り香はあり、「金儲けがカッコいい」「社会に名を轟かせるのがイケてる」といった前提はそれなりにありました。
しかし、それから丸十年が経過して何が変わったのかというと、「利益追求だけじゃなくて、社会貢献がカッコいいよね」という文脈が出てきました。社会起業家や若いNPOの代表、コミュニティデザイナーなどがメディアに登場し、「ああいう風になりたい」という大学生も増えています。
とてもいい流れで、これからも盛り上がってもらいたいと思いますが、これもまたいずれ変化していくでしょう。たしかに、今出てきている「カッコいい社会貢献」という価値の付け方・見せ方は、人の動員に役立つものの、やはり社会貢献に本気で取り組んだり、大規模に行うなかで、カッコいい部分だけでは成立しなくなります。つまり、かつてのヒルズ族への憧れとも通じますが、実際に持続可能な形をつくることはとても地味だったりするわけです。
例えば、ソーシャルビジネス、コミュニティデザインの結果、田舎でおじいちゃん・おばあちゃんがイキイキしてますという、希望に溢れるメディア映像の裏側には、めちゃくちゃ地道な介護職の方たちが何百人もいて、それではじめてその「カッコよさ」が成立している。
そういうリアルに気づいたときに「カッコいい社会貢献」が冷める部分もあるでしょう。ただ、これは批判ではなく、そうだとしても、どうこのいい流れを持続させるかを考えておく必要はあるということです。 そうしたギャップをうまく調停しながら、「糾弾・吊るし上げ型」だけではない、広義の社会運動・社会貢献がカッコいいという流れを、今後いかに生き長らえさせるのかが課題なのかなと思っています。