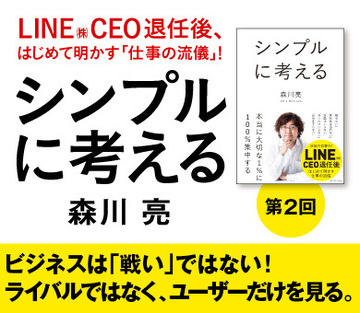構造改革を経て多くの日本企業が過去最高益を記録している。とはいえ、未来に目を向ければ「持続的成長の実現」は依然として大きな課題だ。そして、持続的成長を可能にする鍵は、時代を先取りして自らが変革し続けることができるかどうか、すなわち組織の「自己変革力」である。
多数の企業変革に関わってきたデロイト トーマツ コンサルティング パートナーの松江英夫が、経営の最前線で果敢に挑み続ける経営トップとの対談を通じ、持続的成長に向けて日本企業に求められる経営アジェンダと変革の秘訣を解き明かす。
連載16回目は、日本発の仕掛けである「イノベーションセンター」の仕掛けを中心に持続的成長につなげるための市場・顧客とのつながりの作り方について、デュポン名誉会長・天羽稔氏にお話を伺う。
<顧客とのつながり>
顧客との関係性を強固にした「イノベーションセンター」という仕掛け
松江 日本法人としてのデュポンは、グローバルに日本発のものを多く生み出しています。イノベーションセンターはその典型だと思います。
 天羽稔(あもう・みのる)
天羽稔(あもう・みのる) デュポン株式会社名誉会長 徳島県出身。ワシントン州立大学工学部卒業後、デュポンファーイースト日本支社(現 デュポン株式会社)に入社。自動車関連事業本部部長、名古屋支店長、開発企画部部長、エンジニアリングポリマー事業部長、取締役、副社長などを経て2006年9月より代表取締役社長。2013年1月、代表取締役会長兼デュポンアジアパシフィックリミテッド社長。2014年9月より現職
天羽 社長になったときにまず考えたのは、「デュポン・ジャパンは、どんなミッションを持つのか」ということです。日本社会に貢献することと、あとはデュポングループにどういう貢献ができるのか、その二つが我々の大きな使命だと考えました。後者のグループ貢献ではマーケットが小さい分、数字的にはインパクトが出せないことで苦労しました。どうしてもグローバルに事業部制が強いとすぐに日本の売上の議論をするわけです。縦の組織の中で、そういうふうに考えてしまうのは仕方ない面でもありますが、それは違うだろう、という意識付けをやってきました。その中で一つ貢献できるのは、世界初のものをマーケットに送り出すことでした。その起点として名古屋にイノベーションセンターを設立し、世界初のものがずいぶん生まれています。
松江 イノベーションセンターとは、あらゆる素材を顧客に見てもらい、初期段階から要望をもらって、ソリューションをつくるという仕掛けですよね。
天羽 私は昔からコンサルティングが、営業やマーケティングの主流と思っていて、モノを売るというよりも、その人が困っていることに対して、こちらがどう解決するかを考えてきました。結果として、うちのものが売れればいいし、売れなくても、これはこういう材料を使ったほうがいいですよとか、この材料が高すぎるといった、技術営業みたいなことをずっとやってきました。特に私が入社した当時、担当していた製品はキロ10万円ぐらいしたんです。当時、ナイロンは1キロ500~600円ぐらいですから、すんなりとは買ってくれません。そんなものを扱っていたこともあり、仕事はやっぱり相手が困っていることへのソリューションをどう上手く作るかだと思っていたので、イノベーションセンターのようなことを思い付いたわけです。
松江 技術というよりも営業やマーケティングの発想がはじまりなのですね
天羽 そうです。当時、私が見ていた樹脂部隊は、自動車メーカーとの取引も大きかったのですが、営業はいつも点で当たるのです。おまけに事業部は身近な売り先に行って最終エンドユーザーにはほとんど行ってない。しかも相手は何十万人の企業だから、2~3年すると組織もどんどん変わってしまい、せっかく築いた関係がすぐなくなる。
それを私は変えたかった。最終エンドの人が何を求めているかは相手によって異なるし、相手がこちらにどのようなものがあるかを知っていたら、もっといいものを提供できます。ただし、最終エンドに行くためには組織を使って対処していかないといけない。当社にはこんなにも広い製品があるのだから、点より面で当たったほうが良いと思っていました。会社も、仕事も大きくするためには、組織力をもっと使ってお客さんと一緒にならないといけない。お客さんと一緒になることで大きなトレンドができるのです。
松江 事業部制の縦割りが強い御社にとっては、事業横断的な取り組みは難しかったのではと思います。何がきっかけとなってグローバルに認められたのですか。
天羽 前会長のチャールズ・ホリデーのときに繊維部門を売却した際、その分のレベニューを大きくしたいという与件があって、全社員に対してアイデアが求められたのですが、そのときに提案したことがきっかけです。
それで提案して会長が「いいよ」といってくれたわけですが、その後は総論オーケー、各論駄目といった典型的な話になった。本社で15部門のリーダーと話しても賛成は3で、反対が12。会長が賛成しているので、誰も正面から「駄目だ」とは言わないのですが、「これはなかなかいいよ」のあとに「But」が付いてくる。それでなかなか進まなくなり、結局は2年ぐらいかかりました。
松江 やはりグローバルレベルで初めての企画を通すのは大変なのですね。
天羽 1年も提案してオーケーがもらえないので、会長が日本に来たときに、「駄目だったら、もうやめよう。もしOKなら、全部この金額を出してくれ」と伝えたら、金額的には大した額ではないのですが「駄目だ」と言われました。あとからわかったのですが、彼らがダメだと言っていたのは、コーポレートが負担すると、事業部側に当事者意識が無くなりビジネスが一緒についてこなくなるとの疑念があったんです。だから、最終的には事業部がそれぞれ分担金を払ってやっていく方向に持っていき話をまとめたのです。
松江 イノベーションセンターでは、顧客の技術者を直接に呼び込んで、一緒にソリューションを作っていくスタイルですよね。
天羽 ここで大切なことは単に「モノ(製品)を売る」ことではないのです。大切なのは顧客の課題を同じ目線で解決をする。たとえば、新しい製品アイデアを形にするときに、デュポンが持っている幅広い製品提案だけでなく、顧客のアイデアを理想的な形で実現化するためにサポートをしましょうという話をする。もしコスト面で課題があったら、ここでこうデザインを変えたらもっと安くできるのではないかとか、色々な相談ができるんです。初期の段階でそういう話ができれば、採用になる可能性が高いものがつくれますよね。
松江 一度そういうモデルをつくると、お客様と持続的な関係ができあがってきますよね。持続的成長には「お客様といかに長い付き合いをしていくか」がポイントだと思います。
天羽 名古屋のイノベーションセンターの一つの指標は「リピーター」です。ただの製品展示場ではなくて、いろいろな「ソフトウェア」があります。展示場というのは「静」、止まっているんですね。イノベーションセンターは「動」なんです。毎月180人くらいが来ますが、そういうソフトウェアがあって、その中でやっぱり我々も常に動いているんです。